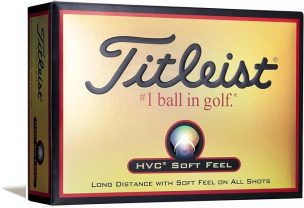「命はつなぐもの」だろうか?――NHKでも特集された自閉症作家が新作で「結婚」「死」「生きる意味」を考える
公開日:2017/5/26

現在活躍中の作家で、もっとも多くの言語に翻訳されている日本人作家は村上春樹氏。ではその次の作家は誰か? 世界30カ国語に翻訳されている『自閉症の僕が跳びはねる理由』(KADOKAWA)の著者・東田直樹氏である。その東田氏の最新作、『自閉症のうた』(KADOKAWA)が5月26日(金)に電子書籍化された。
東田氏について知らない人もいるだろう。彼は重度の自閉症で人と会話することが困難だ。けれども、キーボードや文字盤のポインティングにより、コミュニケーションが取れる。13歳のときに発表したエッセイから、会話が困難な自閉症の人の内面を伝え、その思慮の深さ、豊かな感受性に多くの人に衝撃と感動を与えた。これまでにエッセイ、絵本、小説などを発表している。
今作では、NHKドキュメンタリーで放送された、英語版の翻訳者デイヴィッド・ミッチェル氏を訪ねるアイルランド旅行記を中心に、二人の対話や短編小説が収められている。
■「生きる」ことに思いを馳せる
旅行記から始まる本書だが、相変わらずの東田氏の豊かな表現力、そして達観した人生観は静かな感動を誘う。
アイルランドの古き要塞を前にして、戦いに命を落とした人を思い、生のありがたみを再確認する。これだけなら、普通の人も思い馳せることができる。けれども東田氏は、その先をも見通す。
「命のバトン」という言葉があるが、これは命をつないで生きることを意味しているのだろうか。…
命がつなぐものであるなら、つなげなくなった人は、どうなるのだろう。…
他の人がバトンをつないでくれるという意見もあるだろう。でもそれなら「命は完結する」でいいと思う。
人生を生き切る。
残された人は、その姿を見て自分の人生を生き続ける。
誰もが「命のバトン」を渡せる立場にいられるわけではない。普通のカップルでも不妊に悩んでいたり、不慮の事故で子どもを亡くしたり、「バトン」を渡せない立場の人もいる。彼らの生に意味はないのか。そうではない。生き様そのものが「命」の価値であり、誰しも平等に生をまっとうするべきだ。そう背中を押してくれる。
念のために東田氏の情報を付け加えると、重度の自閉症だけではなく、知的機能にもハンデがあるとの診断を受けている。しかし彼が綴った言葉を読むと、私たちがどれだけ色眼鏡でものを見ているかを再認識させられる。会話ができない、だから何も考えていないわけではない。むしろ表現できない分、人生や生き方について考えに考え尽くしている様子が見て取れる。
■自閉症の人にとって、結婚や死はどう映るのか
翻訳者のデイヴィッド・ミッチェル氏との往復書簡からも、東田氏の卓越した観察眼や人生観を知ることができる。ミッチェル氏が、インタビュアーとして、東田氏に結婚や死生観、創作活動について率直に聞き、それに東田氏が素直な感情で答えている。このやりとりから、いわゆる健常者と東田氏の共通するところ、また異なる視点について知ることができるだろう。
だがもっとも東田氏に近づけたと思えるのは、小説「自閉症のうた」である。小説では、加奈子という重度自閉症の人物の目を通して物語が進む。
加奈子は14歳で特別支援学校に通う。会話ができず気持ちが高ぶると体を制御できない。そして加奈子には毎日ルーティンが存在する。例えば授業の前に12ピースのパズルを必ず完成させること。また帰り道ではマンホールのふたを踏まないと気持ちが落ち着かない。けれども内面は普通の中学生と同じで、家族を思いやる気持ちや、これから将来がどうなるのか不安も持っている。
■自分が生きる意味は何か?
物語はある日、加奈子のルーティンであるマンホールのふたを踏み損ねたところから始まる。マンホールのふたをうまく踏めなかったため、加奈子は道路へ走り出し交通事故に遭う。そこで入院中に四肢が不自由な少年、高雄と知り合う。
自分と同じようにコミュニケーションに不自由している高雄に親しみを感じると同時に、自分より不自由な境遇に哀れみを持つ。夢のなかで、加奈子と高雄は、自由に動き回り会話をする。けれどもそれは叶わない。東田氏は、加奈子に次の様な言葉を語らせる。
もしかしたら私たちは、あんな風に自由だったはず。
話もできず、人の世話がなくては生きられない二人。疲れ果て生きることが嫌になっても、誰にもわかってもらうことなどない。…私や高雄君が生きる意味は何なのだろう。
恐らく東田氏は物心がついてから、自分の生きる意味を何百回も、何千回も考えてきたのだろう。その答えの一つがこの小説には描かれている。
物語の終盤で、それまで意思表示をまるでしてこなかった高雄が、わずかに人差し指を動かし、加奈子と視線を交えるシーンがある。健常者から見ればわずかな動作だが、加奈子と高雄君はそれだけで思いを共有する。そして彼は哀れみの対象ではなく、知性に無限の可能性を秘めていることを発見する。さらにこのような思いを胸に抱く。
今、ここで私たちは息をしている。この世界に存在している。私たちが生きていることに意味などいらない。
いつしか雲が流れ青空が広がった。生きているから命は美しいのだ。
私たちは理不尽な人生に意味を求め、占いや宗教、SNSに頼る。でも生に意味付けするのは他人ではない、自分なのだ。だから自分と他人を比べ、ひがんだり哀れんだりするのは愚かな行為である。
わずかな物語から東田氏は生の本質を説いてくれる。そしてハンデのありなしを超越し、あらゆる境遇の人に突き刺さる。この本は、あらゆる人の根源的な悩みが描かれている。人生に行き詰まったときにぜひ手に取ってほしい一冊だ。
文=武藤徉子