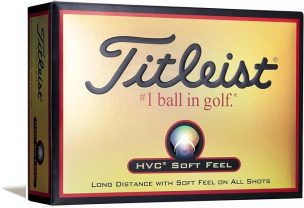西村賢太のネガキャンは炎上マーケティングか、本気か
更新日:2017/11/26
 ついに封切られた、山下敦弘監督の映画『苦役列車』。公開前から原作者・西村賢太の「どうしようもなくつまらない映画」といった“酷評ぶり”が話題を呼んでいたが、公開初日の舞台挨拶では「こうして映画になって、とても嬉しく思っています」と発言。ネット上では「(酷評は)炎上マーケティングを狙っているのでは?」というような意見も飛び交っている。果たして、西村の真意はどこにあるのだろうか?
ついに封切られた、山下敦弘監督の映画『苦役列車』。公開前から原作者・西村賢太の「どうしようもなくつまらない映画」といった“酷評ぶり”が話題を呼んでいたが、公開初日の舞台挨拶では「こうして映画になって、とても嬉しく思っています」と発言。ネット上では「(酷評は)炎上マーケティングを狙っているのでは?」というような意見も飛び交っている。果たして、西村の真意はどこにあるのだろうか?
現在発売中の『新潮』8月号に掲載されている山下監督との対談では、冒頭からR-15指定であることに不満を漏らすという穏やかでない雰囲気でスタート。西村本人がモデルとなっている主人公・貫多を演じる森山未來が関西出身であることにも触れ、「台詞回しが僕の考える貫多とは違いました」とバッサリ。たしかに貫多は「嫌味なくらい東京人であることに誇りを持って」おり、そこにプライドが集約している人物。映画でも貫多が喋る江戸弁のニュアンスを大事にしてほしかったようだ。
西村の批判は続く。準備稿の台本では「小説を書きたいんですよね」となっていた台詞が、映画では「なんか書きたいんですよね」に変更されていたこと。康子が貫多に貸す本をマニアックなものにしてほしかったこと。さらに、風俗のシーンに対しても「あの頃は口でのサービスはなかったですよ」とチクリ。実に細かなところまでチェックしていることがわかる。一方で、原作にはない康子という人物を演じる前田敦子については、「人気アイドルが演じることでの集客効果ということを除けば、オリジナルキャストはいらなかったんじゃないかと僕は思います」と、“客寄せパンダ”としては容認しているよう。
こうして見ていくと、『週刊現代』で行われた六角精児との対談で西村本人が述べているように、「あちこちでネガティブ・キャンペーンをはっていて、そのほうが宣伝になるといういやらしい考えもあるのですが、原作者が褒めてはダメだと思うんです」というのが本音のように思える。しかし、前出の山下監督との対談では、“宣伝のため”とは言い切れない感情を爆発させる場面がある。西村がプレスでは好意的だった態度を一変させたことに、山下監督が「正直腹立たしく感じました」と意見をぶつけた際の返答だ。
「原作者は、見てつまらなかった映画をどこまでも褒めなきゃいけないとでもいうんですか? それこそ僕としてはよほど腹立たしい。(中略)讃辞だけを聞きたければ、自主制作で仲間うちのみでの上映にすればいい」(西村)
大手芸能事務所に所属することからもわかるように、タレント性の高さに人気が集まる西村。しかし作家としては、近年ではめずらしいほどの無頼派だ。映画『苦役列車』をめぐる一連の酷評は、炎上という姑息なマーケティングを狙ったというよりも、自作にこだわりを持つ作家としての一面が露わになった騒動といえるのではないだろうか。