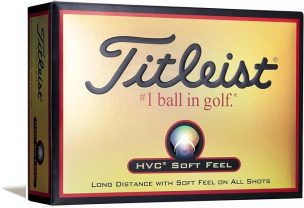第3回野性時代フロンティア文学賞 『罪の余白』 芦沢 央インタビュー
更新日:2012/9/11
反省とは何だろう?――娘を失った父親から絞り出されるその言葉は〝反省〟という概念に潜む闇を顕わにする。それを免罪符として駆使する人々、そこに存在する悪意。その真実を相手に見てしまった時に怒りや哀しみが行き着く先――〝どんな償いを相手に求めれば、自分は納得できるのだろうか〟という問いが『罪の余白』の出発点だったと芦沢さんは言う。
「代金に代わり、小さな悪戯を求める店ができたことから、町が崩壊していくスティーヴン・キングの『ニードフル・シングス』という小説があるのですが、それぞれの小さな欲望や猜疑心、悪意が大きなうねりを持ってくる、その構造が面白いなと。そこに影響を受け、エンターテインメントとして思いついた仕掛けが、娘を死に追い込んだ少女たちに対する、償いの形でした」

あしざわ・よう●1984年、東京都生まれ。千葉大学文学部卒。出版社勤務を経て「第3回野性時代フロンティア文学賞」を受賞した本作でデビュー。執筆中の第2作は「本作の延長線上にある、さらにミステリー色の強い作品」だという。
高校のベランダから転落死した加奈。死の理由は何だったのか、娘の悩みになぜ気づけなかったのかと自分を責める父・安藤。だが、同級生だったという少女が現れたことで、明るみになる痛々しい娘の真実を前に、加奈を死に追いやった咲と真帆に償いを求める戦いは始まる。そして、いじめという悪意を自分たちの正義に塗り替えた少女たちは……。スリリングな心理戦は、次々と視点が変わる構成のもと、うねるような展開を見せていく。
「完全な正義がないように、悪意にも完全なものはない。それを描くためには、ひとつの視点では描ききれないと思いました。悪意のもとになる妬みや欲望って、誰にもある部分で、それを拾いあげるのは、私にとって物語の動機として一番強い。そこが小説の行き着く目標ではないけれど、作家として掘り起こしていきたいところです」
追い詰められていく少女たちが吐露する想い。仲良しグループ内での嫉妬や確執、ひとりでいることを周りに見られることへの恐怖、母親との確執……10代の頃、誰もが抱いたことのある息苦しさが物語を覆う。自分を守るために、社会や大人を見下し、恐ろしい知恵を駆使する咲。咲に見捨てられないよう、必死で罪を取り繕う真帆。その張りつめた空気の中に登場するのが、心理学者である安藤の同僚であり、アスペルガー症候群的一面を持つ女性・早苗だ。
「実は早苗は書きあげた時にはいなかったんです。ラストのどんでん返しには成功したけれど、読み返した時、そこに着地するのは間違いではないかと。早苗という要素が入ったことで、ラストは大きく変わり、安藤と少女たちがつくりだす張りつめた空気に緩急が生まれたと思います」
12年前から文学賞に応募を続け、作家を目指していたという芦沢さん。当初は純文学を書いていたが、数年前、エンターテインメントに転向。届けたいのは“必ず楽しんでもらえる仕掛け”だという。だが、読者が受け取るのは、そればかりではない。読者モニターから寄せられたメッセージには、登場人物に対する深い共感、そして物語から受け取った救いへの想いが綴られていたという。
「私自身、小説を読み、様々なことを乗り越えてこられたので、本作が読者の方の力になったと聞き、こんなに幸せなことはないなって。手放しのハッピーエンドではないけれど、登場人物それぞれに今後の余地が残るラストまで、一気に読んでいただければうれしいです」
芦沢 央 / 角川書店 / 1365円
高校のベランダから転落した加奈。娘はなぜ死んだのか――加奈の悩みが明らかになった時、償いを求める父の戦いは始まった。悪意を持ち、対抗してくる少女たちとの間に繰り広げられる心理戦。ラストのどんでん返しが胸を突く。