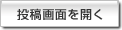2005年12月号 『その日のまえに』 重松清
更新日:2013/9/26
その日のまえに
| ハード : | 発売元 : 文藝春秋 |
| ジャンル:小説・エッセイ | 購入元:Amazon.co.jp/楽天ブックス |
| 著者名:重松清 | 価格:1,543円 |
※最新の価格はストアでご確認ください。 |

あまたある新刊の中から、ダ・ヴィンチ編集部が厳選に厳選を重ねた一冊をご紹介!
誰が読んでも心にひびくであろう、高クオリティ作を見つけていくこのコーナー。
さあ、ONLY ONEの“輝き”を放つ、今月のプラチナ本は?
|
2005年11月05日
『その日のまえに』 重松 清 文藝春秋 1500円 advertisement |
| 自身の余命があと三カ月と告げられた俊治は、衝動的に小学校の頃の思い出の浜を訪れる。幼い頃、海に消えた同級生、そしてその両親を思い出しながら、自分が死に向かうことをゆっくりと認識し始める「潮騒」。 余命いくばくもない妻を連れ、最後の思い出にと新婚時代に過ごした土地を巡る夫。指でなぞるように二人で過ごした時間を刻みつけようとする夫婦を描く「その日のまえに」。そしてついに訪れる「その日」。妻の死をゆっくりと受け入れていく家族を描く「その日のあとで」。 誰にも必ず訪れる死。“その日”を巡る7 つの短編。 |
  |
|
しげまつ・きよし●1963年、岡山県生まれ。早稲田大学卒業後、出版社勤務を経てフリーライターに。91年『ビフォア・ラン』で作家デビュー。99年『ナイフ』が坪田譲治文学賞、『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。『ビタミンF』で第124回直木賞を受賞する。 |
  横里 隆 (本誌編集長。ものを表現するのは怖い。今も毎号震えながら本誌を作っている。スナフキンなら言うだろう。「つまりそういうものなのさ」と) この主題で泣いてたまるか!果たして号泣……完敗でした
|
  稲子美砂 (本誌副編集長。主にミステリー、エンターテインメント系を担当) 日常は「その日」に向かっている
|
  関口靖彦 (今月個人的に楽しませていただいたのは、牧野修さんの長編『記憶の食卓』。こちらはカニバルかつサイコなストーリーで、人がばんばん死にまくります) まるで、眠る前の一杯のお茶。おだやかに胸に沁みる物語
|
  波多野公美 (年に一度のお楽しみ、けらえいこさんの『あたしンち』11巻が発売されました! ←この巻から編集を担当。帯はなんと、角田光代さん! 眠る前に読んで、ほっこりしてほしい一冊です) 深い哀しみを知るのは愛することを知る人
|
  飯田久美子 「誰か」を失うのが、怖いのは……
|
似田貝大介 (12月に発売予定の『幽』4号。今回は雨の山に登ったり、廃墟で夜中に怪談会を開いたり……。着々と進んでいます、ご期待ください!) ちょっとでも後悔しないようにいまを強く生きていたい
|
  宮坂琢磨 (実家の本が処分される。今となっては入手が難しいモノもある。救出に行きたいが、ヒマがない) “死”が訪れるその日のまえに何を残せるのだろうか 自身の死を見つめているこの短編の登場人物は、余命の間に、何を残せるのかを考えている。「ヒア・カムズ・ザ・サン」は既に息子に何を残すのかを考え始めている母と、母の病に抗おうとする息子の物語だ。息子に対する、母親のちょっと自分勝手だけど優しい想い。それは強ければ強いほど、息子に哀しみを呼び起こす。母から何かを受け取り、少しだけ成長した息子の姿に、死んで受け継がれる何かを意識させられた。余命という概念を、生き物が子どもを残せなくなった瞬間からとする、という説を聞いたことがある。その意味では多くの人が余命を過ごしているけれど、人間は想いや心を残すことができる。それは素晴らしいことだ。 |
| イラスト/古屋あきさ |

読者の声
連載に関しての御意見、書評を投稿いただけます。
投稿される場合は、弊社のプライバシーポリシーをご確認いただき、
同意のうえ、お問い合わせフォームにてお送りください。
プライバシーポリシーの確認