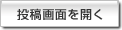2005年07月号 『風味絶佳』 山田詠美
更新日:2013/9/26

あまたある新刊の中から、ダ・ヴィンチ編集部が厳選に厳選を重ねた一冊をご紹介!
誰が読んでも心にひびくであろう、高クオリティ作を見つけていくこのコーナー。
さあ、ONLY ONEの“輝き”を放つ、今月のプラチナ本は?
|
2005年06月06日
『風味絶佳』 山田詠美 文藝春秋 1290円 advertisement |
| 70を越えた今でも、若い男を“必需品”と呼んで真っ赤なカマロの助手席にのせ、孫の働いているガソリンスタンドに足を運ぶ祖母。そんな祖母やその周辺の人々の生き方を理解できない大学生を描く、表題作「風味絶佳」。 父の再婚相手は、大学時代に片思いをしていた女性だった。彼女に対する想いと、再婚し変わってゆく父の姿の違和感から、二人の幸せな生活を目の当たりにしながらも、わだかまりを捨てきれない章造は、家族旅行の席でついに爆発してしまう「春眠」。 職業も年齢も様々に、恋人同士の関係を中心として、彼らをとりまく人々の関係性を描く6 つの短編集 |
  |
|
やまだ・えいみ●1959 年東京都生まれ。85 年にデビュー作『ベッドタイムアイズ』で文藝賞を受賞後、87 年『ソウル・ミュージック ラバーズ・オンリー』で直木賞、91 年『トラッシュ』で女流文学賞、2001 年『A2Z (エイ・トゥ・ズィ)』で読売文学賞を受賞する。他の著書に『ジェシーの背骨』『PAY DAY!!!』など多数。 |
  横里 隆 (本誌編集長。最近、ジムノペディとdoris ばかり聴いている。詠美さんに薦められた日出克もいい。音楽はコミュニケーションにおける“おやつ”かも) すごいすごいすごい!短篇集のマイルストーン
|
  稲子美砂 (本誌副編集長。主にミステリー、エンターテインメント系を担当) 恋愛って何?その解答のいくつかが示されている どれも心地いい小説だと思った。男たちの仕事に対しての向き合い方、女たちの視線、恋愛の情景としての共感、漂う雰囲気。技巧的にすごいなと思ったのは「アトリエ」。地下汚水槽の清掃をする裕二がスナックで見つけた暗くて内気な麻子を娶る。以来、2 階で行われる彼女を空っぽにして愛を注いでいく作業。「私は舌を差し入れ、唾液を流し込みました。出来る限り沢山。」裕二の淡々とした語り口がかえって淫靡で切なくて、ある種の狂気が感じられて……ラストもすばらしい。好きな作品は「春眠」。二人がなぜあれほどに深く結びついてしまったのかも感覚的にわかった。弥生とおとうちゃんの臆面もないどうしようもなさがよくて、二人のやりとりを読んでいるだけでニヤニヤしてしまう。「ぬくぬく」はまさに恋愛の醍醐味ですよね。 |
  岸本亜紀 (『新耳袋第十夜』ついに最終夜刊行です!その翌週の24日には『幽』3号が発売になります。初夏の怪談、お楽しみください!) 山田詠美の小説は、どんな儚い人生でも、風味絶佳なものにしてくれる
|
  関口靖彦 (本書の上手さは、まさに衝撃。こんなふうにものを書くなんて、自分には絶対一生永遠に出来ないと悟らされて悲しかった) “憐みに肉体が加わると恋になる。”誰がこんな文章を書けるだろうか
|
  波多野公美 (個人的にも念願だったバレエ特集を担当。雄弁な身体を持つダンサーの肉声とは?超豪華メンバーです。ぜひご一読を!!) 静かに漂う不安定要素が小説のリアリティを増幅する あの山田詠美が腕によりをかけて料理した「恋」の小説が、おいしくないわけがない。この短編集には、まったく種類の違ういくつもの恋が、味わい豊かに描かれている。味わいを深めているのは、それぞれの恋がはらむ不安定要素だ。例えば、「間食」の寺内が頬を赤らめる相手。「海の庭」の三十年ぶりに再会した二人の距離感。森永ミルクキャラメルを“私の恋人”と呼ぶ「風味絶佳」の不二子。「春眠」のおとうちゃんと弥生。どの場合も、彼らの不安定さは克明には描かれず、ただ、行間から静かに漂ってくる。それは、みな身に覚えがあるけれど、小説に昇華するのは困難な感覚だと思う。山田詠美はやっぱりすごい、と思った。 |
  飯田久美子 (寝坊ばかりしているので「起こし太郎」を買おうと思い、調べたら10 万円もすると判明しガッカリ) 若いものにはまだ負けないというベテランの凄み
|
   宮坂琢磨 (このまえ、身体がどんどん膨らんで部屋から出られなくなる夢をみました。体重が夢見さえ悪くする) わからないって
|
  |
『ベルカ、吠えないのか?』 古川日出男 文藝春秋 1800円 太平洋戦争末期、キスカ島に取り残された日本帝国軍の4頭の軍用犬、エクスプロージョン、正勇、北、勝。玉砕した勝以外の3頭は、アメリカ軍に捕獲され、その血は世界中に広がることになる。彼らの子孫はベトナム戦争をはじめとする東西の冷戦構造の狭間で、様々な運命に翻弄されながらも、ソビエト連邦のある工作員の下で一つの血統として集結することになるのだが……。 |
   宮坂琢磨 |
軍用犬の歴史が示す生のダイナミズム 犬はきらいだ。今まで3回ほど襲われたから。けれど、本作を読み終わった時には「犬」に感情移入していた。それも、一頭一頭の個体ではなく、「犬」という種に対してである。この作品は派生、分化しながら、お互いにそれと知らず運命的な邂逅を果たす、3頭の血統を、徹底的に犬に寄った視点でザッピングしていく。生み、あるいは生ませるために生き、そして死んでいく。人間に飼われながらも、血と本能の衝動に突き動かされ、同族を殺し、主人の死体をも食らう犬たちの生は凄絶だ。 彼らの血は「ベルカ」と名付けられた1 頭の犬が背負い、受け継いでいくのだが、その運命の皮肉さを知ることができるのは読者だけだ。 犬はなにもわからない。滅び行く者とその血を受け継ぐもの。「種」を見続ける読者の立ち位置は、手塚治虫の『火の鳥』にも通じる、 どこか寂寞としたものだ。 |
| イラスト/古屋あきさ |
読者の声
連載に関しての御意見、書評を投稿いただけます。
投稿される場合は、弊社のプライバシーポリシーをご確認いただき、
同意のうえ、お問い合わせフォームにてお送りください。
プライバシーポリシーの確認