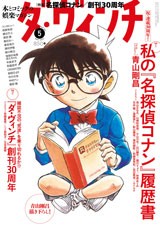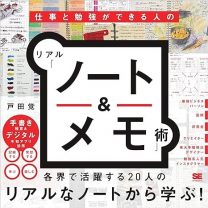中国では屋台も農家もスマホ決済! 日本のキャッシュレス決済との違いは?
公開日:2018/6/25

現金文化が根強い日本にも、いよいよキャッシュレス決済、スマホ決済の波が訪れつつある。大手IT企業が次々とスマホを利用した決済サービスを開始し、対応する加盟店も増えてきた。とはいえ、まだまだ「現金のほうが安心」と考えている人や、「便利なのはわかるけど、どのサービスを使ったらいいかわからない」と足踏みしている人が多いのではないか。そんな“現金好き”の日本人に対して、最近のメディアでは「中国ではほとんどがスマホ決済になっている。日本は世界に遅れている」というような論調がよくみられる。しかし、本稿で紹介する『なぜ中国人は財布を持たないのか』(中島恵/日本経済新聞出版社)は、それを「ごく一面的で短絡的な見方」と指摘し、中国でスマホ決済が急速に発展してきた背景や、今起こっている具体的な潮流の変化を解説している。
■お年玉もスマホで決済
中国のスマホ決済はどれくらい進み、普及しているのだろうか。2017年3月時点で、よく使われている主なサービスとその利用者数は、電子商取引最大手のアリババが運営する「アリペイ」(約4億人)と、メッセージアプリを運営するテンセントの「ウィーチャットペイ」(約8億3000万人)。これらを利用することで、公共料金をはじめ、各種交通機関、病院、飲食店、映画などのほとんど全ての支払いができるのだという。お年玉や慶弔金の送付にまで利用されているというから、どれだけ人々の生活に浸透しているのかがわかる。高機能のレジ機がない個人商店や屋台でも(本書表紙にあるように)QRコードが用意されていて、スマホでそれを読み取り、金額を入力することで決済できるのだ。
■かつてニセ札に悩まされてきた中国
中国でスマホ決済がここまで普及した背景には、インフラへの設備投資の遅れや、現金に対する信頼性の低さが関係しているという。例えば、地下鉄の券売機や自販機では使用できる紙幣の種類が限られており、著者も小銭が足りず窓口で両替したことが何度もあったそうだ。また、日本では普通に暮らしていてニセ札と出会うことはないが、かつての中国は、いつニセ札をつかまされるかわからない状況だったという。著者の友人によると、深夜にタクシーの料金を支払う際、運転手が乗客から受け取ったお札を「この札は汚れているから取り替えてくれ」と一度返してくることがある。そのときに突き返された汚れたお札が実はニセ札とすり替えられていて…なんてこともよくあったのだとか。このように現金の不便さやニセ札のリスクが、スマホ決済の急速な普及を後押ししてきた。
日本と中国では根本的に、現金利用における事情がまったく異なる。中国では急速に広まったキャッシュレス決済・スマホ決済も、現金決済のインフラがきちんと整備され、現金の信用性が非常に高い日本では、その進行はゆるやかなものになるだろう。変化の背景には必ず理由がある。本書で、変わりゆく中国の“今”を知ることは、日本のマネーの未来を考える上でも役に立つはずだ。
文=中川 凌