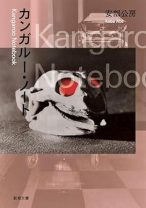目前で体験した9.11テロの瞬間、そしてPTSD。ある女性作家の人生再生の物語
更新日:2018/12/21

2001年9月11日に発生した、米国同時多発テロ(以下、9.11)。4カ所で同時に起こったこのテロによる犠牲者は合計で、日本人24人を含む2996人が亡くなり、負傷者は6000人以上とされている(ウィキペディアより)。
乗っ取られた旅客機が世界貿易センタービルのツインタワーに激突していくシーンが、各国のメディアで繰り返し放送され、テロという名の狂気を世界が目撃した。
現在、国際ジャーナリストとして活躍し、『日本が売られる』(幻冬舎)『政府は必ず嘘をつく 増補版』(KADOKAWA)などのベストセラー著書を持つ堤未果氏は、9.11の朝、世界金融センタービル20階にある野村證券ニューヨーク支社のオフィスにいた。秘書業務を行う現地採用の米国野村証券の社員として勤務していたのだ。
世界金融センタービルは、ツインタワーの真横にあり、連絡通路でつながっている。朝9時の始業まで、まだわずかに時間があった。そこで堤氏が、日本から買ってきたお菓子のお土産を各デスクに配ろうと動いた、まさにその時だった。
ガガーン!という轟音がとどろいた。
頭の奥がびりびりと痛み、私は反射的に両手で耳をふさいだ。
(何なの?)
咄嗟(とっさ)に壁の時計に目をやると8時46分をさしている。
窓のそばにいた社員の一人が叫んだ。
「オーマイゴッド! あれを見ろ!」
ほかのトレーダーたちと一緒に川とは反対側の窓際に駆け寄ったとき、私はあっと叫び声をあげた。
向かい側の世界貿易センタービルの上部から、オレンジ色の炎とどす黒い煙がいきおいよく噴出している。
「戦争だ! 戦争が始まった!」
誰かが大声でわめきたてた。(後略)
■テロが起こっても冷静だった日本人スタッフたち
これは、2004年の著書『グラウンド・ゼロがくれた希望』(ポプラ社)に堤氏が記した、9.11発生時の生々しい様子だ。2011年から14年までの3年間にわたる、9.11を含む外的体験と内的葛藤を綴った本書によれば、口々にわめきたてながらオフィスを飛び出す外国人スタッフたちとは対照的に、オフィス内の日本人スタッフたちは、テロ発生直後もいたって冷静だったそうだ。
しかし、金融センタービルまでが激しく揺れる事態に至り、ビルにいた人たちは一斉に階段に殺到し、窒息寸前の状態で地上へと逃げ出すことになる。
地上に出た堤氏がセンタービルを振り返ると、その目に焼き付いたのは、逃げ場を失った人たちがツインタワーの上層階の窓から転落する姿だったという。
この日から堤氏は、強烈なショック体験がこころのダメージとなって発症する「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」という、見えざる敵とも戦う日々を送ることになる。
飛行機やテロのニュースを見るだけで、呼吸困難になり、心臓が苦しくなる。毎晩決まってテロの悪夢にうなされる。
堤氏が負ったこころの傷が深かったのは、テロばかりが原因ではない。9.11以後、米国は対テロ戦争という大義の下、アフガニスタン、イラクへと侵攻した。
米国野村証券の社員以前は、国連機関と人権NGOで働いていた堤氏は、世界の貧困、人種差別、紛争に対する意識が高く、報復戦争へは断固反対だった。しかしアメリカの選択は違った。
高校卒業後、夢を追い渡米して14年間過ごし、永住権まで申請した堤氏の「大好きだった自由の国アメリカ」は、9.11以降、姿を消した。このことも堤氏のPTSDを悪化させた。
■帰国後の人々との出会いがPTSDを癒していく
そして、作家になるという夢もぼやけ始め、「失ったものを取り戻そう」と、堤氏は帰国を決意する。本書後半では、帰国後の人々との出会いが、狂いかけた堤氏の運命の歯車をアジャストしていく様子が記されている。
帰国後堤氏は、イラク戦争で米軍が劣化ウラン弾を使ったことを告発する米国人科学者や、9.11で身内を失ったものの、それでも米国の報復戦争に異を唱える活動を行う志ある米国人らの活動を、通訳者として支える。
さらには自身の体験を講演の場で語り、小説として発表する活動なども開始する。こうして、新たな目標を見つけ出すことでこころの傷を癒し、再び渡米できるまでに自分を取り戻していく。
その後の著作で堤氏は、『ルポ 貧困大国アメリカ』(岩波書店)、『増補版 アメリカから〈自由〉が消える』(扶桑社)などに代表されるように、かつては自身も憧れた「アメリカンドリーム」とは対局にある、米国のリアルをレポートする。
告発へと駆り立てるもの、それは、裏切られたという悲しみや憎しみからではない。むしろ、愛があるからこそ、より良い国になってほしいという願いを込めて、真実を明かす。それこそが、グラウンド・ゼロがくれた、堤氏にとっての「希望」だったのかもしれない。
文=町田光