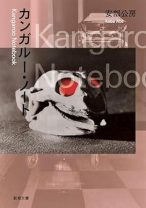海外研究者たちは“日本史の平和さ”に感心している!? 古代の戦いから日本のかたちが見えてくる!
公開日:2019/1/24

まもなく平成が終わる。今上天皇が誕生日の会見で「戦争のない時代として終わることに心から安堵」と述べられたが、明治に鎖国が解かれて以降、緊張した国際関係の中で諸外国との争いが絶えなかった歴史がある。だが、それ以前の時代に目を向けると、日本人の争いといえば主に「内戦」。地理的条件も手伝って、外国からあまり攻撃されることがなかった日本では、「武士」が台頭してから日本人同士による「内戦」が繰り返されてきたのは一般に知られるところだ。
第一線の古代史研究者・倉本一宏氏の『内戦の日本古代史(講談社現代新書)』(講談社)を読めば、そうした内戦はいきなり武士の世になって勃発したわけではなく、壬申の乱など古代から繰り返されてきたことがよくわかる。よくもこんなに狭い国土でそんなに争ったものだ…と思ってしまうが、実は日本の内戦の数や規模というのは、中国やヨーロッパ、イスラム社会と比較するとかなり小さなものらしい。実際、著者の友人の海外研究者たちは「みな日本史の平和さについて感心(かつ感動)している」というのだ。
なぜ「平和」なのだろう? 本書では倭王権の成立時から武士の世の胎動までの内戦を通じて日本のかたちを捉え直そうと試みるが、その中からみえてくる答えの鍵は「王権」のあり方だ。
古代日本で確立された王権が平和だった大きな理由は、なにより「世襲」を支配の根拠にしたことだ。中国のような易姓革命(天命により天下を治める天子の家(姓)に不徳の者が出れば王朝は交代するという考え方)を否定したため、王権を倒そうとする勢力も生まれなければ、王権側も易姓革命に対応するための武力を持たなかった。さらに王権を狙える勢力を考えても、たとえば藤原氏は始祖が天孫降臨神話の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に随伴した天児屋根命(あめのこやねのみこと)であることから、天皇家に背くことははなから考えにくいものであったろうし、平氏や源氏にしても天皇家から分かれた氏族であり、すでに神話に基づいて確立された王権の血筋があるなら、それを否定するより外戚関係を結んで権力を持つほうが効率的でもあっただろう。
そうした結果、日本においては王権そのものに対して戦闘をしかけた例はほとんどなく、皇太子の交代を企てたクーデター計画や権力者の更迭を要求した軍事行動、中央政府の出先機関である国府を襲撃した事件があっただけで、戦いをしかけた側には「国家や天皇に対する反乱」という認識はほとんどなかった(平将門にしても最初から朝敵だったわけではなかったという)。本書に取り上げられた古代の内戦の背景や戦況からも、諸外国のような「殲滅戦」はなく、和平・懐柔路線の外交交渉がメインで大規模な戦闘はほとんど起きていないのは確か。そうした姿勢は日本という国の特質を象徴するものだという。
とはいえ本書の最後で紹介されている平安時代中期の前九年・後三年の役で力を発揮した「武士」は、それ以前とはまるで違う残虐さを示す。元は京都の貴族に出自を持つ軍事貴族がなぜそこまで変貌したのか――そんな日本人の変節に思いを馳せるのも面白い。なお文中には参考文献が細かく紹介されているので、興味のある方にはこの先の読書案内にもなりそうだ。
文=荒井理恵