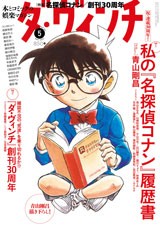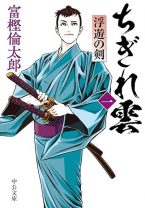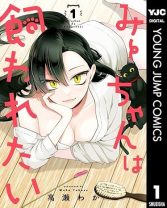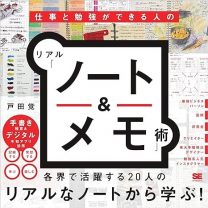「マジョリティ」からはこぼれ落ちる人々がいる。いまこそ、「公」を考えるべき時代だ
公開日:2019/11/19

「みんな」とは実際のところ、誰なのだろうか。
「表現の自由」とは何なのだろうか。
『公の時代』(朝日出版社)では、アーティスト集団Chim↑Pomの卯城竜太氏と、二度の鑑別所収監を経て東京藝術大学大学院を修了した松田修氏の2人が、「公」「個」「表現の自由」といったテーマについて、とことん語り合う。難しいテーマだが、身構える必要は決してない。彼らは、あるときは飲み屋のようにラフな語り口で、またあるときはアカデミックなテンションで、「公」の本質へと切り込んでいく。
“もちろん多様性は大事だよ。知ってるわ。けど本当に、嫌いなモンや理解できないモンまで受け入れる余裕や覚悟がみんなあんのか?って疑問がある”と松田氏は言う。多様性という言葉は、ともすれば便利だ。「みんな違ってみんな良い」と掲げられるスローガンは、果たして「公」を推進しているのか、あるいは後退させているのか。
例えば代表的な「公」として、公園がある。大きな公園が民営化される流れを経て、“「公」園ではなく「マジョリティ」園へとデザインされてきている”と本書では問題提起がなされる。「公」は全員のものだが、「マジョリティ」からはこぼれ落ちる人がいる。社会にはさまざまな人がいて、「公」園が担ってきた役割は、あらゆる人々が分け隔てなく居られることではなかったか。松田氏は、“「把握不能な人たち」が寄りつかなくなった”とその問題点を指摘する。
今、真に必要とされる「公」について、彼らはさまざまな時代や国を参照しながら、対話を進めていく。
福住廉氏、青木淳氏といった鼎談のゲストにも注目だ。あいちトリエンナーレ2019で芸術監督を務めたジャーナリストの津田大介氏との鼎談は、「表現の不自由展・その後」が始まるより前に行われた。炎上して中止となり、再開後もさまざまな波紋を呼んでいる本展についての鼎談、そして騒動後に著者の2人で行われた対談の様子には、ヒリヒリさせられる。“予言の回としか思えないよ”と松田氏が振り返るその鼎談は、さまざまな立場から読まれ、批判も含めて議論されるべき章だ。
「公」や「表現の自由」は今、不完全な概念であったことをまざまざと突きつけられている。現代の新たな「公」や「表現の自由」について、考えていかなければならない。
本書が令和元年に出版されていることは、これから大きな意味を持つだろう。
文=えんどーこーた