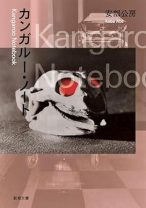犬や馬をパートナーとする動物性愛者「ズー」の性生活。ダイバーシティの先には何がある?
更新日:2020/5/11
濱野さんがドイツで出会った「ズー」は22人、うち19人が男性で女性は3人だ。12人(全員男性)は生来のズーであることを認め、「自分ではどうにもできない、あらかじめ備わっていた感覚だ」と語る。そして17人のパートナーが犬で、犬と馬の両方が4人。中には牛と答えた人もいる。取材を続ける中で濱野さんは、多くのズーたちが言っていた、
「ズーの話とは動物とのセックスの話ではなく、動物や世界との関係なんだ」
という言葉から、動物のパーソナリティと人間との“対等性”について考えるようになる。そして彼女は、ズーたちが対等性を保つためにどう動物たちと向き合い、どうセックスしているかを研究し、描きだす。中には、動物と性交しないという人もいるし、していても人間が挿入するケースは皆無だったそうだ。
濱野さんは本書において、ズーであることを「動物の生を、性の側面も含めて丸ごと受け入れること」と結論付ける。確かに彼ら彼女らは、性欲を満たすために動物を利用しているのではない。非難されることがある自身の性癖を自覚しながら、それでも動物を心から慈しみ、愛する人間たちだ。
本書を読み進めていくと、そのことがよく分かる。「ズー」とAVなどで消費される“ジュウカン”の違いは、まさにここにあるだろう。もっとも濱野さんは、「人間のセクシュアリティやセックスには善悪はつけようがない」とも触れているが…。
最初のうちは「こんな取材をよくしたものだ」という気持ちがあった。しかし、読了後に許容できるようになるわけではないが、動物性愛への理解はわずかながらも得られた気がしている。それはなによりも、本書には動物性愛者を興味本位で煽情的に語る記述がないからだ。
そしてズーたちから勇気を得た濱野さんが未来へ進もうとする姿勢からは、痛いほどの「生への肯定」が伝わってくる。この本は動物性愛だけではなく、1人の人間が傷と向き合い、強さを得ていくまでの過程も描かれているのだ。
ズーたちが、そして取材した著者が性と向き合って生を考える姿勢を受け入れるか、あるいはただひたすら嫌悪し拒絶するか。読み手自身の考えが存分に試される作品と言えるだろう。
文=玖保樹鈴