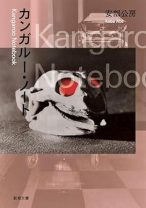【第162回芥川賞受賞作】長崎の離島が迎え、そして見送った人々の歴史を穏やかに描く、古川真人『背高泡立草』
公開日:2020/1/30

毎回、大きな社会ニュースとなる芥川賞と直木賞の発表。先日、第162回目となる同賞が発表され、芥川賞には古川真人さんの「背高泡立草」(すばる/集英社)が、直木賞には川越宗一さんの「熱源」(文藝春秋)が選ばれた。「受賞作は欠かさず読む!」という本好きも多いが、先日24日に芥川賞受賞作の『背高泡立草』(集英社)の単行本も発売されたとあって、書店の店頭も絶賛盛り上がり中だ。
ところで、すでに単行本化された中堅作家までの大衆向け作品が対象となる直木賞に対し、雑誌などで発表された純文学の新人作品を対象とする芥川賞では、今回のように受賞決定時点では単行本が未発売ということもある。作家自身もあまり世間に知られていないことも多く、受賞記者会見には「どんな作家さんなのだろう?」と関心が集まるもの。
今回の受賞者・古川真人さんは、実はこれまでも「縫わんばならん」「四時過ぎの船」「ラッコの家」の3作品が芥川賞にノミネートされてきた実力派であり、今回は4回目にして念願の受賞。会見で喜びを爆発させるかと思いきや、「これからどうなるんだろう。なんでこうなったんだろうという気持ち」と戸惑いを素直に語り、その朴訥とした姿は作品世界にどこか重なるものだった。
連休の最終日、福岡に住む大村奈美は母の実家・吉川家のある長崎の離島まで、今は使われていない海辺の納屋の草刈りに駆り出される。朝早く、車で迎えにきた母に「どうして草など刈る必要があるのか?」と問い詰めても「みっともないから」と相手にされず、途中で親戚と合流してみなで島へ渡ることになる。島には吉川家の<古か家>と<新しい方の家>があるが、祖母が亡くなった今はいずれも空き家であり、ふと気になった奈美は伯父や祖母の姉に昔の家の話を聞いてみる。そして知ったのは元々<新しい方の家>のある場所で酒屋をしていたが戦中に統制が厳しくなって廃業し、満州に行く農家から家を買って<古か家>に移り住んだ吉川家のこと。いつの時代にも島には出て行く人とやって来る人がおり、この2つの家はそうした人々の往来を静かに見つめてきたのだった――。
長崎の離島を舞台にした物語は、わいわいと親族で草刈りをする「現在」の視点から、ふとタイムスリップするように家が見つめてきた島を往来した「過去」の人々(戦時中に大陸に渡った農家、江戸時代に蝦夷に渡った鯨とり、戦後に難破船から救われた朝鮮人など)の人生の断片が交錯する連作短編。たっぷり織り込まれた九州地方の方言のためか、全編にどこか遠い国の話を聞いているような不思議な穏やかさがあり、ポツポツと語られる普通の人々の話に耳を傾けていると、時代を問わず誰にでも「それぞれの物語」があるのだという当たり前のことに気づかされ、そのおもしろさに引き込まれる。実はこれまでの古川さんの作品はいずれもこの本と同じ「長崎のとある島」が舞台となっており、一部では「九州サーガ(一族を描いた叙事小説)」とも呼ばれる。物語の着想は福岡出身で祖母が長崎の島に住むという古川さん自身のルーツから得たものというが、生きていた人の分だけ物語はあるとすれば、この一族の物語はこの先ももっともっと続いていくのかもしれない。
物語の後半、主人公の奈美は草に埋もれた納屋を見つめながら、過去と現在・親が老いていく未来、そして福岡で仕事をする明日と島にいる今…そんなさまざまな「時間」の重なりにぼんやり思いを馳せる。長い旅をしてきたようで実は1日しか経っておらず、まるで長い夢を見ていたかのよう。読む側もそんな不思議な「時間」を味わえる1冊だ。
文=荒井理恵