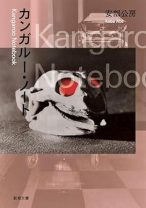“亡き夫の香り”を求める女性が抱える後ろ暗い秘密とは――どんな香りでも作る天才調香師の切なく優しい物語
公開日:2020/4/25

振り返れば毎日、何らかの香りに包まれ、癒されながら生活しているように思う。朝は、コーヒーの香りで目覚め、出掛ける前にはお気に入りのピオニーの香水をひと吹き。お昼は焼きたてのパンの香りに誘われて、気がつけばパン屋に足を踏み入れているし、疲れた夜はアロマの加湿器をつけて眠りにつく。そういえば、ふとした瞬間に嗅いだ香りで、とうに忘れていたはずの懐かしい記憶がブワッとよみがえることもある。香りは、想像以上に人と密接に関わっていて、深い世界なのかもしれない。
千早茜さんの『透明な夜の香り』(集英社)は、そんな「香り」の持つ力や不思議が、心に傷を負った繊細な人間たちの目線で、身体のすみずみまで深く染み入るように綴られた小説だ。
物語は、心に傷を負い、部屋にこもりきりだった元書店員の一香(25)が、古い洋館の家事手伝いのバイトの面接に行くところから幕を開ける。香料植物や薬用植物でいっぱいの庭園がある重厚な雰囲気の洋館には、小川朔という天才調香師が暮らしていた。
短髪で、かすかに灰色がかった目、まるで“紺色”のような暗く見えてかすかに色が溶けている声をした朔は、幼なじみの探偵・新城と共に、完全紹介制の「香り」を作るサロンをひっそりと営んでいる。朔は、恐ろしいほど鼻が利き、匂いから、言葉にしなくても他人の体調や感情までわかってしまう。そのため、「感情の浮き沈みが人より少ないから体臭がうるさくない」という理由で採用された一香でさえも、働く間は、身体や髪や衣服を洗うもの、肌に塗るもの、すべてを朔が調合した品を使うことが条件での採用だった。
朔のもとには、一筋縄ではいかない「秘密」を抱えた依頼人が多く訪れる。「亡き夫の香りを作ってほしい」と頼みながら、本当は不倫相手の匂いを求めている女性や、ひどく不愛想な人気女優。美しい女優が朔に香りを定期的にお願いするその真相にも驚いたし、病気で下半身が動かなくなってしまった息子のために「生きる力を呼び覚ます香り」をお願いした父親に、「蝶の匂い」を手渡しながらも、彼を挑発せずにはいられなかった朔の心の内にも胸が苦しくなった。
朔は、依頼人の嘘も、匂いから即座に見抜く。だが、それを指摘することはあっても、依頼された香りを作ることは、その先の破滅を予想できても止めることはしない。その無情とも思える仕事の仕方に一香は戸惑いを覚える。しかし、常に人よりずっと多い情報量を取り入れながら生きてきた朔の生きづらさや孤独を思い、ほんの少しずつ距離を近づけていく2人の変化も、切なさとときめきが入り混じり、胸がしめつけられた。
本書は他にも、洋館の庭の管理を任されている老人・源次郎から食材をもらい、朔のレシピで一香が振る舞う数々の食事もとても美味しそうで心に残った。「苺とミントのスープ」や「烏龍茶と金木犀の花のジュレ」、「スターアニスとレモンの仔羊クリーム煮」など、自然に囲まれた空間で、身体に良いものを口にし、一香はずいぶん健康になる。朔は言う。
「匂いは残るんだよね、ずっと。記憶の中で、永遠に。みんな忘れていくけれど」
人より優れた嗅覚ゆえに、誰にも理解されることのない寂しさを抱え続ける朔と、そんな朔ゆえの能力に、確かに救われていく人々がどこまでも繊細に、時に生々しく描かれている。あちこちにちりばめられた香りにまつわる薀蓄に驚きながら、しなやかで優しくも、芯のあるとても美しい文章に心を奪われる1冊だ。
文=さゆ