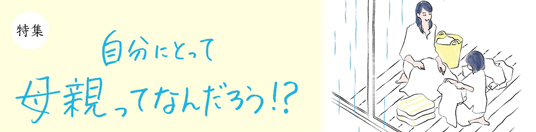「自分の家庭が壊されたり、仕事のペースが乱れることは、絶対にしたくなかった」――『万葉学者、墓をしまい母を送る』にみる、親孝行とは?
公開日:2021/5/9

『万葉学者、墓をしまい母を送る』(上野誠/講談社)は、万葉集の研究者として知られる著者が、家族が誰も住まなくなった故郷の「墓じまい」をし、老いた母を引き取って介護を始め、看取るまでを記録したエッセイである。
とはいえ、タイトルにわざわざ「万葉学者」と付けたことが象徴するように、単なる墓じまい、介護体験記ではない。祖父、祖母、父、兄、母と、中学時代から著者が目にしてきた家族の死をもとに、日本の葬送文化の変化を考察しているのが特徴。和歌の研究を通じて古の日本の文化や死生観、家族観も深く知る著者ならでは作品といえよう。
だから、というわけではないだろうが、一般的な介護体験記にあるような苦闘、感動は前面に出てこない。いや、故郷に住む母を遠く離れた自身が生活する土地に呼び寄せ、仕事と両立させる苦労話もあれば、介護を通じて得た母と息子の相互愛に触れる部分もあるにはある。ただ、それを一歩引いた、どこか客観視しているように書いているため、「重苦しさ」「暑苦しさ」が少ないのだ。故に、墓じまい、介護、葬送といった、いつか直面するとわかっていながら目を背けがちな話題について、エッセイという形であることも含め、語弊があるかもしれないが、気軽な感覚で読めるともいえる。
不思議なのは学術的要素も持つ歴史・民俗的考察が、介護や葬送をする側にとって、ひとつの「救い」に感じた点があったことだ。たとえば著者は母の介護を担っていた兄が亡くなった後、故郷の母を引き取り、介護を引き継いだ。ただ、そこにはこんな思いもあった。
「とにかく、できることはたくさんしてやって、楽しませて、歓楽を尽くさせて死なせたい、と。
しかし、自分の家庭が壊されたり、自分の仕事のペースが乱れることは、絶対にしたくなかった。」
「身内の死にいたる介護は、個々人の生活を崩壊させるような脅威になっているのである」
母の介護について「ものごとを割り切って考えるようにしてきた」と著者は明言する。親の介護を自らの手で手厚くしてあげたい。しかし、それだけに日常の全てを捧げるのは難しい。環境、時間、資金など、さまざまな限界はある。そんな事情を考慮せず、「〜すべき」と非難する関係者がいるのも、またよくあること。第三者の無責任な物言いが、介護の当事者に罪悪感を与えることもある。
介護においても、看取り後の葬儀においても、「できること」「してあげたいこと」はできる限り行うが、無理をしないのが著者のスタンスだ。その理由に触れる部分では、節々で社会や家族関係の変化の歴史・民俗的な考察が入ってくる。それは、研究者に「だから昔通り、理想通りできなくても当然」と説かれているようで、罪悪感も薄れ、楽な気持ちになる。まるでカウンセリングでも受けているような不思議な感覚だった。
著者は母の介護において、自身の手が回らないとき、頼めることはアルバイトとして雇った学生に頼む。人によっては親不孝な行為に映るかもしれないが、母にとっては、肉親でないからこそ甘えを素直に出せる時間にもなったという。若い人との会話も楽しんでいたそうだ。
母はいつまでも子を気にかけるもの、とよくいわれる。子が自身の介護を献身的に担うことは、母にとってうれしいことだろう。ただ、一方で自身のために子が何か多大な犠牲を払っていたら、それはそれで気に病む理由になるかもしれない。
「できる範囲で、やれることをやる」
現代日本の介護と葬送を巡る親孝行は、それくらいの感触でも十分ではないだろうか。
文=田澤健一郎