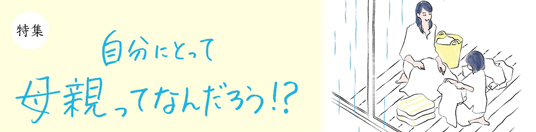誰もが経験する『母親を失うということ』をどう受け止めたらいいのか?
公開日:2021/5/12

現役の精神科医で小説も執筆している岡田尊司の『母親を失うということ』(光文社)は、母の死を契機に、自分と母との想い出や印象的なエピソードを綴った本だ。ただし、本書は著者が幼稚園から小学生だった頃の記憶を追想したもの。親戚や友達との交流も事細かに描かれているが、メインとなるのは母親と著者に関係するエピソードだ。
その母は若い頃、経済的に困窮する家を支える一方、自宅では親類からも辛くあたられる。その悲壮感溢れる描写は読んでいるこちらも鬱々となってくるほどだ。特に祖母の奇行は長く続いた。今でいう認知症なのだろうが、母への罵詈雑言を大声でわめきちらし、彼女の人格を根本から否定。時には母に向けて唾を吐き捨てたという。
著者の職場でもある精神医療の現場では、言いたかったことを我慢してきた患者に、包み隠さず本音を言うことが称揚される。だが、著者はその風潮にも疑義を呈する。当然だろう。著者やその母は祖母の独りよがりの世迷言を聞かされて育ったのだ。
著者は母に対してアンビヴァレントな想いを抱いている。母の帰りが遅いと癇癪を起こし、責め立てる。高額な本を買ってくれないとグズり、おもちゃ屋では店でいちばん高い商品をねだる。母はそんな風にわがままだった著者に寛容だった。著者は自分のことはいつも後回しだった母に、今は申し訳なさを覚えている。
ただ著者は、母の人生を評して「滑稽なほどに幼稚で、醜く、自分勝手で、馬鹿げたものだった」「心配性で、人目ばかり気にして、悲観的」だったと分析する。母を愛し甘えながらも、彼女のネガティヴな側面にも冷静なまなざしを向けていたのだ。
本書を執筆することは著者にとってリスクが高かっただろう。懇意にしていた親類に関する人柄を含め、当時著者が置かれていた人間関係まで暴露するのだから。また、母にまつわる記憶を洗いざらいしたためるのは、親不孝にあたるかもしれない。だが、母亡き後、すべてを綺麗事で済ませるのにも違和感もあった。著者はそう書いている。
母の逝去後、家庭や職場では彼女の痕跡は薄れてゆく。母と親しかった人たちの記憶も風化して、いつかその存在は忘れられてゆくだろう。そして、この本を書いた著者のモチベーションはおそらくそこにこそある。よく、高齢になると自費出版で「自分史」を書く人がいるが、本書はそうした趣味的な域を完全に超越している。もっと重く、暗く、生々しい事実が次々に明らかにされてゆくのだ。
なお、帯には「著者初のノンフィクション」という惹句が躍っているが、筆者にはこの本は私小説にあたる作品だと思える。私小説のおおまかな定義は、作者の実体験に範囲を限定し、身辺や自分自身のことを語り、内面描写を主としている小説のこと。作者が直接に経験した事柄を素材にして、そのまま書かれた小説を指す用語である。そして、この本は上記の定義に当てはまると思える。
例えば私小説では、障害児である息子を抱える大江健三郎氏の『個人的な体験』や、夫の浮気により妻が狂っていく島尾敏雄氏の『死の棘』。あるいは、私小説の救世主といわれる西村賢太氏の諸作と並べて挙げられる作品。本書はそう評するに値する作品である。
ちなみに、自らも私小説で芥川賞候補となった作家で比較文学者の小谷野敦氏の『私小説のすすめ』(平凡社)によれば、昭和やそれ以前の私小説では、事前承諾なしに小説のモデルにさせられた人物が作家を訴えることもしばしばあったそうだ。
当然、本書には親類に関する細かい記述もあるわけで、彼ら彼女らにとっては不本意なところがあるかもしれない。それを承知の上で著者は事実に基づく本作を上梓した。それほどまでに切実なテーマだったのだろう。
また、機能不全の家族の中で辛い思いをしてきた小林エリコ氏の『家族、捨ててもいいですか?』(大和書房) や『わたしはなにも悪くない』(晶文社)のような告白調のノンフィクションも、やはり私小説的とも取れる。 小林氏の一連の作品同様、本書も「令和の私小説」と言えるのではないだろうか。
文=土佐有明