【第9回】電子書籍の本場アメリカの実際をNYで聞いてみた
公開日:2013/11/29
3週間ほどアメリカに出張していました。その際、ニューヨークで出版エージェントとして活躍されている大原ケイさん(@Lingualina)にお話を伺う機会がありましたので、アメリカの電子書籍市場の動向や、今後の展望などを聞きました。日本の作品を米国で出版するための仲介役を務める大原さん。ネット上では歯に衣着せぬコメントで知られる方ですが、日本から見ていると意外と誤解してしまっているアメリカの現状を、米国で出版ビジネスに長く関わった経験を交えながら丁寧に解説頂きました。
日本の作品を海外で知ってもらうために
――米国でエージェント業を営みながら、出版や電子書籍事情を紹介される大原さんですが、今のお仕事をされるようになったのはどういう経緯からですか?

おおはら けい
出版エージェント。ニューヨークの大学でジャーナリズムを学び、講談社アメリカやランダムハウス講談社に勤務後、独立。
現在は、日本の著者・著作を海外に広めるべく奮闘中。また、電子書籍を中心にしたアメリカ出版業界の裏事情、NYローカルネタ、日米文化比較に関する記事を新聞、雑誌に幅広く寄稿する。
著書に『ルポ 電子書籍大国アメリカ』(アスキー・メディアワークス /KADOKAWA)
など。
大原:父の仕事の関係で子供の頃から米国と日本を行き来していました。そしてニューヨークの大学のジャーナリズム科に通ったあと、現地で働きたいと考えて、講談社の現地法人に就職したのがこの業界に足を踏み入れたきっかけです。7年ほど日本の百科事典の英語版の制作などに携わったあと、いったん版権業務の下請けや翻訳などを行うフリーランスになりました。
――現在のエージェントのお仕事とは異なるお仕事だったんですね。
大原:はい、当時景気が良かったこともあり、何となく食べられたら良いかなという感じで何でも引き受けていました。でも2001年の9月11月に起こった同時多発テロが一つの転機になったんです。当時私はウォールストリートで仕事をしていて、ワールドトレードセンターが直接見える場所にはいなかったのですが、崩れ落ちる建物から煤だらけで逃れる人たちを目の当たりにして大きなショックを受けました。「人間いつ死ぬか分からない。後悔しないようにしなきゃ」と考えを改めるきっかけになったんです。
その時たまたま目にした世界最大の出版社「ランダムハウス」のアジア部門立ち上げの囲み記事を見て、担当者にもっと詳しい話を聞きに行ったら協力することになりました。そこでの仕事――主に米国の書籍の中から、日本で受け入れられそうな作品を選んで日本での出版を働きかける――を通じて日米の商慣習の違いなど、どこにハードルがあるのかを身をもって知りました。著者の日本での知名度って世界では全く通用しなくて、「新人」として売り出す覚悟が必要ということもそこで痛感したんです。海外で知られている日本の著者って村上春樹さんくらいではないかと思います。
――なるほど。私もアメリカに来て思うのは、日本の漫画作品はとても人気があるのに、著者や出版社の名前は知られていないことの不思議です。家電や自動車はメーカーの名前がこんなに認知されているのに……。
大原:そうですね。日本最大手の出版社でも、海外支社となるとせいぜい20名前後のスタッフしかいませんから、なかなか海外で認知度を高めてヒットを生み出すのは難しいんです。日本文化に特に関心が強い一部のコアな読者には例えば「KODANSHA」という名前はよく知られてはいますが。
――そういった日米のギャップを乗り越える経験が、改めていまフリーのエージェントになられて活かされている、というわけですね。
大原:はい。いまはランダムハウスで主に行っていたのとは逆に、日本の作品を翻訳して米国での出版につなげるエージェント業務を行っています。アメリカの編集者のなかには日本発のコンテンツに興味を持っている人も多いのですが、日本語が読めないのがネック。日本の出版事情を理解していて、話ができて、米国で「この本ならこの編集者に話せば興味を持ちそうだ」ということが分かるエージェントって実はほとんどいないんです。
――先日、講談社が米国の動画配信大手Crunchyrollと組んで、日本でのマンガの雑誌掲載と同時に米国でも配信を行う取り組みを始めて注目を集めました。そういった取り組みについてはどうご覧になっていますか?
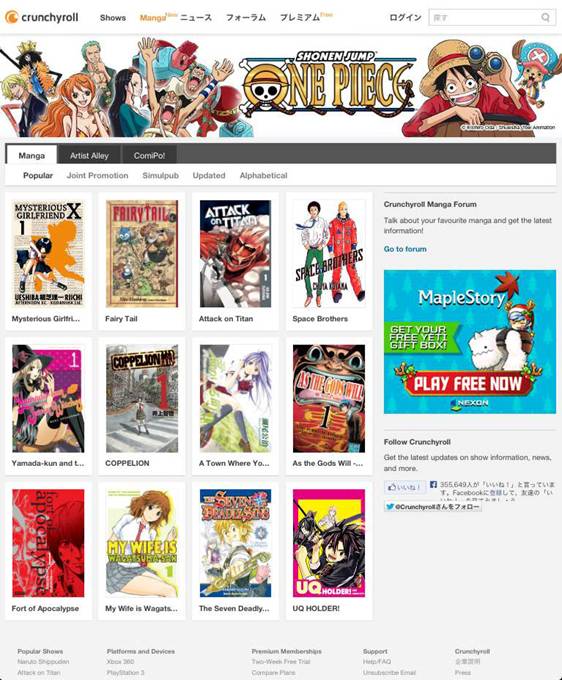
大原:もっと早くても良かったのではないかと正直思いますが、重要な取り組みです。こちらでは探せばネットで海賊版が無料で読めるという習慣が身についてしまっていますから、後手に回った感がありますが、最大手が率先してこれに取り組むというのは評価すべきです。
雑誌掲載と同時に翻訳版も配信するということは、それだけ締め切りが早くなり著者にも負担があるのではないかと思います。これを機に週刊連載という世界にあまり例がない仕組みも見直すきっかけにしてはどうでしょうか。実際、日本の漫画家さんは忙しすぎて、海外でプロモーションを行おうにもこちらに来て頂ける余裕がなかったりします。それって、まさに著者やそれを支える出版社の知名度を上げる機会を逃しているわけなので、もったいないですよね。こちらでは文芸誌も季刊がほとんどなので、「日本には月刊が多い」と言うとビックリされるんですよ(笑)。
実際アメリカの電子書籍市場ってどうなんでしょう?
――2010年にアメリカの電子書籍市場についての著書も出された大原さんですが、現在の状況をどうご覧になっていますか?
大原:「アメリカでは電子書籍が本の売上の半分を占める」という誤解もあるようですが、あれは今年10月にアマゾンのキンドル担当役員がドイツのブックフェアで『今年中にアメリカで売られる本の半分以上がお店でではなくてオンラインで売買される(Eブックと紙の本を含む)ようになる』と発言したものを読み違えたのだと思います。実際は、本の売り上げ全体では電子書籍は30%も行っていないと思いますね。もちろん、作家や作品によっては電子書籍の方が多い、という例もありますが。7割くらいは紙の本を選択しているのが実情です。
――高価なハードカバーと、安価だけれど紙や印刷の質が良くない読み捨てのペーパーバックが存在する中で、電子書籍というパッケージが人気を得たのに対し、日本では文庫版がそのポジションを押さえているというふうにも見えます。
大原:米国にもフォーマットとしてはトレード・ペーパーバックというものがあります。日本でいうところのソフトカバーに近いものです。ハードカバーの約半分の値段(10数ドル)なので、Kindleなどの電子書籍の値段と張り合うくらいですね。Kindleが登場して、さらに廉価のマスマーケット・ペーパーバックは駆逐されつつある状況です。
電子書籍が喧伝された際には、全ての本が電子書籍で読まれるようになる、という主張をされた方もいますが、2013年の状況を見ると、その成長は鈍化してきています。50%くらいで落ち着くのではないかなと私は考えています。
――これはジェフ・ベゾスも言っていますがアマゾンにしてみれば、本が紙で読まれても、電子で読まれてもアマゾンでの購入には変わりないわけですから、そこにそれほど拘りがないようにも見えますね。Kindle Fireなどのタブレットも、電子書籍への移行をうながすというよりも、音楽や映画などアマゾンが覇権を握っていないジャンルへの挑戦というように感じています。
大原:そうですね。出版社からしても、制作や流通の体制が整ってきましたので、紙でも電子書籍でも利率がそれほど変わらないという状況にはなっています。
――電子書籍になると、著者がダイレクトに書籍を販売できます。Kindleなどの電子書店も独占販売などの条件を設けた上で、KDPのようなより料率の良い販売プランを用意していていますが、そういった仕組みを利用する動きは拡がっていますか?
大原:裾野はものすごく広がっていますね。日本のように取次会社が全国の書店に本を素早く流通させたり、納品された本に対して出版社にお金を払うといった仕組みがアメリカにはありません。どんなに急いでも半年くらい先にならないと本屋さんに本は並ばないし、お金が入ってくるのはもっと先になります。従って、日本以上に大手の出版社が存在感を持っている市場です。そういった大手のビジネスの規模感に応えられるごく一部の著者だけが本を出すことができるんです。
――日本の出版の世界が「多様性」に富む、と言われることにも通じますか?
大原:いえ、お国柄ということもあるかも知れませんが、もともとWebで自分の作品を発表するということにアメリカ人の多くが積極的です。Kindleだけでなく様々な電子書店がセルフパブリッシングの仕組みを備えるようなった今、爆発的にタイトル数が増えています。もちろん玉石混交ですが(笑)。裾野が広がっていることは間違いありません。
――これまで出版社から本を出していたような著者が、ダイレクトパブリッシングに移る、といった動きはありますか?
大原:セス・ゴーディンのようなごく一部の著者に限られますね。メディア出演や講演などを通じて自分のファンが何万人もいるような人であればですが。
――そういう人は、スタッフとしてエディターやプロモーターを雇っていたりしますよね。
大原:そうですね。セルフパブリッシングといっても、こちらでいうところの出版社の機能を組織として持っているというイメージです。
――アマゾンが自分たちで出版機能を持って、売上の動向を分析しながら本をリリースしていく「アルゴリズム出版」についても、別のところで言及されていました。
大原:例えばドイツで売れている本があれば、それを英語に翻訳し米国で直接販売するということを行っていますね。サスペンスやロマンスのような、読者が多読型のジャンルについては電子書籍を投入することでうまく行っています。ただ、編集者を雇ってゼロから本を作る、という動きは見直しを迫られているようです。バーンズアンドノーブルのような大手書店チェーンが、電子版をKindleでしか販売していない紙の本を、店頭で扱うことを拒否したからです。著者にとってはやはり「紙の本として書店で発売されていること」がブランドとしての安心感につながっていますから、これは痛手だったはずです。
――アマゾンが全ての書籍の分野においてうまく行っている、というわけではないんですね。
大原:たまたま今回は既存の出版社のやり方ではうまくいかなかっただけだし、そもそもアマゾンは従来のやり方をなぞって成功したいとは思っていないかも知れません。
アメリカから見た日本の書籍市場
――昨年Kindleの日本版が登場して電子書籍が普及の兆しを見せる日本ですが、引き続き出版不況と呼ばれるような苦しい状況も続いています。アメリカから見て日本の状況はどんなふうにご覧になりますか?
大原:電子書籍が大きな変化のきっかけであることは、アメリカも日本も共通しています。これまでの方法では本が売れないわけですから、やり方や業界の構造を変えなければいけないのは自明です。本質は、取次会社と出版社との関係を見直すことだと思います。本を作って、取次に納めれば売上が立ち、全国の書店にも並ぶという仕組みにはもう頼れないはずです。こちらの出版社は本が出来上がる前からプロモーションを入念に行い、取次に対しても積極的に営業を行います。そうしないと、書店が仕入れてくれないからです。
――先ほどの週刊連載=作品の大量生産という話にも通じるものがありそうですね。作品をたくさん出せば取り敢えず売上が立つ、という時代は終わったとすれば、もっと点数を絞り込んで、制作の時間もかけて、その分1つ1つの作品へのプロモーションに注力した方がよい?
大原:その通りだと思います。
――ただ、そういったプロモーションや営業は大手ではないとできない、小さな出版社には難しいということはありませんか?
大原:いえ、プロモーションや営業は外注できますし、特定の分野に特化することで十分存在感を出している中小の出版社もあります。規模の力でアマゾンのような強力な販売者と交渉する出版社もある一方、そういった販売者に頼らずとも読者がどこにいて、どんな本ならば必ず買ってくれるかをつかんでいる出版社は実は元気なんです。ユニークな翻訳物を得意とするメルビルハウスや、エスニック系の小品をアート作品のように売り出すグレーウルフといった出版社がその例ですね。人口は日本の倍ですが、読書人口はほぼ同規模の米国で、5千部から1万部で元が取れるビジネスを手がけています。
――ユニークだけれども一定の需要はあるので、価格を高めに設定できるという面もありそうですね。
大原:そうですね。再販制がない米国では、アマゾンで売っているようなメジャーな作品は書店でもディスカウントせざるを得ません。でも、ユニークな作品であれば定価でも売れる可能性がある。その分利益を生んでくれるはずだ、という販売者側のモチベーションにも影響していると思います。
――電子書籍についてはいかがでしょうか?日本ではキンドルはじめ、様々な電子書店が存在し、一部には「乱立していて分かり難い」という批判もありますが。
大原:実は米国の電子書籍市場でキンドルのシェアは最近下がっています。日本と違って最初はほぼキンドルしかなかったわけですから、NOOKやKoboが登場してシェアが下がるのは当然ですが、それでも5割強という規模にはなってきています。著者・出版社はできるだけ幅広い読者に作品を読んでもらいたいと考え、キンドルだけを選ぶという例というのはほとんどありません。読者の側もどのプラットフォームでも構わない、という意識が強いのではないでしょうか。
そんな中、これらはDRM(デジタル著作権管理)を外していこうという動きが拡がるのではないか、と予想しています。たとえ端末を買い換えても、過去に買った本を読めるというのは読者だけでなく、広く本を提供したい出版社にとってもメリットがある、という理解は拡がっていると感じているからです。
――なるほど。日本でもこれからそういった動きが出てくると良いなと一読者としては思いますね。最後に、他に日本の書籍ビジネスで気になる点などはありますか?
大原:わたし自身、日本の作品を海外で売りだそうとするときに、権利関係が整理されていなくて驚かされることが多いんです。本の売り方、読まれ方が多様になる中、「契約」の重要性が増しています。出版社はもっと著者に、どんな権利をどういう条件で預かって、どんなビジネスをしようとしているのか、もっと丁寧に説明をするべきだし、著者もそこに関心を払うべきです。そして、それが出版社と著者の手に余るということであれば、私たちのようなエージェントの出番でもあると思います。日本でも最近、映画化や舞台化を巡って、いろんな議論が起こっていますよね。元をたどれば契約をきちんと結んでいれば、トラブルを避け、もっとビジネスを発展させることができるはずなのに、勿体ないと思います。
日本では本は旬やブームとして消費されているように思えます。でも、米国始め海外の多くでは、本はじっくりと長く楽しまれ、様々に形を変えて親しまれるものです。そのためにも契約は大切ですし、わたし自身もエージェントとして日本からの作品をしっかりアメリカで知ってもらい、根付かせる活動を続けていきたいと考えています。
――たしかにわたし自身も、契約が無いまま本を書き始めていたり、プロモーションなどについての約束がないことは不思議に思っていたので納得ですね。貴重なお話をありがとうございました。
※一部、大原さまの発言を修正しました(12月2日)

























