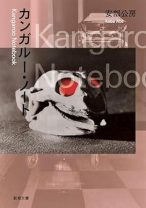官能WEB小説マガジン『フルール』出張連載 【第65回】夏乃穂足【お試し読み】『鬼の涙が花だとしたら』
公開日:2014/11/26
 夏乃穂足【お試し読み】『鬼の涙が花だとしたら』
夏乃穂足【お試し読み】『鬼の涙が花だとしたら』
鬼が吼えると災厄が起こる――古来より鬼と、それに魅入られる人間の伝説がある地、希望谷でトンネル崩落事故に巻き込まれた古林千鳥。千鳥を助けたのは鋼のような体躯と赤い髪を持つ隻眼の男・森羅だった。だが彼は、幼い頃に千鳥の父親を殺した鬼・シンの面影を色濃く残している。手厚い看病と労りの中、森羅の不器用な優しさに惹かれる気持ちと、彼の正体への疑念が膨らんでいき……人間と鬼、種族を超えて育む 一途な愛。
千鳥(ちどり)は一人、真夜中に沢のほとりを走っていた。
二階の自室の窓から、こっそり抜け出してきたのだ。父親から会うことを禁じられたけれど、たった一人の親友にどうしても会いたくて。
気持ちが逸(はや)って、月明かりも届かない暗い森の中でも、少しも怖いと感じない。それより、三日も千鳥の部屋に来てくれなかった親友のことが気がかりだった。夜にはいつも通り窓を開けて、空が白むまで眠らずに待っていたのに。
唯一無二の親友――シンに会えたら、訊いてみたいことがたくさんあった。
全速力で駆けながら、唇に触れてみる。指先に、息が熱い。心臓が壊れそうなほど高鳴って、頬は燃え出しそうに火照っている。
千鳥の部屋を最後に訪れた夜、シンはこれまで一度もしなかったことをした。帰り際にそっと、唇と唇を触れ合わせていったのだ。生まれて初めて触れたひとの唇は、マシュマロよりもずっと柔らかく、温かく湿っていた。
(ねえ。どうしてあんなことしたの?)
微かに触れるだけだった口づけの、意味を知りたい。その夜千鳥の体の中に植えつけられたまま、今も腹の奥や頬を燃やし続けている、消えない熱の意味が知りたい。
(ううん、本当は何も訊かなくたっていいんだ)
何も話さなくてもいい。顔が見られればそれでいい。だってシンの顔を見たら、きっと千鳥の胸はいっぱいになってしまって、何も訊けなくなってしまうだろうから。
シン。シンに会いたい。
元々体が弱かった母が亡くなってから、父は十一歳の千鳥とまだ三歳の佳乃子(かのこ)を連れ、父方の祖母が住む郷里、希望谷(きぼうだに)へと移った。
希望谷に来てからもうそろそろ半年が経とうとしているのに、千鳥はいつまで経ってもよそ者だ。クラスで誰かと組む時にはいつも千鳥が余るし、休み時間にも遊ぶ相手がいないから、一人ぼっちで本を読んでいる。
転校してすぐの頃、リーダー風を吹かせている一派にへつらわなかったせいかもしれないし、いまだに抜けない東京言葉がいけないのかもしれない。
けれど、千鳥は、クラスで孤立していることを父や祖母に言おうとは思わなかった。千鳥と佳乃子を育てながら忙しく働いている彼らに、余計な心配をかけたくない。
それに今は、どんなに学校で独りぼっちでも全然平気だ。放課後には内緒の親友と思いきり遊べるし、夜中に部屋の窓を開けておけば、忍んできてくれるのだから。
希望谷を流れる希望川を上流に向かって歩き、山桜の古木が一本だけ生えていて草の広間のようになっている場所で、シンとは出会った。シンは、千鳥の特別だ。あの真っ赤な髪も、蜜色の肌も、古めかしい着物姿も、彼を慕う妨げになりはしない。
彼はカワガラスの餌場やアケビが取れる場所を知り尽くしていたし、木の枝と蔓だけで鮎を釣り上げることもできた。小さな焚火を熾(おこ)して魚を焼いて食べることや、古い熊穴を使って秘密基地を作ることを教えてくれたのも、シンだ。
二人でした冒険の数々に、どれほど夢中になったことだろう。どんなに楽しかったことだろう。
学校では、息を詰めて存在感を薄めるようにしていたし、嫌なことがあっても、家では何も問題ないというふりをしていた。どこにいても所在なくて、冷えて 凝(こご)った胸の内が、たった一人の友達といる時だけ溶けたチョコレートみたいに溢れ出す。シンの美しい顔を見ているだけで、言葉を交わさなくても満た された気持ちになる。
感情の赴くままにどんなにはしゃいでも、心の柔らかな部分をさらけ出しても、シンなら絶対に千鳥を嘲ったりしない。それは絶対の信頼だった。
川縁(かわべり)の道を、いつも二人で待ち合わせをする桜まであと少しのところまで来た時、鳥達が羽音をたてて一斉に飛び立った。上空を旋回する鳥の群れがやけに黒々と見えることに、理由のわからない不安をかきたてられる。
次に聞こえて来たのは、今まで一度も聞いたことのない異様な音だった。
うおおおおお……ん。
沢が、いや山全体が咆哮している。
ここのところ、山でトンネル工事をしているから、時々窓が震えるほどの爆音が聞こえてくることはある。だが、この音はそれとは全然違う。まるで、巨大な生き物が吼えているかのような……。
(何か、嫌な感じ)
本能的な恐怖を感じ、いったん家に帰ろうかと逡巡した、その時。
唐突にがくっと体が沈む感じがして、確かだと思っていた靴の下の地面が消えた。足元の土手が崩れたのだと知る間もなく、千鳥の体は下へ――泡立つ急流へと叩き込まれた。
速い流れに頭を押される。沈むたびに水を飲む。
怖い。苦しい。
流されていく千鳥の目に、こちらに向かって飛び込もうとしている父親の必死の形相が映った。きっと千鳥を追って、助けに来てくれたのだ。
(父さん、助けて)
叫ぼうとして開けた口にどっと水が流れ込み、塊となった重い水に絡めとられ、視界が水の暗い灰緑色に閉ざされた。
2013年9月女性による、女性のための
エロティックな恋愛小説レーベルフルール{fleur}創刊
一徹さんを創刊イメージキャラクターとして、ルージュとブルーの2ラインで展開。大人の女性を満足させる、エロティックで読後感の良いエンターテインメント恋愛小説を提供します。