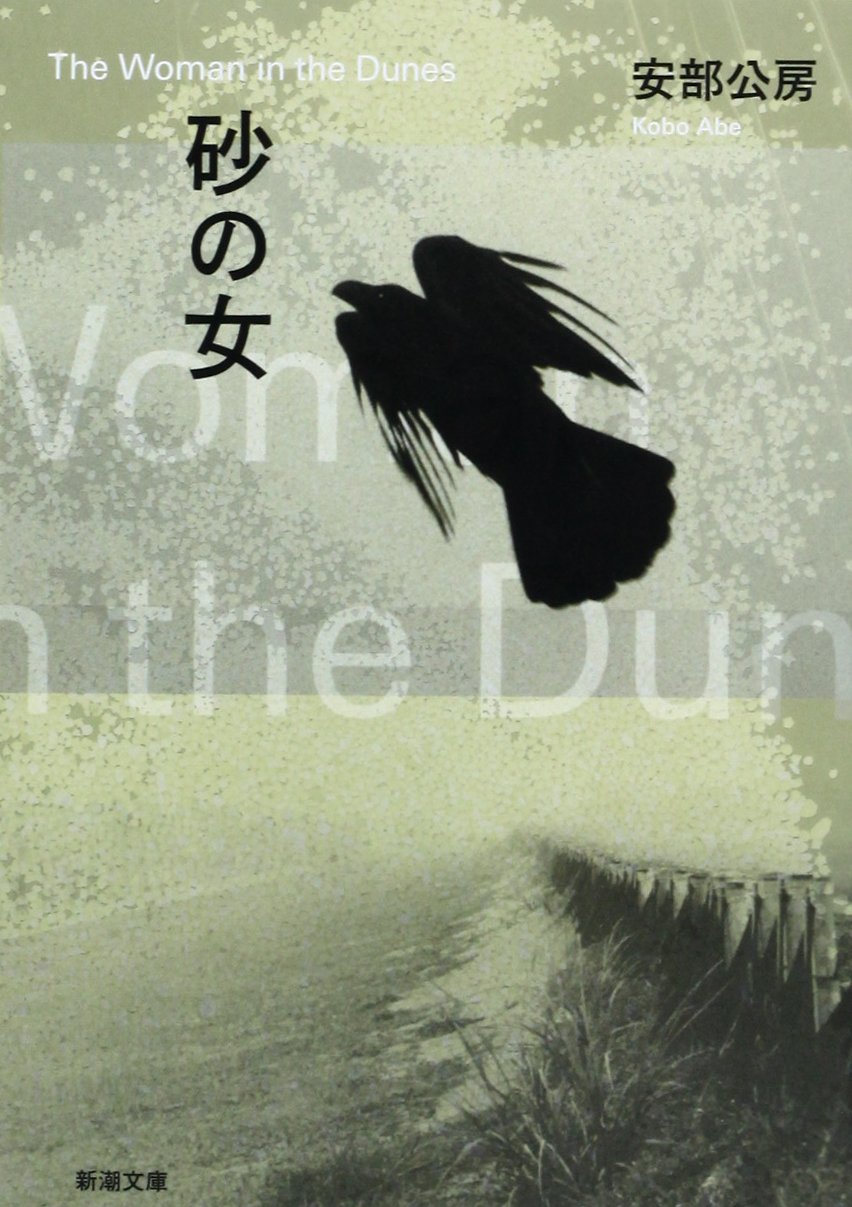変態は一日して成らず! ー安部公房『砂の女』| 連載第7回
更新日:2015/8/1
「愛おしき変態本」第7回は、安部公房の『砂の女』をお送りする。1962年に発表され、読売文学賞やフランスの最優秀外国文学賞を受賞、20数ケ国語に翻訳されるなど海外でも高い評価を受け、安部が世界的な作家となった作品だ。
あべ・こうぼう 1924年(大正13年)東京府北豊島郡滝野川町西ケ原(現在の東京都北区西ヶ原)出身。本名は公房(きみふさ)。1925年旧満州の奉天(現在の瀋陽)に家族とともに渡り、少年期を過ごす。1948年東京大学医学部卒業。1951年『壁』で芥川賞を受賞。主な作品に『他人の顔』『人間そっくり』『燃えつきた地図』『箱男』『笑う月』『方舟さくら丸』『カンガルー・ノート』など。1973年より演劇集団「安部公房スタジオ」を結成して演劇活動も行い、『棒になった男』などの戯曲も多数手がける。1993年(平成5年)1月22日、急性心不全のため死去。
『砂の女』の主人公は、新種のハンミョウを見つけに休暇を取って辺鄙な海岸までやって来た、昆虫採集が趣味の男だ。虫を探すために下を向いて歩いていると、半月状にそそり立って城壁のように部落を取り巻いている砂丘の稜線に空いた穴の中に家があることに気づき、それを撮影しようとすると、村の漁師らしい老人が「調査ですかい?」と話しかけてきた。昆虫採集だと告げると「県庁の人じゃないんですね?」と妙なことを聞かれ、ふと向こうを見ると、同じような服装の男3人がこっちを見ている。男が名刺を渡すと「ははあ、学校の先生かね……」と言った老人は、この後はどうする、もう上りのバスはないから、貧乏村でよければ泊まるところは自分が世話をする、と言う。
老人について行くことにした男が向かったのは、貧乏村の一番外側、さっき男が見ていた砂丘の稜線に接した穴の中のひとつだった。中には家があり、その屋根の高さの三倍はあろうかという砂の崖に囲まれている。男が縄梯子を使って降りて行くと、家には30歳前後の人の好さそうな小柄の女がいた。しかし家の壁や襖、柱はズタボロ、窓には板が打ち付けてあり、畳は腐る寸前(歩くと濡れたスポンジを踏むような音がする)、焼けた砂の蒸れるような悪臭が一面に漂うというなんとも壮絶なところだ。普通なら泊まるのを躊躇しそうなものだが、男は「全ては気の持ちよう」と割り切る。しかしランプはひとつしかなく、風呂もない、というか水もロクにない。そして食事になるのだが…
女が食事をはこんできた。魚の煮つけに、貝の吸物だった。いかにも浜の食事らしく、それはいいのだが、食べはじめた彼の上に、女が番傘をひらいて、さしかけて来たのである。
「なんなの、それは……?」なにか、この地方の、特別な風習なのだろうか?
「ええ……こうしないと、砂が入るんですよ、ご飯の中に……」
「どうして?」おどろいて天井を見上げたが、べつに穴があいているわけでもない。
「砂がねえ……」と、女もいっしょに、天井に目をやりながら、「降ってくるんですよ、どこからでも……一日掃除しないと、一寸(※約3センチ)もつもってしまいます。」
毎日砂掻きをしないと、砂によって木が腐ってしまうという女の言葉を訝しむ男…。やがて夜になり、女は砂掻きを始める。
「じゃあ、一つ、ぼくも手伝うとするか。」
「いいんですよ……いくらなんでも、最初の日からじゃ、わるいから……」
「最初の日から?……まだそんなことを……ぼくがいるのは、今夜だけだよ。」
「そうですかねえ……」
「そんな暇な御身分じゃないからね……さ、そのスコップを貸した、貸した!」
「お客さんのスコップなら、そっちにありますけど……」
実はこの砂丘は貧乏村を砂から守る防砂堤で、もしここに人が住まなくなって砂掻きをやめてしまうと、10日もたたないうちに村は砂で埋まってしまうという。防砂林を作った方がいいと男は言うが、砂掻きの方が安上がりだという女に、「くだらん!」と男はスコップを投げ出してやめてしまう。ところが翌日起きてみると、昨日降りてきた縄梯子が消えていた。砂の中にあるかと探してみるも、ない。砂の壁は簡単には登れそうもなく、家の屋根に登っても上まで10メートルくらいある。男は試しに崖を登ってみるが、途中までしか行けずに転がり落ちてしまった。女は言う。「もう、お分かりなんでしょう?」と…。そう、男は砂掻きの「労働力」として捕らえられ、この砂の中に閉じ込められたのだ。
数日後、男は女を縛り上げてストライキを決行する。そして女に、今までにこんな目に遭ったのは自分が初めてかと聞くと、これまでにも砂掻きのために捕まった人はいるが逃げられた人はいないという。男は言う。「いいともさ、それじゃ僕が最初に逃げ出してやる!」 ところがこのストライキ、飲み水の配給を断たれて、あえなく断念となる。
失敗を繰り返さないため、男はこっそりシャツでロープを作り、そこに帯を結び、裁ち鋏を先に括りつけて周到な準備をする。そして監視の隙を突いて砂の壁の上へ投げると、砂止めの俵に鋏が刺さった! 男はロープを手繰って砂の崖を登り、46日ぶりに外へ出た。必死に逃げる男だったが、なんと途中で流砂に飲み込まれてしまう。村人に助けられ、引き戻された男はすっかり意気消沈、こんな言葉を吐く。
「納得がいかなかったんだ……まあいずれ、人生なんて、納得ずくで行くものじゃないだろうが……しかし、あの生活や、この生活があって、向うの方が、ちょっぴりましに見えたりする……このまま暮していって、それで何(ど)うなるんだと思うのが、一番たまらないんだな……どの生活だろうと、そんなこと、分りっこないに決まっているんだけどね……まあ、すこしでも、気をまぎらわせてくれるものの多い方が、なんとなく、いいような気がしてしまうんだ……」
その後、男は「希望」と名づけたカラス捕獲機を作るのだが、その捕獲機が偶然砂の中の水分を吸い上げる溜水装置になることに気づく。やがて女が妊娠(もちろん男との子だ)するが、ある日下半身を血に染めて激痛を訴え、治療のため穴の外へと運ばれて行く。皆が行ってしまった後、縄梯子がそのまま残されていた。待ちに待ったこの瞬間…男は縄梯子を登って上まで行くが、下を見ると女を運び出す際に溜水装置が壊れたらしく、それを直しに下へ戻ってしまう。
べつに、あわてて逃げだしたりする必要はないのだ。いま、彼の手のなかの往復切符には、行先も、戻る場所も、本人の自由に書きこめる余白になって空いている。それに、考えてみれば、彼の心は、溜水装置のことを誰かに話したいという欲望で、はちきれそうになっていた。話すとなれば、ここの部落のもの以上の聞き手は、まずありえまい。今日でなければ、たぶん明日、男は誰かに打ち明けてしまっていることだろう。
逃げるてだては、またその翌日にでも考えればいいことである。
このラストで「なんで逃げないの?」と思うか、「ああ、そうだよねぇ」と納得するかで、あなたに変態の素養があるかどうかがわかるだろう。
もしも自分の中の変態性に気づいたとき、最初は「そんなはずはない」と否定をする。しかし一度見つけてしまった変態性は、消えるどころかますます肥大し、やがてそれは自分の一部であると思わないと自分が自分でなくなってしまうかもしれない恐怖となる。その恐怖を克服するには、変態の自分が必要とされる状況や場所を見つけ、承認欲求を満たしてやる必要がある。その欲求は日々濃くなって行き、ある日ふと見ると、とんでもない場所まで辿り着いている自分に気づく。その道は決して後戻りはできない…変態は一日して成らず、だ。
ちなみに本書の冒頭には「――罰がなければ、逃げるたのしみもない――」という一文がある。何事も果てまできてしまうと、罪や罰さえ甘美な毒となりうるのかもしれない。そこまで到達してしまうのは、果たして幸せなのか? それは辿り着いた人にしかわからないことだろう。多くの人は、そんなことに気づかず生涯を終えるものだ。
安部は幼い頃に旧満州で育ったこともあり、砂漠について独自の視点を持っていたことを『砂漠の思想』というエッセイに書いている。
砂漠には、あるいは砂漠的なものには、いつもなにかしら言い知れぬ魅力があるものである。日本にはないものに対するあこがれだとも、言えなくはないが、しかし私などは半砂漠的な満州(現在の中国東北部)で幼少年時のほとんどをすごしたのだ。いまならノスタルジアだと説明してしまうこともできるわけだが、記憶の中でも、その半砂漠的風土のなかにいてさえ、なお砂漠にあこがれを持っていたことを思いだす。空が暗褐色にそまり、息がつまりそうな砂ぼこりの日、乾ききったまぶたの裏に、拭いてもふいてもぬぐいきれない砂がくいこむ、あのいらだたしい気分の裏には、不快感だけではなく、同時にいつも一種の浮きうきした期待がこめられていたように思うのだ。
(中略)
砂漠というとすぐ、死や破壊や虚無だけを思いうかべるのは幸福な詩人だけの話で、一般的には、むしろ砂のもっているあのプラスチックな性質にひきつけられるのが普通なのではあるまいか。ちょうど子供たちが、砂場遊びに時を忘れ、世界を創造したような気持になるように……
死後、執筆中だった長編小説『飛ぶ男』や、エッセイ『もぐら日記』がワープロのフロッピーディスクから発見される(日本の作家で初めてワープロを使ったそうだ)など新時代の作家として活躍した安部。もしその死があと数年先であったならば、ノーベル文学賞を受賞していたであろうと言われている。
私小説をまったく書かず、独創的な世界を自由に構築していたように見える安部だが、長年愛人関係にあったという女優の山口果林による『安部公房とわたし』には、創作に行き詰まり「ただひたすら深夜の高速道路を走り続け、ブラックホールに飲み込まれてしまいたい気持ちになる」と語ったこともあったそうだ。また「人間はサルじゃない」とよく口にしていたそうで、この言葉を口にすると、思いもかけない方向から解決策が飛び込んできたという。とにかく「考える人」だったようだ。不思議で不条理、なのになぜか強く惹きつける魅力を持つ「公房ワールド」を体験してもらいたい。
愛おしき変態本の世界、次回「最終回」は、変態といえばこの人の右に出る作家はいないであろう「変態のラスボス」谷崎潤一郎の作品を紹介します。
文=成田全(ナリタタモツ)
【著者プロフィール】
成田全(ナリタタモツ)
1971年生まれ。イベント制作、雑誌編集者、漫画編集者などを経てフリーとなり、インタビューや書評を中心に執筆。文学・自然科学・音楽・美術・地理・歴史・食・映画・テレビ・芸能など幅広い分野を横断した知識や小ネタを脳内に蓄積し続けながら、それらを小出しにして日々の糧を得ている。現在は出身地である埼玉県について鋭意研究中。