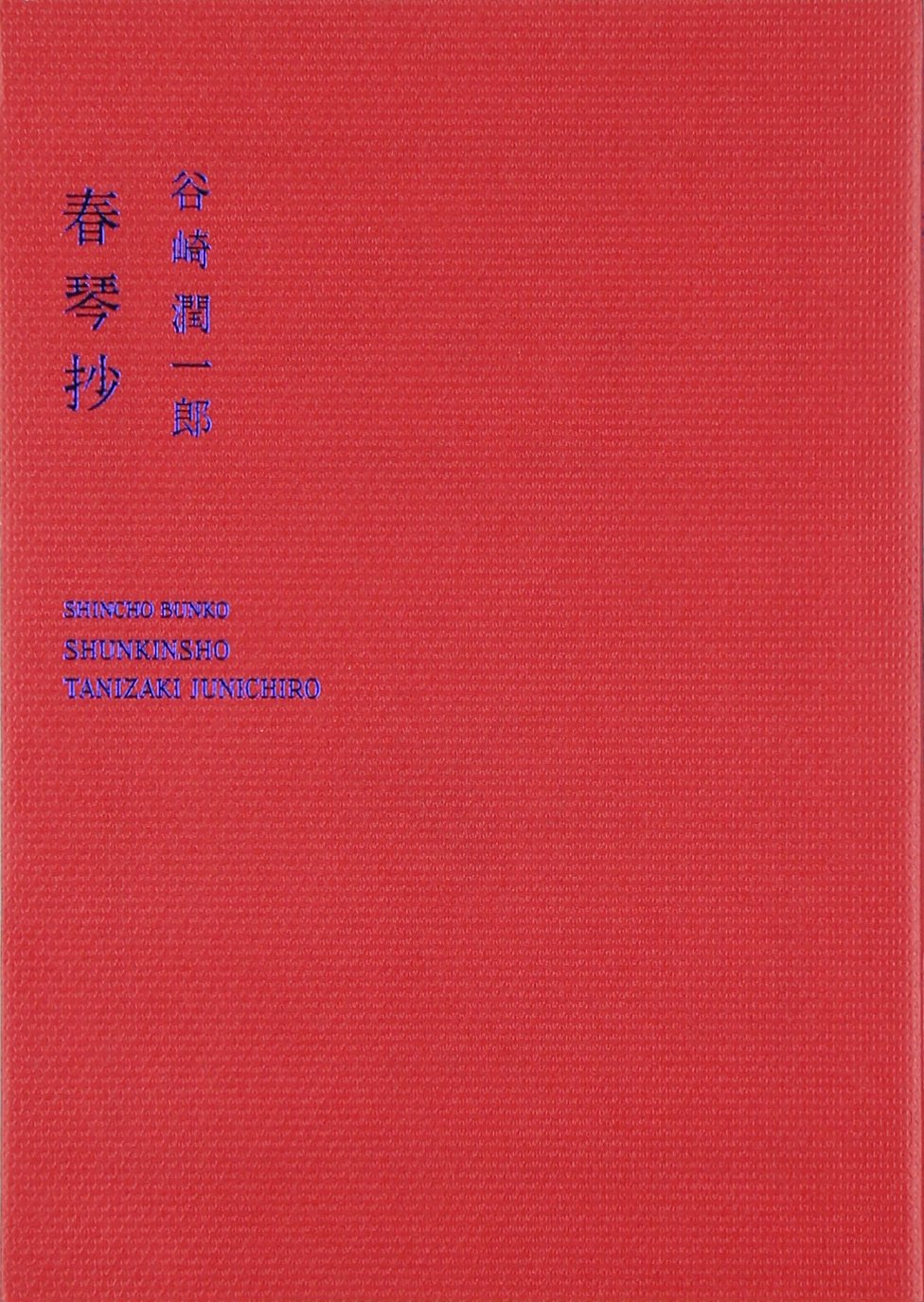愛ゆえに自ら針で目を突き、盲目となったことが人生最大の喜び! 谷崎潤一郎『春琴抄』| 連載最終回
公開日:2015/8/8
愛おしき変態本の世界
「愛おしき変態本」最終回は、“変態のラスボス”と言っても過言ではない、2015年7月に没後50年を迎えた谷崎潤一郎をお送りする。
たにざき・じゅんいちろう 1886年(明治19年)東京市日本橋区蛎殻町(現在の東京都中央区日本橋人形町)出身。東京帝国大学中退後に発表した『刺青』が永井荷風に激賞され、作家としての地位を確立。1923年、関東大震災に遭遇したことで関西へ移住。晩年に熱海や湯河原へ移るまで関西で過ごした。1965年(昭和40年)7月30日、湯河原の自宅で腎不全から心不全を併発し死去。
「変態本」の宝庫である谷崎の作品から何を選ぼうか、大いに迷った。美少女を薬で眠らせて背中にコッソリ大きな蜘蛛の入れ墨を彫ったことが悪女誕生のきっかけとなる『刺青』、遊びがエスカレートし、まだ10歳の少年がドMへの扉に手をかける『少年』、堅物のサラリーマンが「リアル美少女育成ゲーム」で大失敗(ある意味では大成功?)してしまう『痴人の愛』、普通の刺激に飽きた男が女装にハマる『秘密』、複雑に入り組む男女関係の上に猫様が君臨する『猫と庄造と二人のおんな』、上方言葉の女性が独白するレズビアン小説『卍』、性欲の強い年下妻とそれに翻弄される高血圧ジジイの夫婦がお互いの日記を盗み読みして綱引きする『鍵』、息子の妻に性的な興奮をする77歳のジジイが家族の目を盗んで義娘の足を舐めまわし、最後には自分の墓石を義娘の足型にして死んでも踏み続けてもらいたいと願う足フェチ文学の金字塔『瘋癲老人日記』、夫婦仲は冷え切っているが離婚に踏み切れず、妻には夫公認の愛人がいるという、最初の妻を作家・詩人の佐藤春夫に譲った谷崎自身の経験が下敷きと言われる『蓼食う虫』、大阪の旧家に生まれた四姉妹を美しく描く大長編なのに、「下痢はとうとうその日も止まらず、汽車に乗ってからもまだ続いていた」という衝撃の一文で物語が終わる『細雪』などなど、リストとあらすじだけでこんなに長くなってしまうほど(しかもこれ以外にもまだある)、とにかくありとあらゆるド変態のオンパレードだ!
しかしやはりここは谷崎の代表作であり、文庫本で100ページに満たないという取っつきやすさ、そして文学史には必須の作品であるということから『春琴抄』を選んだ。独特な古文風の文体、改行がなく、句読点も最小限しかないため文章がみっちりと詰まっており、最初は読みにくいと感じるかもしれない。しかし文章のリズムに慣れてくると、異常な世界に引き込まれ、時に悶絶しそうになりがら、あっという間に読み切れるはずだ。
舞台は江戸末期の大阪・道修町。主人公は薬屋を営む裕福な家の次女として生まれた鵙屋琴(もずや・こと)だ。「端麗にして高雅」といわれるほどの美人で頭もよく、琴や三味線、踊りも上手な子として大事に大事に育てられるが、9歳で眼病にかかって失明。それからは三味線の稽古に励むのだが、家族や使用人たちも手を焼くほどのワガママお嬢様となってしまう。
そのお世話役となったのが、江州日野町(現在の滋賀県)にある薬屋の息子で、鵙屋へ見習いに来ていた温井佐助(ぬくい・さすけ)だった。佐助は琴の4歳年上で当時13歳(奉公に来たのは琴の失明後)。それまで色々な人が琴の世話を担当していたが、「佐助どんにしてほしい」という琴の鶴の一声によって世話係となった。その理由を問われた琴は「誰よりもおとなしゅうていらんこと云えへんよって」と説明している。二人の身分が違うのは当たり前だが、この時点ですでに完全なる上下関係が出来上がっているのだ。
「暑い」と言う琴に「暑うござりますなあ」などと相槌を打つのはNG。それは「ウチワで扇ぎなさい!」のサインだからだ。そんな厳しい琴であったが、佐助はそれを苦労と思うどころか、むしろ喜んでやっている。やがて佐助は琴に憧れてコッソリ三味線を購入、明け方に起き、押入れにこもって稽古するようになる。真っ暗闇な場所だが、佐助は琴と同じ暗黒世界で三味線を弾くことがこの上なく楽しいと感じている。程なくして三味線の稽古が発覚、「丁稚の分際で生意気な真似をすると憫殺(びんさつ ※哀れんで無視すること)されるか嘲笑されるか、どっちみち碌(ろく)なことはあるまいとおそれを抱いていた」佐助だったが、予想外に「聴いてやろう」と言われてしまう。しかしいざ弾かせてみると、自己流にしてはいいじゃないかと感心され、琴の個人レッスンを受けることになる。それ以来「こいさん(お嬢さんの意味)→お師匠様」「佐助どん→佐助」という呼び方に変わり、完全な師弟関係に。さらに琴の教え方は超スパルタ。「阿呆、何で覚えられへんねん」と罵られ、ぶたれるたびに佐助は意気地なくヒイヒイと声を上げて泣くため、女中さんがそんなことしたらいけないと言いに行くと…
春琴は却って粛然と襟を正してあんた等(ら)知ったこッちゃない放ッといてと威丈高(いたけだか)になって云ったわてほんまに教(お)せてやってるねんで、遊びごッちゃないねん佐助のためを思やこそ一生懸命になってるねんどれくらい怒ったかていじめたかて稽古は稽古やないかいな、あんた等知らんのか。
私が怒られたじゃない!と怒る琴。以後、佐助が泣くことはなくなった。すると「これ以上ひねくれたら困る」と心配した琴の両親のはからいによって、佐助は18歳で琴と同じ師匠の教えを受けるようになる。
その2年後、16歳になった琴が妊娠していることが発覚。誰の子か絶対に言わない琴、その琴に叱られるから言えないという佐助。やがて生まれてきた男の子は佐助そっくり…。こうなったら佐助と結婚しなさい、そうじゃないとこの子は養子に出さないといけない、それでいいのかと詰め寄る両親に「何卒(どうぞ)何処(どこ)へなとお遣りなされて下さりませ一生独り身で暮らす私に足手まといでござります」と涼しい顔で言う琴…。ということでその子は養子となるが、どこに出されたのかはわからないままだ(その後、琴と佐助の間には二男一女の子が生まれるが、男の子は養子に、女の子は生まれてすぐ死んでしまったため、琴は一度も子育てをしていない)。
やがて実家を出て三味線の師匠「春琴」として生計を立てるようになった琴だが、贅沢し放題(足りない分は実家から援助)で、佐助は相変わらずの下僕扱い。ある時虫歯が痛いのを我慢して佐助が春琴をマッサージしていたところ、冷たい春琴の足で腫れたところを冷やそうとすると「横着者!」と顔を蹴ったり、せっかく三味線教室に来た生徒の頭を三味線のバチで殴るなどやりたい放題。またある金持ちのボンボンの生徒が美人の春琴のことを気に入り、自分のものにしようとしたことがあったが、琴は超スパルタ三味線レッスンでしごきまくり、弾けないボンボンにイラッとして最後にはバチで眉間を殴打! 出血したボンボンは「覚えてなはれ」と捨て台詞を吐いてやめてしまうということもあった。
そんなことばかりしていたからか、春琴が37歳の時、寝ていたところを暴漢に襲われ、熱湯をかけられて顔に火傷を負ってしまう。隣の部屋で寝ていた佐助はすぐに駆けつけるが、その顔を見て「あ!」と叫んで目を覆ってしまう。春琴は「わては浅ましい姿にされたぞわての顔を見んとおいて」と言う…。春琴の顔の傷を見たのは治療をした医者だけ。やがて傷が癒えて包帯を外す前、佐助は火傷の痕を見ないため、常人では考えつかないようなとんでもないことをやってのける。
佐助は女中部屋から下女の使う鏡台と縫針とを密かに持って来て寝床の上に端座し鏡を見ながら我が眼の中へ針を突き刺した(中略)黒眼を狙って突き入れるのはむずかしいようだけれども白眼の所は堅くて針が這入らないが黒眼は柔かい二三度突くと巧い工合にずぶと二分程這入ったと思ったら忽ち眼球が一面に白濁し視力が失せていくのが分った
目が見えなくなりました、もう一生お顔を見ることはありません、と言う佐助に春琴は…
よくも決心してくれました嬉しゅう思うぞえ、私は誰の恨みを受けて此のような目に遭うたのか知れぬがほんとうの心を打ち明けるなら今の姿を外の人には見られてもお前にだけは見られとうないそれをようこそ察してくれました。
その言葉を聞いた時が、佐助にとって後にも先にも人生で最高の瞬間だった…そして、犯人はお師匠さまと私を困らせようと思ってやったのに、私の目が見えなくなったから水の泡ですね、と言って2人は抱き合いながら泣く。それからの人生はこの世が極楽浄土になったように感じながら、春琴はずっと頭巾を被って生活し、58歳で死去。佐助は誰とも結婚せず、83歳という長寿を全うした。
人と人が簡単に出会える現代とは違い、昔は限られた場所でしか知り合うことができなかった。しかし運命的に出会ってしまった琴と佐助は、お互い10代という多感な時期に自分と相手の中にある「変態の素質」を見つけ、徹底した反復学習によって絶対に離れることのない陰と陽のような強い絆で結ばれる。外から見るとその関係性は理解できない倒錯的なものだが、外界から閉じられた2人の世界では美しい純愛であり、互いに敬意を払う師弟愛があり、ワガママを許し合うSとMの補完関係にあり、ありのままの自分をまるごと受け入れてくれる魂の双子であるのだ。
また『春琴抄』は琴が産んだ子の父親は誰だったのか、熱湯をかけた犯人が誰だったのかなどハッキリしないことが多い。なので「何にでも理由があり、謎は解明されるもの」という考え方に慣れ切ってしまった現代人には、少々理解し難い物語かもしれない。しかし谷崎は1934年に書いた『文章読本』で「一体、現代の文章の書き方は、あまり読者に親切過ぎるようであります。実はもう少し不親切に書いて、あとを読者の理解力に一任した方が効果があるのであります」と記しており、とにかく「含蓄」が大事であると力説している。これは谷崎の美意識であり、谷崎の随筆『陰翳礼讃』にも通じる日本的な情緒だ。
実家が貧乏になったため、学費を援助してもらう代わりに書生として入っていた家の女中さんにラブレターを出したことが大問題となって大学を中退することになった初恋、最初の妻は知人に譲り、2番目の妻はないがしろにして、芥川龍之介のおかげで出会えた3番目の妻と添い遂げたが、その他にも愛する人がいたという、とにかく恋多き人物だった谷崎。明治から大正にかけて活躍したアナーキストの大杉栄は『生の拡充』という著作で「美はただ乱調にある。階調は偽りである。真はただ乱調にある」「今や生の拡充はただ反逆によってのみ達せられる。新生活の創造、新社会の創造はただ反逆によるのみである」と書いているが、奔放な結婚生活や、『源氏物語』を訳せば「不敬だ」と発禁処分になり、太平洋戦争が勃発した翌年から書き始めた『細雪』は「時局にそわぬ」と軍部から出版を潰されるなどしてきた谷崎は、ある意味で「反逆の人」であり、「生」と「性」を拡充しまくった作家と言えるだろう。
そんな谷崎に、そしてこれまで「愛おしき変態本の世界」で紹介した作品を生み出した文豪に「あなたたちはなんと素晴らしい変態だろう!」と惜しみない賛辞を送り、連載を終わりたい。
文=成田全(ナリタタモツ)
【著者プロフィール】
成田全(ナリタタモツ)
1971年生まれ。イベント制作、雑誌編集者、漫画編集者などを経てフリーとなり、インタビューや書評を中心に執筆。文学・自然科学・音楽・美術・地理・歴史・食・映画・テレビ・芸能など幅広い分野を横断した知識や小ネタを脳内に蓄積し続けながら、それらを小出しにして日々の糧を得ている。現在は出身地である埼玉県について鋭意研究中。