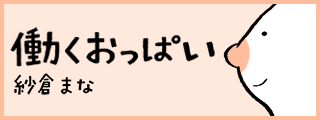『働くおっぱい』第7回「夜の営みと生理」/紗倉まな
公開日:2018/10/25
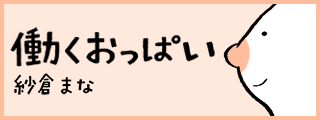
皆様は日常で叫ぶことはあるだろうか。私はトイレでよく叫ぶ。
先日はiPhoneを家のトイレに水没させてしまい、盛大な叫び声を発して瞬間的に狂った。思いも虚しく、黒い画面の世界へと逝ってしまった手元のアイフォンに嗚咽し、水に流せない事件(トイレだけに)となった。これが最近の“ベスト叫び”である。
もちろん、iPhone水没の一件はなかなかイレギュラーな叫びであります。頻繁に起こってはさすがに困るし、なるべく避けたい。「よく叫ぶ」。それは、トイレットペーパーが切れたとか、何か大切なことをふと思い出したとかそういう類の叫びもあるけれど、「毎月子宮から訪問する来客」にたじろぐことによって発せられることも、女性として25年生きていると当然ながらあるのだ。
生理とは、まさに、日常に潜む最大級のメランコリーである。
*
去年に放送されていた大河ドラマ「おんな城主 直虎」の中で、「おなごは血など見飽きておるからな!」という、直虎が政次に発したとても印象的な台詞があった。もちろんこれは、月経ではないことを指していたようにも感じられたけど、私はその言葉を、女性という生き物を捉えた直接的な意味で感じ入り、心と子宮が連動して小さく震えたのだった。
毎月の流血がパンツやナプキンや衣類やシーツを赤く染めるたびに、嫌悪感よりも前に「あー。だから最近、やけに私ではない感があったのね」と深く納得し、頭の中でふと直虎の言葉が蘇り、“子宮内での静かな戦い”の手当てに勤しむ。テンションが下がることには違いがないのだが、それでも、今回もきちんと訪れてくれたことに安心し、感謝もする。一週間という長くも短くもない期間をいつだって丁寧にもてなし、ため息をつきながら一緒に過ごすのだ。
出血というのは、動揺や恐怖や痛みを確実に伴うものであるから、そもそも生理の話をすること自体に強い苦手意識を持っている殿方も多くいるのではないでしょうか。しかしながら、女性の身体へと成熟した私たちにとっては、見慣れたくなくとも見なくてはいけない現実として存分に叩きこまれているため、血の受け止め方を、血の概念をも、鮮やかに変えてしまっているところもあるのだろうと思う。
相棒となった子宮に「あれ、先月より早くきたけどどうした?」なんて語り掛けることを続けてみれば、もはや生理という現象を「厄介だけど大切な人」と擬人化して扱っているのかもしれない(そんなことをしているのはお前だけだよ、という声もちらほらと聞こえてきそうですが…失礼)。年に数回しか会わない友人よりも、親密度は極めて高いということは断言できる。
その愛着のせいか、夜の営みをしようと布団の上で足を広げ、相手に身を委ねかけたときに、うっかり「開けてびっくり玉手箱状態」に遭遇してしまった相手の反応というのを事細かく見てしまうのだけど、これって女性アルアルなのでしょうか。
うわっ、もしかして生理? 面倒くさそうな声を出して眉間の皺を深めている表情を見れば、一気に心も視線も冷めてしまうのだよな。「空気読めなくてすんません」と言わんばかりの、微量な出血。そりゃあ、ぎょっとしてしまうのは致し方ないけれど、私たちがぎょっとするのとは異なる種類のものであるように感じてしまうわけで。鉄のような不愉快な匂いを嫌悪に思われているようで、出血しているという事実すらも怪訝に扱われているようで、抗えない性別による身体の違いにちょっとだけ腹が立ち、ちょっとだけ悲しくなってしまうのだ。
それにしても、生理現象に出血を伴うというのは、なんだか不思議ではないですか。そもそも論になってしまいますが…。もっとどうにか、怪訝に思われぬような方法はなかったのでしょうか。かわいらしいパンジーがぽんっと出てくるとか、シャネルの香水のような匂いのする体液が溢れ出るとか、何かもっと煌めかせて対処できなかったのかな。“毎月の出血”という神秘的な現象に対して、不毛な議論を持ち込みたくなってしまうのは、私にとっての常である。
*
遡ること平安時代、女性の血は穢れとして、生理中の女性は「月経小屋」に隔離されていたという話を聞いたことがある。今でこそ隔離される慣習はないけれど、「穢れ」から、「よくわからないもの」「扱いにくいもの」という腫れ物に触るようなイメージへと変わり、その傾向は現代にも深く根付いているように感じる。よくわからない生き物を、薄いガラス一枚で隔てた状態で観察しているような、異性との間で生まれる一定の距離感は普遍的であるように思うのだ。
例えば、イライラしている女性を見て「おっ、生理中?」と嘲笑う起因も、これであると睨んでいる。すべての怒りが、すべて生理によって引き起こさるわけでは当然ないのだけれど、安易で短絡的なこの発言は、怒りの根源を考えずに済むわけだし、非常に都合の良い解釈として使える。だが、このような発言を聞くたびに、「腫れ物に触れるようで面倒くさい」がもはや生理のデフォルトになってしまっているような危機というのを、恐ろしいほどに感じてしまうのだ。
確かに私は、かつて好きだった人達に、理不尽な苛立ちを存分に振りまいて生きてきた。怒りの導火線はわずか数ミリなのに、着火した後の起爆力は半端ない。ふと冷静に振り返ってみると、自分の言動はあまりにも幼稚で放漫に満ちていて笑えてくる。
「燃えるごみの袋に入ってたよ」
一人暮らしをしていた学生の頃、部屋にやって来た恋人がそう言って、ごみ箱の中から空いた化粧瓶を拾い上げた。布団の中で海老のように丸まりながら腹痛に堪え、彼が帰るまで必死に眠気と戦いながら、ぼんやりと考えた。あぁ、私、余裕がなくてちゃんとごみ箱を見ずに捨ててしまったのだな。今度から気を付けるね。そう答えよう。本心はそんなところだった。が、しかし、私は変なことを口走ってしまったのだ。
「…は? がんばれば燃えるじゃん。そのままにしておいてよ」
人間失格。なぜ、なぜ、そんなことを言ってしまうんだろう私……頑張るとか、そういう問題じゃねえよ……瓶に意思はねえよ……。
別々の人間が頭と口に宿っていて、二つは直結しているようで連動していないような、奇妙な展開になっていく。自分でも意味の分からぬことを言ってしまっていると理解している中で、それでも、「そうだね、燃えるよな…」と彼に返してほしいと願ってしまった。そして、さりげなく分別して、ごみを出しておいてほしかったのだ。
彼は少し考えたあと、さらっと言った。
「いや、燃えないよ。ちゃんと仕分けしようね」
突如、私の「理不尽」スイッチが入る。いや、そういう返答がほしいんじゃないよ。燃えないことは普段分別しているしわかっているんだよ。こんなことを言ってしまうほどに辛い今の現状を汲んで労わってほしいだけなんだよ。私だって言ってしまったあとなんだか恥ずかしいよ。穴があったら入ってるよ。
頭の上から爪先まで、いらぬ神経が増えてしまったように、とってもとげとげ。触れたら痛いぜ、怪我するぜ。ささくれだった心や皮膚を、唾をつけて滑らかにするような、適切で柔らかい対応を男性にしてもらったとしても、生理中のメランコリーは妙な生き物でしかなく、瞬間湯沸かし器並みに温度を上げていく暴れ馬のような怒りを前にして、うまくハンドルを切れないこともある。
クッションを投げ、黙れと叫び、出て行けと暴言を吐き、もう嫌だわーと泣きながら寝る。きっと、恋人が家事をやらなければ、部屋が汚くて精神不衛生になり怒りが満ち溢れる。だが恋人がせっせと家事をやってくれても、自分がダメな人間に思えてきて自己嫌悪に陥り、きっとまた、自分にとっても予想外なことを叫ぶだろう。つまり、他人が息を吸って吐いているだけでも、怒りは増幅して落ち着かないような様な気さえする。なんていうことだろう。アーメン。
*
“今月もやって来たぜ、出血大サービス!”は強烈なパワーをもった定例行事であるに違いなく、結果、余計なおまけがついてくる。その“おまけ”というのが、“自分が自分ではない感じがする違和感”であり、ここにたいへん苦悩する。前向きな“おまけ”であれば最高にありがたいのだが、不安や悲しさや怒りへと簡単に変換されていくので、“不安定なおまけ”であるという事実にはしみじみと頷くしかない。
解決方法はただ一つ。時間である。そう。そもそもこれは、己との、そして子宮との、真っ向勝負になっているのだ。血の流れが途絶えるという終止符が打たれるまでの期間、ぐっと我慢する。「心の傷は時が癒してくれる」という典型的な失恋後のメンタル脱出方法とどこか似ている。
自分でも扱いにくく、時が宥めてくれる現象なのだから、他者にとっては余計に扱いにくいものであることは頷ける。とはいえ、生理についての知識がはたしてどれほどあるのかと問うてみれば、きっと、曖昧なことくらいしか理解されていないのではないだろうか。
実際問題、生理になった女性の対処法はフィーチャーされるけれど、生理そのものの知識についてはおざなりだ。いろんなメディア媒体で、私に向けての性の質問を受け付けてみると、男性からの質問の2割ほどに「生理のことがよくわかりません」という内容が見えるのも、そういうことだと思う。
月に一度生理がくることや、女性が生理中にどういった精神状態や肉体状態になるのかはわかっていても、なぜ生理がくるのか、生理がきて終わるまでの間、身体の中で何が起きているのか、そういった目まぐるしい内部状況や、また生理がくることの尊さというのを、実際にはよくわからないまま過ごしてしまっているところはあるのかもしれない。
学生の頃の私はまさにそうで、生理によって引き起こされる負担を少しでも軽減させることには強い意識を向けるのに、身体の中の出来事に対しては全く興味を持っていなかった。考えずともふらっと訪れ、いつのまにか波のように引いていくものだし、しんどいときはEVEを飲めば頭痛や腹痛は緩和された。動けないほど苦しくなったら産婦人科に行って、ピルで対応したりもした。
生理以外にもっと考えねばならぬ悩み事のほうが多くて、内部事情への興味はあっという間に薄れていく。だから、別によかったのだ。不安やとてつもない苦痛を覚えなければ、人は身体のことをそこまで調べないというのは、自分の身体で実証済みのことでもある。
子宮内膜は、よく「赤ちゃんのお布団」と例えられる。ふかふかに整えたベッドの上で、卵管から飛び出した卵子と、外からやってきた精子の結びつきを、さぁどうぞと子宮内膜が受け止めようとする。来客が長居しないことがわかると、そのベッドを外に出すのだ(毎回変えるなんて本当に律儀ですよな…)。ものすごく簡潔にまとめてしまったけれど、そのベッドを外に出し切るリフォーム作業が生理なのである。
しかし、そんな生命の、神秘的なリフォーム作業であるという意義は常に忘れ去られる。血を伴い、見事に精神をかき乱し、思いっきりメランコリーにさせられたとて、これもまぁ致し方ないと重い腰を上げながら自身を労わる気持ちを芽生えさせるには、何度もこの意義を思い返すことが大事なのかもしれない。
「この間はシングルベッドを運び出したくらいの痛みだったけど、今回はダブルベッドを運び出した並の痛みだな……だいぶ大胆な模様替えしてるんだなぁ」なんて優しく考えてみても、まぁ、ときたまドアを飛び蹴りしたくなるような衝動は絶対に芽生えるけれど。
その時は即様、寝るべし。寝れば心はどうにかなるべし。どうせずっと眠いし。なるべく穏便に、人に当たらずに、生理じゃね?と囁かれない程度に、痛みも薄いままに、どうにか長い冬も、過ごせますように。子宮に今日も、私は叫び続ける。
バナーイラスト=スケラッコ
さくら・まな●1993年3月23日、千葉県生まれ。工業高等専門学校在学中の2012年にSODクリエイトの専属女優としてAVデビュー。15年にはスカパー! アダルト放送大賞で史上初の三冠を達成する。著書に瀬々敬久監督により映画化された初小説『最低。』、『凹凸』、エッセイ集『高専生だった私が出会った世界でたった一つの天職』、スタイルブック『MANA』がある。
twitter: @sakuramanaTeee
Instagram:sakuramanatee
YouTube: まなてぃーちゃんねる