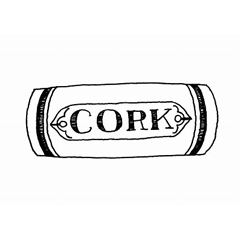まつもとあつしのそれゆけ! 電子書籍 第9回 脳科学者に聞く「紙の本vs.電子書籍」
更新日:2013/8/14
電子教科書について
まつもと :記憶への定着、というところからは、教科書として電子書籍を使う――いわゆる電子書籍の問題にも著書で触れていますね。わたしはこれまでの取材を通じて、理科で映像を使ったり、算数で図形の概念を伝えるのに向いているのではないか、という風に考えているのですが。
酒井 :確かに移動や重なり、図形の変化を動きで見せるといった際には、デジタルであることが、理解を助けることにはなるでしょうね。
ただ今まで、それがなかったら、頭に定着しないとか、勉強できなかったということは一切ない。むしろ、わかりやすくすることによって、そこを補う「手続き」を失っているのではないかと、僕は逆に心配になります。
まつもと :手続き?
酒井 :脳の中で「足りない情報」を補うための想像力ですね。『脳を創る読書』でも書いたように、情報の入力が少なくてできるかぎりそれを補おうとすることが、「思考力」を作るものだと、私は考えています。そうすると、足らない部分をデジタル表現で丁寧に補ってしまうのは、親切なんだけど、生徒はそれを自分でやらなくなったら、結果的に思考力そのものを奪うことになってしまう。
まつもと :思考力を養う手続きを失わないように教材を設計したり、指導の際気をつける、ということではダメなんでしょうか?
酒井 :うーん……使い分けができればもちろん良いけれど。たとえば、斜面にボールが落ちるという物理の問題を考えてみましょう。

上の図のように静止画で表現してあげると、「ボールは斜面をだんだん加速して落ちていくんだね」ということが伝わるわけです。でもこれを一気に動画で見せてしまったら、なんの意味もない。
子どもによっては、これは一定のスピードで落ちたというふうに思っちゃうかもしれない。加速したということすらわからないかも、というわけです。
まつもと :なるほど。いわゆるマルチメディア教材を作る側、あるいはそれを使って教える側のリテラシーや工夫が問われますね。
酒井 :作り手や教える側が、こういうものを教えたいと思っているかどうかが大切です。足らないものを補うものだとしたら、紙の本でも充分ではないかと考えています。 私の本の中では、マジックの教本を取り上げましたが、重要な動作だけが紹介されていて、残りの部分は自分で考えて補わないといけない。けれども、それがビデオ映像になってしまうと単なる物まねになってしまって見ている方も演じている方も面白くない。手品が自分のモノにならないし、そこからはっとするような更に良いものが生まれてこないわけです。この話をプロのマジシャンの方にしたら、その通りだと意気投合しましたね。
まつもと :学校での学習にも通じる話であると。
酒井 :そうですね。学習を通じてプロフェッショナルになるというのは、繰り返しそれを行って自分のものにし、どんな状況でもそれができるようにならなくてはいけない。物まねやコピーではなく、人ぞれぞれの個性や持ち味、それを行う状況にスムースにつながっていないといけないわけです。
まつもと :ここまでお話を伺うと、先生としては、教科書は紙のままでも良い、という意見になりますか?
酒井 :極論すればそうなります。教育は紙を守り続けた方が良い。そうじゃない方面で電子化の面白さ・利便性を追求してはどうかと思います。
まつもと :その結果、例えば教室では紙の本だけれど、図書室では電子書籍に触れる、といったイメージですね。
実際問題、義務教育で使用する教科書に関する法律でも対象は紙の本と定まっていますので、まず副教材としてデジタル教材を採用し、教育効果を見定めようという試みは続いています。
酒井 :そうですね。先日、ある学校の校長先生と対談してびっくりしたことがあるんです。理科の教材で、1年分のパワーポイントが付いてくる、というんですね。
まつもと :ほう・・・。
酒井 :だから、先生は何も準備しなくてもそのまま教室でそれを表示すれば授業の形になってしまう。でも、そうなると先生は何をしたら良いのかと悩むことになる、といった馬鹿馬鹿しい話になってしまうんです。
まつもと :電子黒板の導入にあわせた動きですね。でも、確かに表示して終わりでは困ります。
酒井 :全国一律でそれを使えば教育の質も一律になる、という考え方では教師を殺すことになるし、先生がそれで良いんだと思ったら、教育は崩壊します。
まつもと :教室で先生がただ黒板に板書する時間を短縮し、その分生徒に向き合う時間を増やそうという狙いがあるはずではありますが。
酒井 :その狙いを先生が誤解すると大変なことになる。生徒もそれを書き写すことで、先生が板書している内容の間違いに気づいたり、それを指摘して先生とやり取りすることで、クラス全体の学習効果が高まったり――そういうことが大事なんです。完璧な誤植のないものを延々見せられて、先生もそれを順に表示して満足し、でもテストをしてみたら、誰もその内容を覚えていなかった、なんてことになりかねません。
まつもと :たしかにデジタル教材導入のモデル校の授業例などを見ても、先生の側にむしろ紙の教科書で授業をするときよりも、高いリテラシーを求められていると感じました。工夫が求められるんですよね。果たしてそれを全国くまなく行き渡らせることができるんだろうか、とは思います。
酒井 :僕がそういうことを意識的に考えるようになったのは、先生が独自のプリント教材を使ってユニークな授業をすることが多かったからかもしれません。プリントには書き込むところがあり、先生の個性がそのままデザインされた形で授業が進んでいく。自分が書き込んだプリントを見返してみると、その時の授業風景が思い浮かぶくらいです。脳にとって情報がとてもリッチなんですね。そういう経験をしていたから、デジタルによって教材が規格化されてしまうと、そういった味がなくなってしまうのでは無いかと危惧しています。
まつもと :なるほど。
酒井 :プリントを作る時点で、先生が情報を取捨選択しているわけで、それは教育上必要なことだと思うんです。その先生にとって、ここが勘所だから、通常よりももっと時間をかける必要があると考えてそうする。逆にここはさっと済ませる、という風に。それはやっぱり教師の役割です。このクラスは、あるいはこの学生はこうだから、こうしようというプランが当然生まれるべきで、また別のシチュエーションならその場にあわせた教え方ができるのがプロの教師であるべきですから。
まつもと :かつて学校にテレビを導入して、映像番組による授業が始まったときも似たような議論がありましたね。お話を伺っていると、教材そのものよりも、それを扱うことになる先生側の問題が大きいと言えそうです。頼り切ってしまってはいけないと。
酒井 :銀塩カメラもフィルムの制約があるからこそ、何をどう撮るか気合いを入れて頑張るのだけれど、デジカメだと適当にパシャパシャ撮ってしまう、という話にも通じるものがあります。
まつもと :うーん……。ただ、さらに俯瞰して言えばデジタル環境に対するリテラシーの話になってくるのではないでしょうか? つまり、義務教育やさらに幼い頃から電子デバイスやデジタルコンテンツに親しんでこそ、デジタルとも適切に向き合い、活用できるリテラシーが生まれてくるのでは――そういう考え方はありませんか?
酒井 :確かにそれはあります。ただ紙というのは先ほどお話ししたように非常に変化に富み、思考力や個性を育んできました。これが、もし仮にデジタル――例えばPDFしか生徒が知らなかったら、そういう発想や可能性すら出てこないわけです。親や教師はそこには注意しないと。
まつもと :何が何でもデジタルから遮断せよ、というお考えではないわけですよね?
酒井 :もちろんそうではありません。取り入れつつ、ということです。ただ、先ほどのパワーポイントのように、易きに流れる懸念はあります。
まつもと :アジア諸国に対して、電子教科書の導入が非常に遅れているという意見もありますが。
酒井 :私は全く心配していません。例えばアメリカの教科書は分厚くて重くて、それを電子化することでメリットがあるということはよく分かります。でも、日本はどうかというと、そもそも教科書がそんな風になっていない。私から見ると、英語圏の教科書は説明に無駄が多すぎるんです。彼らの文化は、1つのことを伝えるのに、豊富に語り尽くすものですから。読む方も十二分に聞いて、読んで、それでやっと腑に落ちるというところがあります。
まつもと :洋書などもそうですね。
酒井 :日本人は元々口数が少なく、語らずして相手に伝える技を磨く文化を育んで来たのです。教科書だって当然エッセンスだけが書いてあり分厚くない。それでも読み手はくみ取ってくれるだろうというギリギリのところを狙っている文化でもあります。むしろ沢山書く方がかっこ悪いくらい。
ガラパゴスだって構わない
酒井 :僕は電子書籍や電子教科書でも、作り手が個性を活かしたプレミアムバージョンをどんどん作れば良いと思っています。
まつもと :現状の電子書籍のように汎用性を追及する方向性ではなく?
酒井 :そうです。これでしか読めないというところに逆に付加価値を付けていく。作家の原稿がそのまま読めますとか、著者からのメッセージが入ってますとか、いろんな方向性が考えられますよね。そういう面白さを追求して欲しい。それは我々の脳を刺激するし、記憶の定着においても重要な要素ですから。
まつもと :先ほどと似た質問になってしまいますが、そういった面白さや、そこから生まれる多様性・オリジナリティを表現するためには、早い段階からデジタル環境にある程度触れておく必要はありませんか?
酒井 :なるほど、そう誘導されてしまうと、そうしてもいいんじゃないかと(笑)。あくまで教育する側がきちんと比較して選べれば、良いと思います。
まつもと :個人的にはそういったデジタルリテラシーを育む教育が遅れてしまった結果、米国や韓国に例えば情報家電の分野で後塵を拝すことになったのではないかと考えることもあるのですが。
酒井 :いや、まずは我々が我々自身をよく理解しなければなりません。日本はそういった分野に時間がかかったり、慎重なのかもしれない。
でも、それも文化ですから流されてはいけないと思います。学生だってそうです。時間をかけてじっくり学んだ結果理解したことは、他の生徒より遙かに深いことだってある。他の国がどうあれ……。
まつもと :ガラパゴスでもいい?
酒井 :ええ。徹底的に日本人が心地よいと思えるものを生み出して行けば良い。アメリカの電子書籍の普及率を気にする必要も無いし、合わせようなんて考える必要もないです。日本人がどのように電子書籍を受容するのかという推移を見守りつつ、我々にとってもっとも良い形でそれを提供すれば、それは文化になっていくわけですから。
まつもと :たしかに外界と隔絶され、外来種が入ってこない本来の意味のガラパゴスであればそれでも良いかも知れませんが、実際電子書籍の世界でもアマゾンのキンドルサービスがいつ始まるかという状況です。そういった生態系を脅かす変化に対して、独自の進化を続ければ良いというのは残念ながら許されない状況ではないでしょうか?
酒井 :だからそこで良さを分かっている人が、もしかするとそれは老舗かもしれませんが、環境を守り抜くでしょう。これだけ西洋音楽が入って来たって、邦楽が無くなったりはしなかったのですから。日本の良さはそうやって残っていく。
でも、若い人が聞くのはやっぱりロックとかニューミュージックになっていますから、もっと邦楽も聞いて欲しい。そうしないとそもそも邦楽って何か分からなくなってしまう。とすると例えば指導要領でもう少し和楽器を使った時間を設けようという風に変わっていく必要があります。そうやって、選択肢が拡がればいい。
むしろ外敵が来た方が、自分たちにはこれが大切だったということに、はっと気づかされるきっかけにもなる。そうやって共存していけば良いと、わたしは楽観的に捉えています。
高機能な「脳」に迫る電子書籍を
まつもと :最後にやはり先生のご専門である脳と電子書籍の関係をおさらいして、インタビューを締めくくりたいと思います。本の中で、たとえ黙読であっても脳の中では本を音読しているという説明があり、とても興味深いと感じました。
「ダ・ヴィンチ電子書籍アワード」でも、絵本の朗読アプリは毎回高い評価を得ることが多いのですが、先生は絵本などの読み上げについては、どう考えていますか?
酒井 :ぼくたちの実験では、テキストの自動読み上げも対象にしています。ただ、小説などの物語は人間が読まないと、その文脈にあった「間」とか、登場人物の気持ちに添った抑揚をつけるといった表現ができない。電子書籍でもやはり人間が朗読した音声を選べるようにしなくてはいけません。
まつもと :そうですね。朗読アプリでもほとんどは声優さんが読み上げた音声を再生したり、親が読んだ音声を録音・再生する機能を備えていたりします。
酒井 :そこでも、個別性の追求が際限なく続いていくべきですね。子供にとって絵本はこれで十分ということはない。勝手に音声が再生されて、順番にページが送られる、ということでは先ほどのパワーポイントと同じことになってしまいますから。自分の親が読んでくれるから理解できることもあるし、実際に読んでいる様子や表情から伝わることや喜びがある。好みに応じて読み手や読み方のバリエーションを選べるとか、そこまで追及していって欲しいですね。
まつもと :なるほど。
酒井 :結局、そうやって多様性や個別性を追及していくと、ほとんど人間がやっていることと変わらなくなっていく。そういうところを目指すことが進歩だと思って欲しいですね。豊富な、旧字のような一見無駄と思えるような情報も切り捨てるのではなく、どんどんくっつけていく。デジタルには圧縮可能という強みがあるのですから。解像度が高くなって印刷物と変わらなくなったからこれで十分だなんて思わないで欲しい。
まつもと :もっと上を目指すべき?
酒井 :当然ですね。紙の質感を再現したり、ページをめくるとシェードが異なっていくとか、そういうところまで表現できるはずだし。実際、作家の自筆原稿を再現しようとしたら、そのくらいの表現が求められる、フルカラーでも足りないはずです。
まつもと :なるほど。今回先生のお話を伺って改めて感じたのは、紙=アナログのデジタルに対する優位性、スペックの高さですね。現状では敵いようもない。
酒井 :(頭を指さしながら)こっちがそうだってことなんですよ。脳がきわめて高スペックなんです。もしくは網膜や耳が非常にハイスペックなんです。そんな中、「このくらいでいいや」って大人が子供に与えるものをデザインしたり、技術者が仕様を定めているようでは全然足りないんです。
まつもと :先生が言いたいことは、「アナログに回帰しよう」ということではなくて「デジタルはもっと高みを目指すべき」ということなんですね。
酒井 :もちろんです。それが実現すれば、貴重な原稿が経年変化で劣化してしまうこともない。次の世代への遺産とすることができる。絶版になった本を紙のまま放置しておくのではなく、失われてしまう紙の本来の質感を当時のまま電子化して保存する、という発想が必要なんですよ。両方向なんです。
まつもと :電子書籍やデジタル教科書に関わる人達に求められる努力というのは非常に大きい訳ですね。
酒井 :そうなんです。だからそういう人たちにこそ、本当に紙の本を愛して欲しいと思います。
まつもと :その良さを再現し――
酒井 :紙の本が好きだから、それをいかに電子化できるかということに情熱を傾けて欲しい。それはロボットの開発にも似ています。人間にいかに近づけるかという研究にゴールはなく、妥協したらつまらないものができてしまう。鉄腕アトムを目指してこそ、ホントに凄いものができる。
まつもと :そこまで近づいて欲しい。
酒井 :そう、そういうことです。それは無限に時間がかかる挑戦です。そのくらい人間というのは実は奥深い。脳科学もまだまだこれからの分野ですが、その奥深さを垣間見せてくれます。一般の人にもその面白さを伝える役割を果たせるはずです。それをきっかけに、視覚を通じて「脳」は、物事をこう見ているのかも知れないと想像を膨らませると、そこに面白さがあるんです。
まつもと :今のところ、電子書籍と脳科学を結びつけた研究はありませんか?
酒井 :私の知る限りはほとんどないですね。
まつもと :そういったアプローチが今後求められますね。先生の研究にも期待しています。ありがとうございました。
 |
『脳を創る読書』酒井邦嘉 実業之日本社 1260円 |
――――――――――――――――――――――――――――――
ちば :なんだかすごく幅広い+奥深いお話しを伺った気がします。
まつもと :脳科学から読書、そして電子書籍を考える、というアプローチは新鮮でしたね。
ちば :でも、最後にもお話しがあったように、人間の脳が満足する電子書籍を作るのって大変そう・・・。
まつもと :そうですね。実際に販売される電子書籍はコストとの兼ね合いもありますから、どこかに落としどころは設けないといけません。ただ、ビジネスとは別に、アカデミックな世界では理想を追求するような研究がなされていて、私たちが手に取る電子書籍やリーダーに少しずつ反映されていく形になっていかないといけないなと思いました。
ちば :たしかに他の分野、商品だとそれが当たり前ですよね。
まつもと :先生の主張はアンチ電子書籍という風に捉えられがちなのですが、両方のバランスを本質的なところで図るべき、というお話しには共感します。「電子書籍元年」や海外に対する電子化の遅れ、という視点だけだとそういう本質的なところを見落としがちになるので、気をつけないといけないな、と感じさせられましたね。
まつもとあつしのそれゆけ! 電子書籍では、電子書籍にまつわる質問を募集しています。ふだん感じている疑問、どうしても知りたい質問がある方は、ダ・ヴィンチ電子ナビ編集部までメールください。
■ダ・ヴィンチ電子ナビ編集部:d-davinci@mediafactory.co.jp
イラスト=みずたまりこ
「まつもとあつしの電子書籍最前線」 バックナンバー
■第1回「ダイヤモンド社の電子書籍作り」(前編)(後編)
■第2回「赤松健が考える電子コミックの未来」(前編)(後編)
■第3回「村上龍が描く電子書籍の未来とは?」(前編)(後編)
■第4回「電子本棚『ブクログ』と電子出版『パブー』からみる新しい読書の形」(前編)(後編)
■第5回「電子出版をゲリラ戦で勝ち抜くアドベンチャー社」(前編)(後編)
■第6回「電子書籍は読書の未来を変える?」(前編)(後編)
■第7回「ソニー”Reader”が本好きに支持される理由」(前編)(後編)
■第8回「ミリオンセラー『スティーブ・ジョブズ』 はこうして生まれた」
■第9回「2011年、電子書籍は進化したのか」