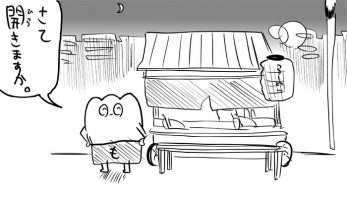人生空回りばかり…ため息をつくミチコの前に現れた、怪しげな屋台。暖簾をくぐると、そこにはいたのは⁉/悪魔の夜鳴きそば②
公開日:2021/2/20
「あの、いいですか」
その屋台には誰もお客が座っておらず、ぐつぐつと煮える寸胴の音だけが、静謐な路地に響いていた。
「1人なんですけど……」
私は暖簾をくぐって、店主に指を1本立てる。
そこにいたのは、
「や〜ん、いらっしゃ〜い」
オネェ口調で話す男性――らしき、白い物体。
成人男性並みの背丈がある、はんぺんの妖怪みたいな、謎の生き物がそこにはいた。
――ば、化け物だ。
私は見ないふりして踵を返そうとしたが、
「お待ちぃ!」
と、雄叫びのような声が飛んできたので、蛇ににらまれた蛙のように固まった。
「あんた、お腹空いてるんでしょう。顔色も悪いわよ」
彼は暖簾から上半身をぬるりと覗かせた。
真っ白なプルプル揺れる肉体に、ぎょろっとした大きな目ん玉が2つついている。
「だ、大丈夫です。いつもこんな顔です」
震える声でそう伝えると、
「そうなの。普段からキチンと食べてないの?」
と、心配するように聞いてきた。
「まぁ、忙しくて夜は、あんまり」
まさかの親身な質問に、私は拍子抜けしつつもなぜか答えてしまった。
「あらまぁ。じゃあ、今日くらいは食べていかない? たまには胃袋にあったかいもの入れな。そのほうが体も楽になるわよ」
まるでお母さんみたいな口ぶりで。
普段こうも心配されることのない私は、この謎の生き物の厚意を無下にするのもなんだかいたたまれなくなって、屋台のほうに戻ることにした。
「……ねぇ、店長、それ着ぐるみ?」
私が席についてそう漏らすと、彼は体を左右に揺らしながら鼻で笑った。
「違うわ。ただの美しい餅の妖精よ。なぁに? 今まで妖精は見たことないの?」
そう言って彼はにっこりと微笑む。
……私はまぁそういうこともあるか、と思いながらラーメンを注文することにした。
疲れているので深く考えたくないのだ。きっとあれだ、今、流行りのユーチューバーとかが『リアルな餅の着ぐるみでラーメン屋を営業してみた』とかやってるんだろう。
そう自分の中で結論づけて料理を待つことにした。
……いや、そんな企画、誰が見るんだろう。
ぐつぐつぐつぐつ。
ジャグジー風呂のように水泡が湧き起こる音だけが響く。
白い餅の背中から見える東京タワーを眺めながら、私は手持ち無沙汰から会話を投げかけた。
「ねぇ、店長さん」
「かしこまらずに、気軽にもちぎママってお呼び」
「あっ、うん。ねぇ、もちぎママ、この店いつからあったの? 私、4年も虎ノ門で働いてるけど、屋台そばなんて初めて見た」
彼は、粉のついた麺をジャッとお湯に放り込む。
沸騰に巻き込まれた麺が寸胴の中を踊っていた。
「昨日からここに出し始めたのよ、久しぶりにね」
「久しぶりってことは、前にもここでやってたこともあるんだ」
「そうね……ずっと前だけどね」
「ふーん……」
「屋台だからね、いつもフラフラといろんなところに行って営業してんのよ。あんた、今日はここに来られてラッキーよ」
「う、うん。……でも、虎ノ門じゃあまりお客さん来ないでしょ?」
するともちぎママは、まな板の上に横たわる細ネギをトントンと包丁で切り落としながら、首を横に振る。
「そんなことないわよ。あたいの店はお客がいるところにしか開かないから」
「どういうこと?」
飲み屋街のほうがお客なんてたくさんいるだろうに。
いまいち要領を得なかったので聞き返す。
「あたいの店はね、お腹と心がペコペコになった人間のもとにしか訪れないって決めてるの。だから今日、あんたがこの店を見つけてこられたのは、偶然じゃなく必然ってわけよ」
「フゥン……」
「あんた信じてないでしょ」
ママはジロリとこちらを睨めつける。
「信じますよ。餅の《妖怪》がいたんだから、もうちょっとやそっとじゃ驚かないです」
私はもうヤケクソでそう答える。
湯気越しに間近でもちぎママを眺めていると、その白い肉体はどう見ても着ぐるみじゃないようだ。こんなことあり得るのだろうか。だけど、だんだんこれが現実なんだと飲み込まざるを得なくなっていた。
きっと私は、最近とくにダメダメな毎日で落ち込んでいたから、陰気なオーラで妖怪を呼び寄せてしまったのかもしれない。
「餅の《妖精》だからね、妖精。間違えちゃダメよ。なにもあんたの魂を奪いにきたわけじゃない。元気が出るきっかけを与えにきたオカマなのよ」
店長は冷蔵庫からチャーシューを取り出す。鶏胸肉のチャーシューのようだ。夜食にはヘルシーでありがたい。
「だから、他のお客はここには近づいてこられないわけよ。悩みと空腹を抱えていないかぎりね」
「不思議なお店。でも大丈夫なの? お客さんが少なくても……」
「いいのよ。落ち着いたほうがゆっくり食べられるでしょう。それに、もしあたいがいろんなお客を呼びこむようにしてしまったら、大変よ」
「なんで?」
「考えてごらんなさいよ。きっとあたいの美貌を目当てに連日連夜、行列ができるわ。そうなったら街が大変になるじゃない。あたいの美しさは東京タワーを霞ませてしまうわ」
お腹が減ったが、この妖精の減らず口を聞いていると、待ち時間がつぶせてよかった。
それからすぐにラーメンが私の前に運ばれてくる。
鶏チャーシュー、少量のやっこネギとどっさり白髪ネギ。あとはメンマと海苔に、すりごまが少し散らされた具材たち。その隙間からたんぽぽ色のきれいな中太麺と、透き通った淡麗醤油のスープが覗いている。
「召し上がれ」
「……いただきます」
私は湯気の立ちのぼる器に、そっとレンゲを落とす。すくい上げたスープに浮いた脂を、火傷しないように吸い上げる。
ずずっ……。
緊張していたような気持ちも、乾いた喉も、それだけでホッとした。秋のそぞろ寒さを吹き飛ばすような、そんな温度が体に伝わってきた。
「おいしい……」
「あら〜、よかった」
またぐつぐつと沸騰する音だけが響く。経年劣化した屋台の木製ベンチがきしむ。お尻の骨も痛むくらい、硬い座り心地も新鮮だった。なんだかすべてが居心地よく感じた。
もうあと1時間半ほどで明日に日付が変わるというのに、どうしてだろう、明日が来ないような気がした。夜がどこまでも続くような、そんな気持ちになった。
ああ、おいしい。
「もちぎママ、ほんとおいしい。うん、おいしいよ……」
カチャカチャとザルや菜箸を洗う彼の白い後頭部に、そう投げかける。
あったかいのはスープだけじゃない。この静かな空間そのものが、暖房もないのに暖かく感じる。
ちょろいだろうか、私はもう安心しきっていた。
こんなにおいしいラーメンを出してくれたなら、この妖精と言い張る生き物が悪いやつじゃない気がするのだ。
それから私は、ラーメンに目を落としながら、フゥとため息をついた。
「私、幸せになりてぇ……」
……やってしまった。
ふと、そう漏らしてしまった。
まるでその台詞は、敗北に打ちひしがれて「強くなりてぇ……」と嘆く、少年漫画の主人公みたいだった。
それに、そこそこ大きな声でつぶやいてしまったので、もちぎママの耳にも届いただろう。
おセンチな独り言をつぶやく、ちょっと痛い女だって思われたかもしれない。
とたんに恥ずかしくなって、急いで麺をすすって大げさに音を立てた。
「ごほぉ」
むせた。
すると、もちぎママがそっとお冷やを注いで出してくれた。
そして彼は口を開いた。
「幸せになりたいなら、なりなさい」