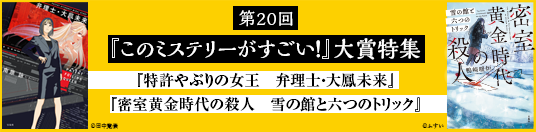10年前に起きた「雪白館密室事件」。香澄が事件当時のまま残された部屋を調べていると/密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック③
公開日:2022/3/5
第20回『このミステリーがすごい!』大賞・文庫グランプリ受賞作。鴨崎暖炉著の書籍『密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック 』から厳選して全5回連載でお届けします。今回は第3回です。三年前に起きた日本で最初の“密室殺人事件”。その判決を機に「どんなに疑わしい状況でも、現場が密室である限り無罪」が世間に浸透した結果、密室は流行り病のように社会に浸透した。そんななか、主人公の葛白香澄は幼馴染の夜月と一緒に、10年前に有名な「密室事件」が起きた雪白館を訪れる。当時は主催者の悪戯レベルだったが、今回はそのトリックを模倣した本物の殺人事件が起きてしまい――。あなたは、この雪白館の密室トリックを解くことができるか!?「雪白館密室事件」が起きたのは、香澄が泊まる西棟とは逆側の東棟の2階にあった。肝心の密室事件があった部屋は、10年前のまま残されている。香澄が部屋を観察しながら推理していると、そこに密室探偵の男が現れる。

『雪白館密室事件』が起きたのは、僕が泊まる西棟とは反対側に位置する東棟の二階だった。東棟の二階の廊下には毛足の長い絨毯が敷かれ、歩くとフカフカとする。僕の前を行く迷路坂さんが立ち止まり、一室の扉を指し示した。
「この部屋でございます」と迷路坂さんが言った。
この部屋か、と僕は思った。
少し緊張しながら、ノブを掴み、扉を開く。その部屋は、僕が泊まっている西棟の部屋と同じくらいの広さだった。十畳ほどで、ただし二つの部屋が連なっている造りだ。部屋の入口から見て左手の壁にもう一つ扉があり、隣の部屋に行ける造り。そしてその隣の部屋こそが『雪白館密室事件』の本当の現場なのだ。
僕は室内に入り、左手の壁の扉を潜る。今は扉は開いている状態だ。十年前の─、事件の際にも開いていたらしい。
隣室に踏み入った僕の目に留まったのは人形だった。ナイフが刺さったフランス人形─、ではなく、無傷のクマのぬいぐるみ。さすがにナイフの刺さった人形ではショッキングなので、代わりに置かれているらしい。
僕は過去に書籍で読んだ事件の概要を思い出してみた。あらましはこんな感じだ。
十年前─、雪城白夜が主催するホームパーティーでのこと。中央棟のリビング(現在はロビーに改修されている)で皆が食事を楽しんでいると、東棟の方から女の叫び声が聞こえた。びっくりした皆は、悲鳴が聞こえた東棟に向かう。そこで再び叫び声。どうやら二階から聞こえる。階段を上り廊下を右往左往していたところで、みたびの叫び声。そこでようやくと皆は、どの部屋から悲鳴が聞こえているかに気が付いた。ノブを掴み、回す。鍵が掛かっていた。来客の一人が雪城白夜に言う。白夜と同年代のミステリー作家だ。
「この部屋の鍵は?」
「数日前から紛失しているんだ」と白夜は答えた。「どこに行ったのかわからない。でも、おかしいな。昨日確かめた時には、この部屋には鍵が掛かっていなかったはずだが」
「となると、誰かが鍵を掛けた?」
「そう考えるしかないだろうな」
今度は別の来客が訊ねる。大手出版社の若手編集者だ。
「マスターキーはないんですか?」
「マスターキーはないんだ」と白夜は首を振る。
「でも、持ってましたよね、マスターキー。使っているのを見たことがあります」
「ああ、あれは西棟のマスターキーだよ。西棟と東棟では鍵の体系が違っているんだ。西棟のマスターキーでは、東棟の部屋の鍵は開けられない。そして東棟にはマスターキーが存在しない」
「どうして存在しないんですか?」
「さぁ、どうしてだったかな? 忘れてしまったよ」
のらりくらりと白夜は言う。そんな彼にまた別の客が訊ねた。デビューしたばかりの十代の女性作家だ。
「じゃあ、合鍵はないんですか?」
「合鍵はない。この雪白館の鍵はすべて極めて特殊なものを使っていてね。合鍵を作ることは不可能なんだ」
「じゃあ、部屋に入るには窓を破るしかないですね」
「いや、窓には格子が嵌まっているから、人が出入りすることはできない」
「じゃあ、いったい、どうやって中に入れば……、」
そこで、再び女の悲鳴が聞こえた。皆は顔を見合わせる。「仕方がないな」と別の客が言った。辛辣で知られる三十代の男性評論家だ。
「ドアを破ろう。いいですよね、先生」
「緊急事態だ」
白夜は渋々と頷いた。
体格のいい男たちが数人、内開きの扉の前に陣取る。そして掛け声とともにドアにぶつかった。扉が軋む音。それを何度となく繰り返す。十回に迫ったところで、ようやく扉が音を上げた。
破られた扉が勢いよく開く。室内は真っ暗だった。誰かが手探りで電気を点ける。
照明に照らされた部屋の中に、異変は見つからない。
「もしかして、あっちの部屋じゃないですか」と大手出版社の若手編集者が言った。彼が指差しているのは、入口から見て左手の壁に設えられた扉だった。隣室に移動するための扉で、今はその扉は開いている。開けっぱなしの状態だ。扉は壁の中央よりも右側に─、つまり、部屋の入口から見て奥側に設置されていた。
皆でおっかなびっくりと、隣室に続く扉へと近づく。隣室の照明は、入口のある主室の照明と連動しているようだった。主室の電気を点けたことで、今は隣室の照明も灯っている。なので扉に近づくと、中の様子は良く見えた。隣室にはナイフの刺さったフランス人形が転がっていた。ちょうど、扉の真正面に当たる位置だ。床ごと貫くかのように人形に突き立てられたナイフは、刃渡りが三十センチほどもあり、その刃が扉の方を向いてキラキラと輝いていた。
悲鳴を上げる者はいなかった。ただ、皆びっくりした様子だった。
フランス人形が転がった隣室には、その人形の他にも特徴的なものが二つあった。事件の遺留品と言ってもいいのかもしれない。
一つ目がボイスレコーダーだ。これはフランス人形の傍に落ちていた。再生させると女の悲鳴が聞こえた。どうやら先ほどの悲鳴は、ここから流れていたものらしい。
そして二つ目は、『被害者』役のフランス人形から少し離れた位置に転がった瓶だ。その瓶の中には鍵が入っていた。白夜は透明なプラスチック製の瓶を手に取って、「間違いない、この部屋の鍵だ」と言った。
皆はざわついた。
「じゃあ、この部屋は─、」と白夜と同年代のミステリー作家が言った。「密室だったということか?」
「信じがたいが」と白夜は言った。「そういうことになるな」
「いや、そんなわけないでしょう。先生、ちょっとその鍵貸してくださいよ」と辛辣で知られる三十代の男性評論家が、白夜から鍵の入った瓶を受け取る。固く閉められた蓋を開けて、中から部屋の鍵を取り出した。「よくあるトリックだ。どうせこの鍵が偽物とかだろ」
彼はそう言って鍵を持って、部屋の入口の扉まで移動した。そして鍵穴に鍵を挿し、驚いたように目を丸くする。
「本物だ」と辛辣で知られる三十代の男性評論家は呟いた。
「信じられないな」と白夜は言った。「まさか、こんなことが起きるとは」
「てか、先生」
「うん?」
「先生、さっきから、何をニヤニヤしてるんですか?」
とデビューしたばかりの十代の女性作家が言った。
皆の視線が白夜に集まる。白夜は笑みを消して、しれっと言った。
「笑ってないよ」
「どう見ても笑ってるじゃないですかっ! あっ、もしかして、さては先生─、」
十代の女性作家はそこで言葉を止めた。皆まで言うまい、と彼女は思った。このジジイを吊るし上げるのは、密室の謎を解いてからでも遅くはない。
彼女は宣戦布告のように、挑戦的な笑みを白夜に向けた。その笑みを浮かべたのは彼女だけではない。白夜と同年代のミステリー作家も、大手出版社の若手編集者も、辛辣で知られる三十代の男性評論家も─、そして他の客たちも皆、同じ気分だった。
自分が一番最初に謎を解いて、このジジイに目にものを見せてやる。
こうしてホームパーティーの隠しイベント─、『雪白館密室事件』の推理大会の幕が上がった。一夜のうちに様々な推理が飛び交い、そして真相に辿り着いたものは誰一人としていなかった。
「……」