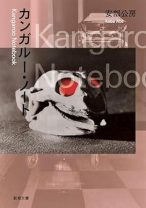19歳で下半身不随になった天才ドリブラー。夢と才能を奪われた青年が、世界初の車イスプロサッカー監督になるまでの苦闘の日々
更新日:2017/7/31

かつて、日本にJリーグはおろか「プロのサッカー選手」という概念もなかった時代に海外挑戦を夢見ていたサッカー少年がいた。彼の名は羽中田 昌(はちゅうだ・まさし)。数々のサッカー関係者から、将来のA代表入りを確実視されていた「天才」ドリブラーだった。韮崎高校時代には三度の全国高校サッカー選手権に主力として出場。1983年、三年時に出場した第63回の決勝では病気の影響から20分間のプレーに留まったものの、鮮烈な印象を残す。たまたまテレビ中継を見ていた漫画家の塀内夏子さんが、羽中田さんをモデルにしてヒット作『オフサイド』を生み出したほどだ。
しかし、高校卒業後まもなく、羽中田さんは一生、車イス生活を強いられることになる。失意の底にまで落ちた「天才」は、人生に新しい光を見つけられたのか? 『必ず、愛は勝つ! 車イスサッカー監督 羽中田昌の挑戦』(講談社)は羽中田さんの半生を追った、渾身のスポーツルポである。揺るぎない夢が持つ巨大な力は、サッカーファンに限らず強く読者を惹きつけるだろう。
1983年8月6日。高校卒業後、自分を見つめ直すために浪人生活を送っていた羽中田さんは、雨の中バイクを運転していて、下り坂で前輪をパンクさせる事故に遭った。三ヶ月以上の入院を経て、医師から宣告されたのは「もう足は動かない」という残酷な事実だった。
それでも、「天才」とまで呼ばれた男がそう簡単にサッカーをあきらめられるはずがなかった。薬や鍼治療を試し続け、一年以上も休職し中国の気功師を頼りもした。しかし、気の済むまで治療をやり抜いたことでついに羽中田さんは区切りをつける。1990年6月、羽中田さんは妻となったまゆみさんとともに中国からの帰国を決断、やがて山梨県庁での仕事に没頭するようになる。
そんな羽中田さんのサッカー熱を蘇らせたのは1992年のJリーグ開幕だった。高校時代のライバルたちが、自分も立ったことがある満員の国立競技場でプレーしている姿を見て、羽中田さんは自分に問いかけた。
〈オレ、やっぱりサッカーが好きだ。ピッチを駆けることはできなくても、サッカーが好きだ。大好きだ。これ以上、自分の気持ちを偽っちゃいけない。心に穴が空いたままで、生きていくことはできない〉
羽中田さんはサッカーの指導者になろうと決意する。県庁から慰留されるも、退職した羽中田さんはまゆみさんとスペインのバルセロナに渡る。少年時代、羽中田さんがサッカーを愛するきっかけになったヨハン・クライフが、監督としてFCバルセロナを率いていたからだ。当時、クライフのチームは「ドリームチーム」と呼ばれ、現在のバルセロナにも続く完成度の高いパスサッカーを披露していた。
最先端の戦術を現地で観戦しながら、語学学校やコーチングスクールに通う日々。同時期の留学仲間には、後に五輪代表監督にもなる反町康治さんや、現・株式会社いわきスポーツクラブ代表の大倉智さんもいた。「選手に手本を見せられない」という理由から現地のスクールではライセンス取得を許されない聴講生扱いだったが、それでも羽中田さんのサッカー観は、反町さんたちと比べても引けをとらないほど熱かった。顔を合わせるたびに始まるサッカー談議に加え、一流の授業と地元チームの見学で、羽中田さんは愛するサッカー漬けの日々を送る。
サッカーの指導者としては車イスが全く弊害にならないわけではない。帰国後、晴れてS級ライセンスを取得した後も、順調な出来事ばかりではなかった。それでも、羽中田さんは現在、東京23フットボールクラブの監督としてJリーグを目指しながら、憧れのバルセロナのような美しいサッカーを日本で実現するという高い理想を掲げている。羽中田さんは体の自由を奪われても、心の自由まで自ら奪うことができなかった。Jリーグ元年に感じた衝動に蓋をしてしまったら、今の充実した生活はなかったかもしれない。「できないこと」を決めてしまうのは世間や常識ではなく、自分自身なのだ。本書は心の声に正直になる大切さを読者に教えてくれる。
文=石塚就一