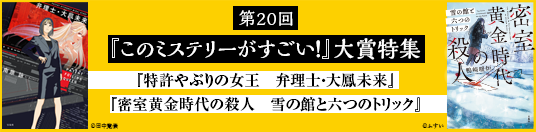「新しい知的スポーツを楽しむように、特許をめぐる争いを楽しんでほしい」──『このミス』大賞受賞『特許やぶりの女王』南原詠インタビュー
更新日:2022/3/24

特許の専門家・弁理士が、絶対的不利な状況に立ち向かう! 第20回『このミステリーがすごい!』大賞受賞作『特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来』(南原詠/宝島社)は、現役弁理士が描くリーガルミステリー。女性弁理士・大鳳未来の強気なキャラクター、VTuberをめぐる特許紛争などが話題を呼び、早くも5万部を突破する勢いだ。
大手企業で働く弁理士が、なぜミステリー作家を志したのか。特許×VTuberという着想はどこから生まれたのか。そして、特許論争の面白さとは。南原詠さんにお話をうかがった。

取材・文=野本由起 撮影=奥西淳二
技術の切り方にもセンスが問われる。だから、弁理士の仕事は面白い
──南原さんは企業内弁理士として働いているそうですね。もともとはエンジニアでしたが、同じ会社内で特許出願を行う知的財産部門に異動したとうかがっています。この分野に興味を持ったきっかけは?
南原詠さん(以下、南原):率直に言えば、エンジニアとして挫折したからです。入社して3年くらいで「向いてないな」と思って。その後のキャリアパスを考えていたところ、たまたま元エンジニアが知的財産の仕事をするケースが少なくないと聞いたんです。「じゃあ、やってみようかな」と思ったのがきっかけです。
──弁理士は、特許のプロフェッショナルです。具体的にはどういう仕事をしているのでしょう。
南原:弁理士の仕事は、よく“攻撃”と“防御”という言葉で表現されます。“防御”は、特許権侵害の警告書が届いた時にどう対応するか。でも、やっぱりメインとなるのは、特許出願を行う“攻撃”です。「今度、こういう機能が搭載された新製品を発売します。だから、この機能についてちゃんと権利を取っておきましょう」という仕事ですね。企業の知財部の場合、開発部の社員に話を聞いて、「これは出願しましょう」「これは逆に出さないほうがいいです」と判断して、発明という形に技術を切り取って権利化します。
──仕事の面白さややりがいを感じるのは、どういう時ですか?
南原:技術の切り取り方には、ノウハウがあるようでないんです。どうやって発明を閃くかと同じように、どうやって切り取るかが難しくて。ある程度、システマティックな流れができていますが、慣れや経験、個々のセンスによるところが大きいんです。そこがこの仕事の面白みかもしれません。
──法律知識が重視されるのかと思いきや、センスも問われるお仕事なんですね。
南原:弁理士として独立した先輩は、「ひとつのものをどの角度から見るかによって、技術の切り取り方が変わってくる」とおっしゃっていました。例えばスマホのタッチパネルで、アイコンを制御するプログラムを組んだとします。それによって今までよりも動作が2倍近く早くなった場合、それをプログラムの発明と見るのか、それともタッチパネルの発明として見るのか。もっと言えば、スイスイ快適に動かせるスマホを発明したと考えることもできます。切り取り方ひとつで、どういう発明かが大きく変わってくるんです。

小説執筆のきっかけは、論文作成のストレスを発散するため
──弁理士として働きつつ、小説家を志したきっかけは?
南原:いちばん大きいのは、弁理士資格を取るための勉強をしたことですね。答案を書く試験なのですが、個性を出してはいけなくてとにかくつまらないんですよ(笑)。苦にならない方もいるでしょうけど、僕はストレスが溜まってしまって。好き勝手に書かせてくれという気持ちが、小説を書きたいという気持ちにつながりました。ある日突然、つながっちゃったというのが正直なところです。
──小説家を目指すにあたって、若桜木虔先生の小説講座を受講されたとか。
南原:そうなんです。確か就活の時だったと思うのですが、小説の書き方に関するQ&Aが載ったサイトを見つけたんです。そこで答えていらしたのが若桜木虔先生でした。ふと小説を書きたいなと思った時に、先生のことが頭に浮かんで、調べたところメール通信添削講座やカルチャーセンターで講座を開いていることを知って。それで、弁理士試験合格後の研修が終わった最終日に申し込みました(笑)。
──そこから受賞までは順調でしたか?
南原:『このミステリーがすごい!』大賞に7回応募しているので、自分としてはあっと言う間でした。「もう7年経っちゃったのか」みたいな感じでしたね。当初は書くのが遅くて、ちょっと油断していたら締め切りまで残り半年になっていて。『このミス』大賞は5月31日締め切りなんですけど、出し終えてフッとひと息ついているともう秋になって、「ああ!」と思ってると年が明けてしまうという(笑)。
──『このミス』大賞一本に絞って投稿されていたのでしょうか。
南原:他にもいろいろ出しましたが、毎年応募していたのは『このミス』大賞でした。若桜木先生からも「この作品だったら『このミス』大賞がいいんじゃない?」とアドバイスをいただいていたんです。同門に、日本ミステリー文学大賞新人賞でデビューされた石川渓月さんがいらっしゃるんですね。ご本人は「これ、ミステリーじゃないのに」と思いながらも、先生のアドバイスにしたがってこの賞に応募したところ見事に受賞されたそうです。
──南原さんが『このミス』大賞を勧められたのは、なぜだと思いますか?
南原:キャラクターや語り口など、いろいろな要素から「ここがいいんじゃないか」と考えてくださったのかなと思います。実際、初めて『このミス』大賞に応募した時に期待のコメントをいただけたので、相性は悪くないのかなと思いました。