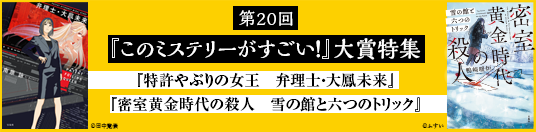ミステリー好きの高校生・香澄と幼なじみの夜月。ふたりは今晩の宿である「雪白館」へ向かうが…/密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック②
公開日:2022/3/4
*
「大変、香澄くん、ここってネットに繋がらない」メロンソーダを飲みながら、夜月が僕の向かいの席で悲痛な声を上げた。僕はロビーのソファーに腰掛けながら、紅茶に口を付けて言った。
「タクシーを降りた時から圏外だっただろ?」
「そうなんだけど、ホテルに着いたらWi-Fiが使えると思ってたんだもん」夜月は、ううぅ、と嘆き、傍のテーブルを布巾で拭いていたメイドの迷路坂さんを呼び止める。
「すみません、ここってWi-Fi飛んでないんですか?」
「申し訳ございません」と迷路坂さんは、あまり申し訳なくなさそうに言った。「ネット回線は引いておりますが、無線LANは導入していないので。どうしても携帯電話は圏外になってしまいます」
「ううぅ、まじか。陸の孤島やんけ」夜月はそう嘆きながら、スマホをポケットの中にしまった。そしてロビーを見渡して言う。ロビーには、ぽつぽつと客がいた。
「今日は何人くらいのお客さんが泊まりに来ているんですか?」
「予約されているお客様は十二人です」
「十二人も。そんなに」夜月は目を丸くした。そして納得のいった顔をする。「やっぱり、みんなイエティに興味があるんですね」
「イエティ?」
「無視してください」僕は迷路坂さんにそう告げた。
迷路坂さんは首を傾けた後、ホテルが繁盛している理由について教えてくれた。
「手前味噌ですが、支配人の作る料理がとてもおいしいんです」
「詩葉井さんの?」と夜月は言った。「料理は彼女が作っているんですか?」
「はい、創作イタリアンで、とてもおいしいと評判です。この館が長期滞在のお客様しか受け入れていないのも、元々は色んな料理を味わっていただきたいという詩葉井の我が儘から始まったものでして。でも、その甲斐もあって、料理を目当てにやって来られるお客様も多いんですよ。例えば、あそこに座られている社様とか」
迷路坂さんは、少し離れたテーブル席で談笑する男に目を向けた。高そうなスーツを着た四十歳くらいの男と、セーターにジーンズ姿の三十歳くらいの男が談笑している。社というのは、四十歳くらいの男の方らしい。
「ちなみに社様は会社の社長らしいのですが」
「社長の社さん」と夜月。
「うちの料理を大変気に入ってくださっているようで、よくおいでになるんです。まぁ、私は支配人を口説きに来ているんじゃないかと疑っていますが」
そう言われると、そんな感じがする。社はいかにも自信にあふれたタイプで、瞳もギラついていた。何というか、女癖が悪そうだ。
「もう一人の方は、社さんのお連れの方ですか?」と夜月が訊いた。社と話すセーターの男に視線を向ける。社とは対照的に、落ち着いた雰囲気の容姿だった。
「いえ、あのお客様と社様は初対面だそうです」と迷路坂さんは言った。「お二人とも時計が趣味だそうで、互いの腕時計を見てすぐに会話が弾んだそうです。お二人とも昨日から泊まっているのですが、たった一日であのように仲良くなられました」
確かに、初対面とは思えない雰囲気だった。しかし社長である社が目に留めるほどの時計を付けているとは。あのセーターの男も、実はかなりの金持ちなのだろうか。
「はい、医者だそうです」
「医者かよ」やはり上流階級だったか。
「はい、石川さんという名前だそうで」
「医師のイシカワさんね」と夜月。
「二人とも何百万円もする時計を使っているそうです。そこまでの高級品を身に付けるのは、私は逆に下品なんじゃないかと思っているのですが」
迷路坂さんは、そんな風に毒を吐く。彼女は毒舌メイドだった。おまけに、よく考えると顧客の職業といった個人情報もペラペラと喋っているし。個人情報ゆるゆるメイドなのかもしれなかった。話し相手としては楽しいけれど、ホテルの従業員としてはどうかと思う。
そんな個人情報ゆるゆるメイドは、こちらにぺこりと一礼して、その場を立ち去ろうとする。僕はそこでふと迷路坂さんに用があったことを思い出した。呼び止めると、迷路坂さんはどこか迷惑そうに視線を向ける。
「何でしょう?」
「いや、何というか」僕は紅茶で喉を湿らせて言う。「この館には、雪城白夜の持ち物だったころから、手の入っていない部屋があると聞きまして」
僕の曖昧な言い回しに、それでも迷路坂さんはピンと来たようだった。「ああ、あなたもあの部屋が目当てなんですか」と告げる。
「あの『雪白館密室事件』の犯行現場が」
僕はこくりと頷いた。かつて雪城白夜のホームパーティーで起きた事件の現場だ。
迷路坂さんは小さく肩を竦めた。
「密室の謎解きなんて─、私には何が面白いのかわかりませんが、もちろんお見せすることは可能です。支配人の創作イタリアンと並んで、当ホテルの名物ですから」
僕は紅茶を飲み干し、腰を上げた。そしてメロンソーダを飲んでいる夜月に訊く。
「夜月はどうする?」
「私はまったく興味ないので」
間髪入れずに返ってきた。僕はとても寂しかった。