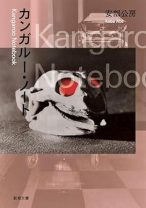家族の中で「ひとりだけろう者」という疎外感…家族の断絶とそれをつなぎ直す言葉の意味『わたしのいないテーブルで』
公開日:2021/12/11

『わたしのいないテーブルで デフ・ヴォイス』(東京創元社)は、手話通訳士・荒井尚人を主人公にした丸山正樹氏の代表作シリーズ第4作。荒井は両親と兄がろう者であり、家族の中で自分ひとりだけが聴者として育った“コーダ(CODA)”(“Children of Deaf Adults”)だ。
音声日本語よりも早く覚えた日本手話を使って家族と何不自由なく会話をしながらも、自分だけが聴こえることにある種の孤独を感じ、それが長じて家族と疎遠になった時期もあった荒井。そんな彼も今では警察官のみゆきと結婚し、その連れ子の美和、荒井とみゆきの間に生まれた瞳美の家族4人で幸せに暮らしている。瞳美はろう者として生まれてきたため、家族の中で瞳美だけが聴こえない。だから、荒井たち家族は瞳美の前では全員が日本手話を使って会話をしている。幼い瞳美にとって、言葉とは日本手話のことだ。物語は2020年春、コロナ禍における荒井の家族と、ひとつの事件を軸に展開していく。
ウイルス感染拡大の影響で思うように仕事ができない荒井が、なじみのNPO法人から“支援チーム”の一員として協力を依頼される。その仕事は、実の母親を刺して傷害事件の被告となった女性ろう者、勝俣郁美の通訳だった。幼い頃に両親が離婚した郁美は今回の事件の被害者である母親の智子に女手ひとつで育てられ、専門学校卒業後は家を出て派遣社員として仕事をしてきた。しかし、コロナ禍の影響で休職を余儀なくされ、久しぶりに郁美が実家に戻ってきたところに事件は起きた。郁美はなぜ母親を刺したのか? 彼女は傷害の事実については認めても動機については何も語ろうとしない。全治3週間のケガを負った母親の智子によると、料理をしていた郁美と味付けについて口論になり、突然刺されたという。しかし、その口論の内容ははっきりとしない。智子は聴者で手話がわからないため、ろう者である郁美の言うことがほとんど理解できないからだ。
なんとか郁美の心を開かせて、「話してもらう」ための糸口を探していた荒井の前に浮かび上がってきたのは、タイトルの由来にもなっている“ディナーテーブル症候群”という言葉だった。これは、ろう者が聴者の家族の会話に十分参加できず、疎外感を覚えている状態のこと。この疎外感こそ、聴者とろう者の立場は逆だがCODAとして幼い日の荒井がずっと感じてきたものであり、荒井が我が子の瞳美に感じさせまいとしているものだった。
家族のつながりは個人の思いと関係なく存在する。互いを慈しみ合う気持ちがあれば、それはより密なものになっていくだろう。しかし、そこにいったん断絶が生じてしまえば、そこに生じる不在の大きさが、疎外感をより深いものにしてしまう。この小説は聴者が普通に暮らしていれば気づくことのないコロナ禍におけるろう者の困難をリアルに描きつつ、普遍的な家族の問題、人と人とをつなぐ言葉の大切さについて、真摯に語っている。家族の中で自分だけが疎外感を味わっているような感覚は、誰もが経験しているものではないだろうか。
「私一人、家族であって家族じゃなかったみたい」
だからこそ、荒井の過去、郁美の動機、それぞれの疎外感の真実が見えたときに強く胸を打たれる。言葉が家族の断絶を生むのかもしれない。しかし、それをつなぎ直すのもまた言葉なのだ。
文=橋富政彦