どこまでのめりこむと病気? 生活が破綻する前に知っておきたい、ネット依存・ゲーム依存のこと
公開日:2018/7/31
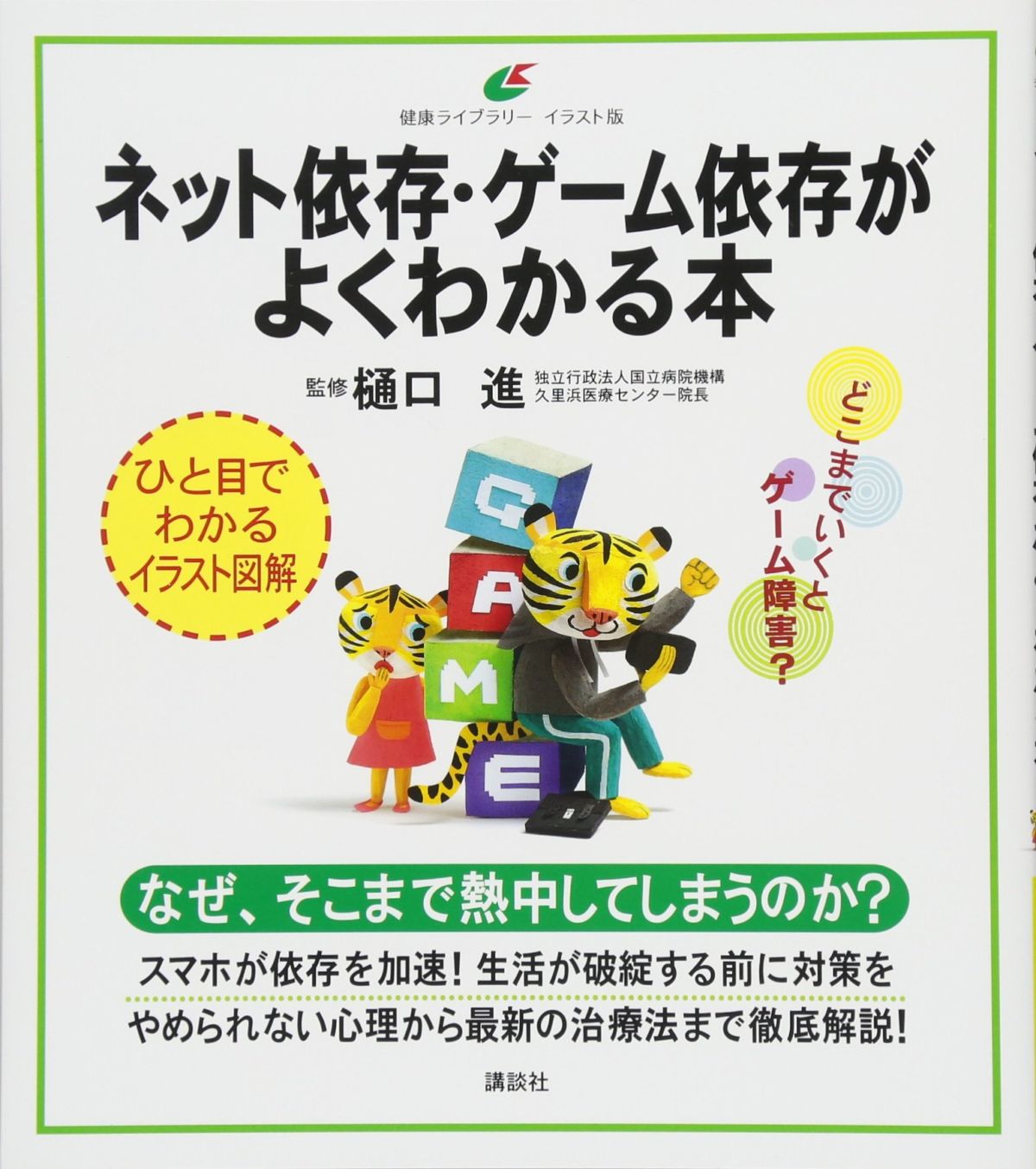
数年前、パソコンのMMO(大規模多人数型オンラインゲーム)などにハマり、生活のすべてを捧げてしまう“ネトゲ廃人”という言葉が話題になった。今やネットに接続する端末の主流はスマートフォン(以下、スマホ)に切り替わった印象もあるが、手元でいつでも操作できる利便性から、日常で“依存”を自覚する人たちも多いかもしれない。
今年に入り、WHO(世界保健機関)がオンラインゲームなどに熱中して生活に支障をきたす症状を「ゲーム障害」として認定したのも記憶に新しい。社会的な対策も進む中で、世の中に警鐘を鳴らす本『ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本』(樋口 進:監修/講談社)が刊行された。
私たちとスマホやネットとの関係に、ハッとさせられる内容がまとめられている。
●ネット依存・ゲーム依存になりやすい/なりにくい人の傾向
依存とはそもそも「やめたくても自分では欲求や行動を制御できない『コントロール障害』の状態」に陥っていることだと本書は指摘する。スマホでいえば、画面を見ながらの会話を注意されてもやめられない、睡眠不足やお金の使い込みにより日常生活に支障をきたすといったケースなどが当てはまる。
さらに、久里浜医療センターが世界各国の「ゲーム障害」に関する疫学研究を調査したところ、ネット依存・ゲーム依存になりやすい人となりにくい人には以下のような特徴があることが分かったという。
【なりやすい人】
・ゲームを肯定する傾向が強い
・男性である
・友人がいない(少ない)
・衝動性が高い
【なりにくい人】
・社会的能力が高い
・自己評価が高い
・学校(勤務先)でうまく集団にとけこんでいる
・学校(勤務先)が楽しいと感じている
もちろんこれらが当てはまったからといって、必ずしも“依存”に陥るというわけではない。しかし、この結果から「学校や勤務先などで友人をつくり、ネットやゲーム以外にも交流の機会をもつこと」が、予防策として浮かび上がったという。
●スマホの手軽さとゲームのギャンブル性が依存の引き金に
スマホのゲームに依存する事例でよく取り上げられるのが、抽選で何らかの特典を得られる“ガチャ”を始めとした課金システムだ。現行のゲームの多くについて、初めは「基本無料」をうたっていながらも「もっと楽しむためには時間やお金を使う必要がある」と指摘する本書は、この仕組み自体が「利用時間や利用頻度、利用額がふえやすい」原因だとしている。
さらに、その根底にあるキーワードとして浮かび上がるのがスマホのゲームが持つ手軽さとギャンブル性である。
スマホはそもそも、連絡手段として身近に置いているケースも多い。そこへゲームの運営会社から通知が来るなどして、仕事や勉強の合間などでゲームをプレイするという「ながらプレイ」の習慣が付いてしまうと、いつもゲームの進捗が気になって仕方ないという状況に陥りやすいのだという。
さらに、ガチャなどにみられるギャンブル性も依存の原因になりやすく、射幸心を刺激されることで、ゲームから離れられなくなる場合もあるそうだ。
●依存克服の第一歩 行動を記録する方法「モニタリング」
ネット依存やゲーム依存に陥ってしまった場合、克服のためには本人だけではなく家族の協力も必要になる。本書では、そのための方法をいくつか提案しているが、実際の治療では「モニタリング」という方法が使われることもあるという。
これはシンプルに、自分の1日の行動記録を付けるというもの。起床や就寝、ゲームをしていた時間帯などを記録するほか、例えば、「だるい」「なんとなく」などその時ごとの体調や理由を簡単でもよいので書き込んでおく。ただし、パソコンやスマホを使ってしまうとネットやゲームにふれてしまう可能性があるため、紙に書き留めるようにする。
ある程度の期間は記録し続け、振り返ってみると自分の生活習慣の乱れやネット・ゲームに没頭する様子が、客観的に浮かび上がるというわけだ。
腹八分目とはよくいわれるが、なにごともやり過ぎは禁物。本書は、何かとスマホに頼りがちな現代に生きる私たちに、一石を投じてくれる一冊である。
文=カネコシュウヘイ





