平成は「まだら」な時代だった――小泉政権下で大臣を歴任した竹中平蔵が語る時代の軌跡と教訓
公開日:2019/3/14
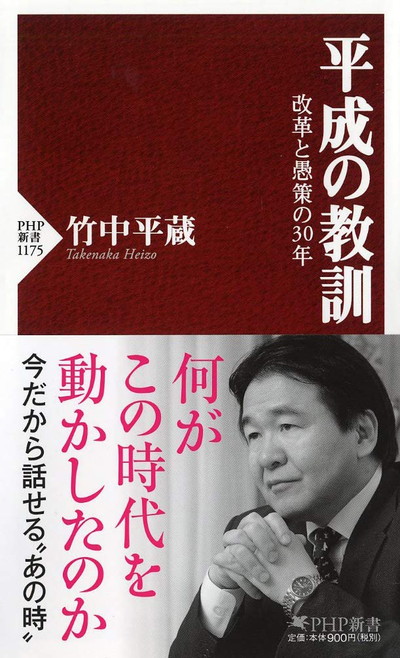
平成はどんな時代だったのか。この時代に何が起きたのか。私たちの歩んだ軌跡を検証することが、次の時代を正しい方向へまっすぐ進む道しるべになる。
『平成の教訓』(竹中平蔵/PHP研究所)では、小泉政権で大臣を歴任した竹中平蔵氏が平成30年間を振り返り、この時代から得られる教訓を考察している。
■平成は「まだら」な時代だった
「失われた30年」という表現があるように、「平成は失敗の時代だった」と総括する経済学者や専門家がいる。しかし竹中氏はこれを「不適切」と指摘。「平成は“まだら”な時代」だというのだ。本書より30年間を振り返ってみたい。
平成は1989年から始まった。このとき日本はバブル絶頂期に入って誰もが浮かれていた。しかし2年と経たずにバブルが崩壊して株価と地価が暴落。企業が次々に倒産した。その後、97年から01年まで、本格的な金融危機が訪れる。
そして01年に小泉政権が誕生し、不良債権処理を断行。郵政・道路公団民営化をはじめとする構造改革を行う。2003年4月末に記録した日経平均株価7600円は、2007年12月末には15000円と倍増。景気が回復し、格差が是正され、貧困化も改善された。竹中氏は、自身も経済財政政策担当大臣として活躍したこの時期を「改革」と表現している。
しかし民主党政権時代、2011年には東日本大震災も経験し、日本は再び低迷。2012年末から発足した第2次安倍政権のアベノミクスによって経済が上向きになる兆しが見えるも、改革の取り組みはまだ半ばにあり、これからが正念場だ。
このように平成はバブル絶頂期から崩壊を経験し、その後も浮き沈みを繰り返してきた。「失われた30年」ではなく「まだらな30年」と表現するのが適切ではないか。竹中氏はそう考察している。
■これからの時代は強いリーダーが必要だ
平成時代になって日本の力強い成長が失われてしまった。これにはいくつか要因がある。竹中氏は本書で「日本が世界に大きく遅れをとったのは、物価と人口が失われたから」と断言している。
中国は大きく人口増加し、アメリカは移民を受け入れ続けた。とくに移民はおおむね若く、海を渡って人生を切り開こうと考える「前向きで意欲的な人々」が多い。彼らが戦後日本の「高度経済成長」のような役割を果たすのだ。「デフレの放置」と「外国人受け入れへの消極的な姿勢」の2つが、平成時代の日本経済の姿を決定づけ、先進各国との圧倒的な立場の違いを生み出した。
しかし失ったものばかりに目を向けても仕方ない。平成を経験したからこそ得られた教訓を糧に、これからの時代を生きていくべきだ。本書の最終章では「平成が示す、未来への教訓」と題し、竹中氏の考える教訓と提案が語られている。
その1つが、国と企業が「官民パートナーシップ」を組んで時代を切り開いていくことだ。中国・アリババが政府と手を組んで巨大なビッグデータを集めて大成功しているように、日本も「政府の果たす役割」を見出さなければならない。
昔ながらの癒着構造の中でゾンビ企業を救済する「JAL問題」のような「官民一体」ではなく、関西空港が民営化して黒字化を実現したように、「民間にまかせる」ことが大事だ。そうして運用収入を得て、政府は次の政策を展開していけばいい。
そしてなにより強い政治リーダーが必要だ。これからの時代は極端な人口減少が起きる。だからこそ国民に「失われることを受け入れて喪失ダメージを小さくする」縮小戦略を明るく語り、議会とバトルして構造改革を行う強い意志を持つリーダーが必要だ。
竹中氏は本書で、平成30年間の良い面と悪い面を詳細に検証している。さらに政策面での改革と愚策も取り上げ、今後の日本に提言を行う。小泉政権下で大臣を歴任した竹中氏だからこそ語れる内容が本書にある。
文=いのうえゆきひろ





