即効性バツグン! ミスなく仕事が10倍速くなる「5分間逆算仕事術」
公開日:2020/1/7
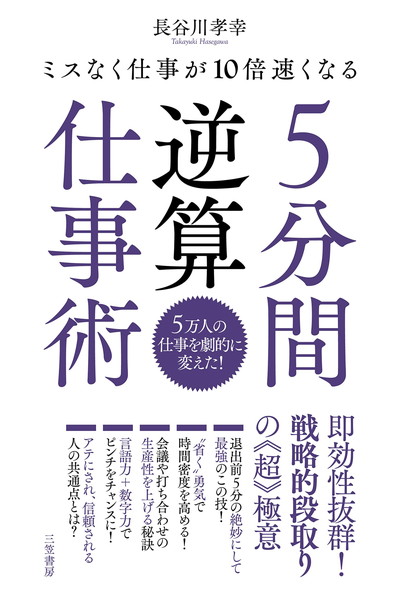
2019年11月、大阪府の吉村洋文知事が、事前申請せず職員が残業した場合、午後6時半にパソコンを強制終了するシステムを導入すると発表。長時間労働抑制の一環として大きな話題になった。
働き方改革で残業が奨励されない昨今、いかに効率よく目の前の業務をこなすか「生産性」が問われる。『ミスなく仕事が10倍速くなる 5分間逆算仕事術』(長谷川孝幸/三笠書房)で紹介されるアドバイスは、その一助となるだろう。本書のポイントはコレだ。
段取りよく仕事をこなす人とそうでない人、その差はゴールからしっかり逆算して考えることができているかどうかにあります。
本書より即効性抜群の「ミスなく仕事が10倍速くなる」テクニックを少しだけご紹介したい。
■翌日の業務の段取りを「前日の退勤5分前」で組もう
どれだけ仕事が忙しい人であっても、わずか5分間を用意できない人はそうそういない。もし「仕事の効率が悪いな~…」と悩んでいるならば、「退勤前の5分間」を活用してみよう。
段取りよく仕事を進めたいならば、1日単位で自分がどのように業務をこなしたいか想定しておくべきだ。しかしその想定を「その日」にやってしまうと遅すぎる。
「前日の退勤5分前」に、翌日の自分はどんな業務をどれだけこなしたいのか、“ゴールから逆算して”ざっくりと計画を立てよう。すると翌日は出勤時からすぐに業務に取りかかれる上に、想定外の業務が発生しても「今日はこれくらいの仕事量だから、ここを調整すればなんとかなる」と対処も見える。
ここで大事なのは、5分以上を費やしてはいけないこと。要領が悪い人の中には、「時間をかければよいものができる」と考える人がいる。しかし段取りを組む作業に数十分を費やしては本末転倒だ。どれだけ完璧なスケジュールを立てようが、翌日に突発的な案件が入れば木っ端微塵に崩れてしまう。
きっかり「前日の退勤5分前」で翌日の段取りを組むことが「ミスなく仕事が10倍速くなる」最も基本的で重要なポイントだ。
■仕事の効率化で欠かせない「標準作業時間」
たとえ要領よく段取りを組めても「標準作業時間」を計り間違えていたら、仕事の効率は悪いままだ。
標準作業時間とは、もともと製造業で使われていた言葉で、「それを行う最も適切な時間」もしくは「あるべき姿を実現するためのあるべき時間」という意味を持つ。
事務作業にも営業回りにも、仕事のあらゆる行為には必ず標準作業時間が存在し、それを守ることで仕事の効率化が実現する。翌日の業務をずらっと並べたとき、標準作業時間を度外視して仕事を詰め込んだら本末転倒だ。しかし「1枚の企画書を作るのに6時間かかる」と想定しても本末転倒だ。
まずは自身が抱える業務をすべて洗い出し、それらの標準作業時間を正確に見極めることも、仕事の効率化を図る大事なポイントである。
■「品質」「コスト」「安定度」を成立させよう
本書では標準作業時間の正しい見極め方を詳細に解説している。“仮の標準作業時間”を見極めるまでは簡単だ。ある業務を、ストップウォッチで計測しながらこなしてみよう。何回か計測を繰り返すと、仮の標準作業時間が見えてくる。
仮の標準作業時間が見えた後は、それが正しいか、一定期間を定めて検証してみよう。設定した時間が多めに余るようならば、設定が甘い。ちょうど設定した時間内にぴったりと終わることが標準作業時間のキモだ。
そして時間を検証し終わった後は、アウトプットの検証だ。ここが最も大事である。いくら時間内に業務が終わろうと、「帳簿がズタズタだ」「商品説明のときに言うべき言葉を言っていない」など、アウトプットが成立していなければ大失敗だ。真の標準作業時間とは、ある業務の「品質」「コスト」「安定度」を成立させた上で、その時間内にぴったりと終わること。
もし仕事を効率化できなくて残業ばかりしているならば、ぜひ「前日の退勤5分前」と「標準作業時間」を活用してほしい。とても基本的なように見えて、本気で実践すれば劇的に変わるはずである。
かつて「一生安泰」のシンボルだった大企業から次々とリストラが発表されている。キリン、日産、富士通など、業績の好不調に関係なく、主に40代以上の熟年サラリーマンが対象のようだ。
大企業にどのような思惑があるかはさておき、いずれにせよ「退勤までに質の良い業務を効率よくこなして帰る人材」ならば、リストラ対象に入っていないことは間違いない。
時代のトレンドは「仕事の効率化」である。もしそれができなくて困っているならば、ぜひ本書を読んでサラリーマン人生の一助にしてほしい。
文=いのうえゆきひろ





