なぜ呼吸器を扱うために多くの人手が必要なの? 肺の仕組みを知ればナットク! “最強”に面白い人体の不思議
更新日:2020/4/5
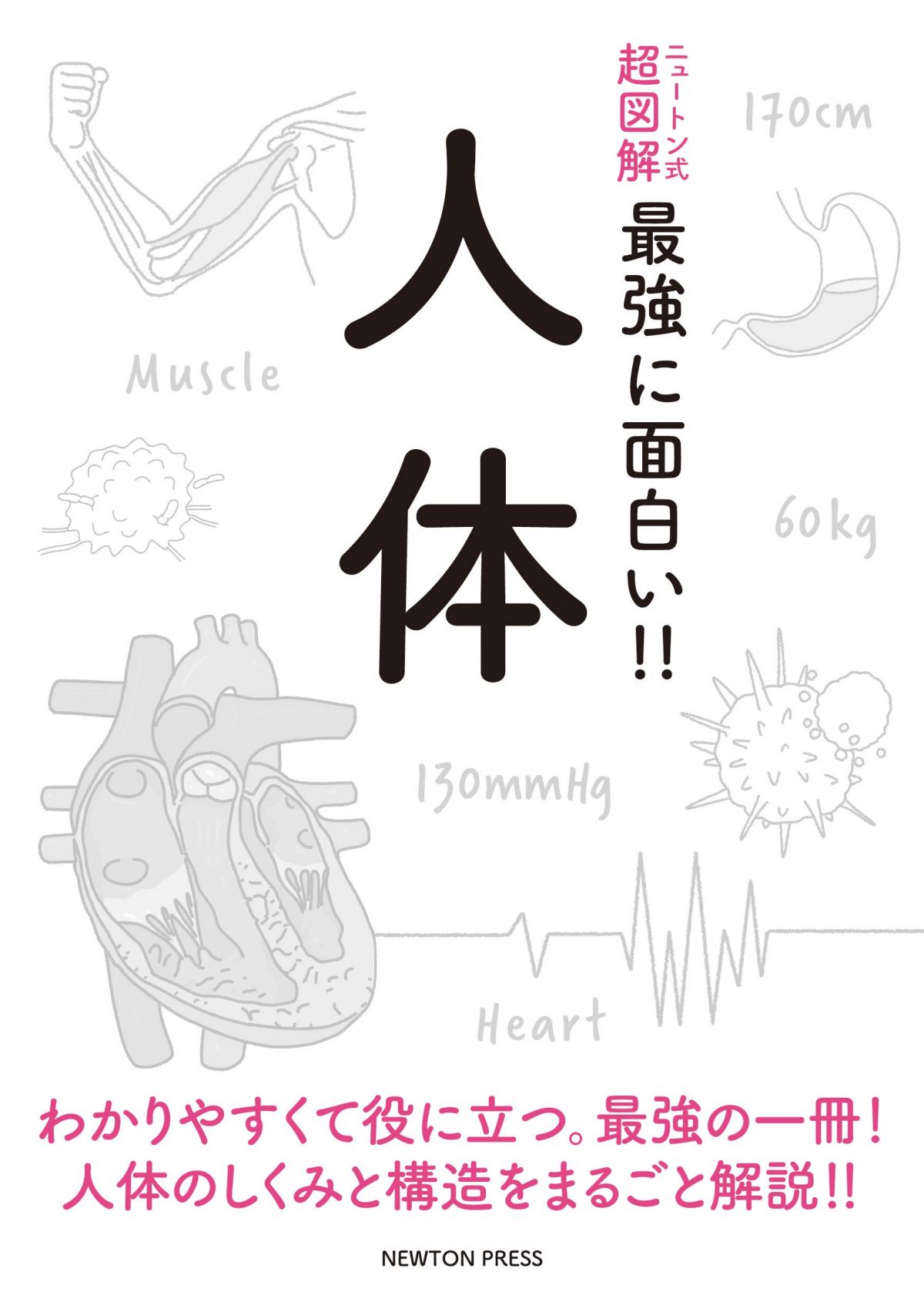
新型コロナウイルス禍は、この原稿執筆時点でなお終息の兆しが見えない。人間というものは、分からないことを分からないままにしておくことにストレスを感じる生き物ゆえ、不安感だけが先行して、物量自体は心配のいらない紙類の買い占めが未だに続いている有り様。さらに、3月19日に公表された「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」の提言から、「地域における現有の人工呼吸器の数を超えてしまうことが想定される」と報道されれば、SNSでは「人工呼吸器が足りないなら量産すればいい」などという言説が流布してしまうくらいだ。それはひとえに、人体の仕組みを理解していないことから生じる誤解だろう。こんな時には、なんとなく知っているつもりでいるより『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 人体』(橋本尚詞:監修/ニュートンプレス)で学ぶのが良いのではないか。
本書の特徴は、人体の仕組みを「消化」や「呼吸」といった一連の流れに沿って解説している点。今回は特に、新型コロナウイルスによって発症するとされている肺炎に注目してみようと思う。
肺を、「空気の出入りによってのびちぢみする、風船のような器官」と考える人は多い。確かにそのとおりではあるのだが、もちろん肺だけがぷくぷくと動いているわけではない。息を吸うときには、肺の下部にある筋肉の横隔膜が縮むのと、胸部の肋骨を動かす筋肉が縮んで肋骨が引き上げられ胸腔という部分が前上方向に広がることで肺は膨らむ。よく「お腹で息を吸って・胸で息を吸って」と言われるが、それももちろん同じ肺で、動かす筋肉が違うのだ。いわゆる「腹式呼吸」は横隔膜を動かすことによる安静時の呼吸なのに対して、運動などで多くの呼吸が必要な場合に肋骨の周囲の筋肉を動かすのが「胸式呼吸」となる。
鼻や口から吸い込まれた空気の通り道となる「気管」は、肺の中に入った先で分岐を繰り返してすみずみに広がり、その末端は「肺胞」と呼ばれる「ぶどうの房のような構造」になっていて、ここに空気が入ると風船のように膨らむ。つまり、肺は一つの風船のようにはなっておらず、小さな風船の集合体なのだ。この肺胞で、酸素と二酸化炭素のガス交換が行なわれ、肺胞の表面積は両肺合わせて100~140平方メートル(テニスコート約半面分)になるというから、コンパクトに収納している人体の凄さに驚かされる。
そして、肺炎を起こし正常に機能しない肺に人工呼吸器で空気を送り込むということは、動いていない周囲の筋肉に圧迫された状態で小さな風船の集合体のような肺胞に負荷をかけ損傷させるリスクの高い処置であり、機械だけ増やしても監視する人員を配置しなければ適切に運用するのが難しい。
かように肺炎は怖い症状であるから、喉の痛みや鼻水といった風邪のような症状が現れるだけでも心配になるかもしれないが、血液の章では「免疫細胞たちが体に侵入した病原体に徹底抗戦をしかけている証です」と、外敵から体を守る仕組みが解説されている。
哺乳類の免疫システムは二つあり、一つは生まれたときから自然に備わっている「自然免疫」と呼ばれるもので、もう一つが「獲得免疫」といって、一度攻撃したことのある病原体の情報を細胞が記憶しておくことにより、同じ病原体の次の襲撃に備える。だからといって、そのために自ら感染しやすい場所に出向くなどというのは愚かな行為なれど、厚生労働省のサイトに掲載されている一般向けのQ&A(3月23日時点版)でも、患者の多くは治癒して重篤化するのは20%未満というデータが示されているので、過度に恐れるのはストレスとなって体に良くない。
ストレスがかかると「交感神経」と「副交感神経」という、二つの対照的な働きを持つ神経からなる「自律神経」の機能が乱れるからだ。特に交感神経はストレスを感じると活発になり、心拍数と呼吸を増やす一方で消化管などの働きを抑えたり血管を収縮させて血液量を減らしたりしてしまい、体への負担となる。
ただし本書によれば、交感神経の反応は「ストレスが去るとすばやく元の状態にもどります」とのこと。私としては、テレビやネットなどで新型コロナウイルスに関連した刺激的な情報に触れてストレスを高めるよりも、小宇宙や化学工場にたとえられるほど神秘的で不思議な人体の仕組みを解説してくれる本書を読むほうをお勧めしたい。その面白さに、きっと驚くことと思う。おっと、興奮すると体にはストレスになるから、交感神経が活発になったと感じたときには深呼吸してみるのが良いだろう。
文=清水銀嶺





