「添加物は身体に悪い」はデマだった? 食の健康にまつわる嘘と真実
公開日:2020/5/31
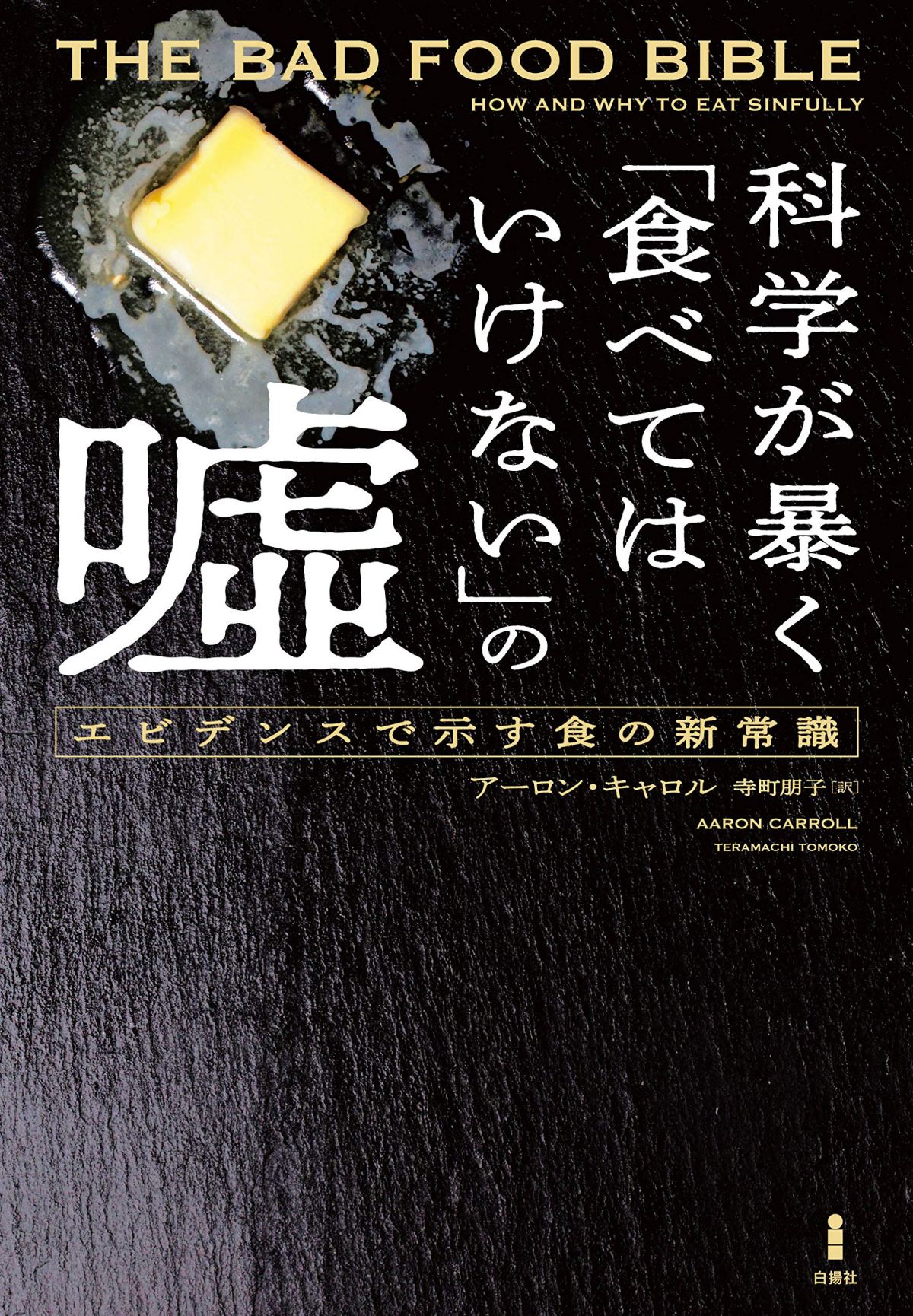
2015年、世界保健機関WHOの外部組織である国際がん研究機関(IARC)はベーコン、ソーセージ、ハムなどの加工肉に発がん性があると発表し、世界中で物議を醸しました。同組織は1971年以来、1000を超える薬剤の評価を公表していますが、「発がん性がない」としている物質は一つしかないのだといいます。それはカプロラクタム、食品とはまったく無関係なナイロンの原料です。
『科学が暴く「食べてはいけない」の嘘』(アーロン・キャロル:著、寺町朋子:訳/白揚社)は、現代で「身体に悪い」とされている食品について最新研究から科学的根拠を検証しています。みなさんも「バターは身体に悪い」、「塩分の取り過ぎは悪い」、「卵は一日一個まで」、「添加物は身体に悪い」など、健康にまつわる噂を聞いたことがあるのではないでしょうか。
そうした研究や噂の出所を明らかにする本書からは、実は科学的根拠の薄いデータや偏見によるイメージから、一方的に悪者にされてしまった食の真実が見えてきます。
例えば、最近よく聞く「グルテンフリー」をうたった食品。これはもともと小麦アレルギーやセリアック病といった小麦のグルテンを受け付けない体質の患者のための療養食です。健康ブームでメディアに取り上げられ、メーカー各社が新製品を売り出し、いまではスーパーやコンビニなどでも流通している食品ですが、本書によれば美容やダイエットへの効果は科学的に証明されていないといいます。ダイエットの点では、2006年に行われた健康調査では、グルテンフリーを常食するセリアック病患者の約81%でむしろ体重増加がみられたのだとか。
消費者に誤解を生み出した例としては他にもあり、「コーヒーは子どもの発達を妨げる」という話です。事の発端は1910年代にアメリカで販売された穀物由来の代用コーヒー「ポスタム」の誌面広告で、「コーヒーを飲んでいた子どもは、飲まない子どもよりも成績が悪い」などの研究結果を挙げ「ポスタム」を飲むように促すものでした。広告主のC・W・ポストは、自らが考案した「ポスタム」で莫大な利益を得ます。ところが、この結果を裏付ける研究データや論文は現在に至るまで発見されていないというのです。いまではポストの仕掛けたマーケティング戦略だったとされています。
一度、根付いた悪評を消すのは簡単ではありません。いまもアメリカで偏見に晒されているのが、日本人にはお馴染みのうま味調味料です。うま味調味料はグルタミン酸ナトリウム(MSG)という化学物質ですが、自然界にも存在するもので生物の活動にかかせません。それが悪者となったのは、1968年のアメリカで中華料理店にて食事した客が手足のしびれ、体調不良を訴える騒動が起きたことでした。「中華料理店症候群」と名付けられ、確たる科学分析や原因究明がなされないまま、料理の多くで使われていたうま味調味料が原因と結論づけられてしまったのです。
自分に身近なものが健康に悪いという、ショッキングな噂ほど人の興味や恐怖心を煽ります。しかし一方的な主張のみを鵜呑みにすると、かえって大切な家族の健康を損なうおそれれがあります。ネットやSNSでフェイクニュースが溢れる昨今、真実を見分ける判断力を磨きたいものです。
文=愛咲優詩





