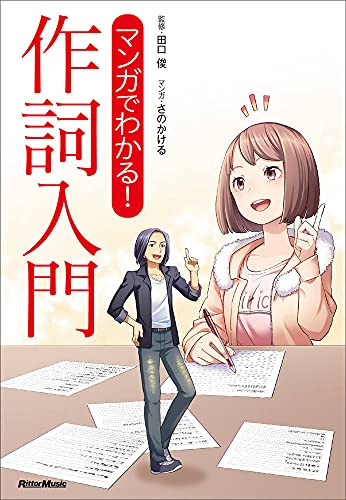歌詞を作るなら“サビ”から!? 初めて作詞に挑戦する人にオススメのコミック入門書
公開日:2021/3/14
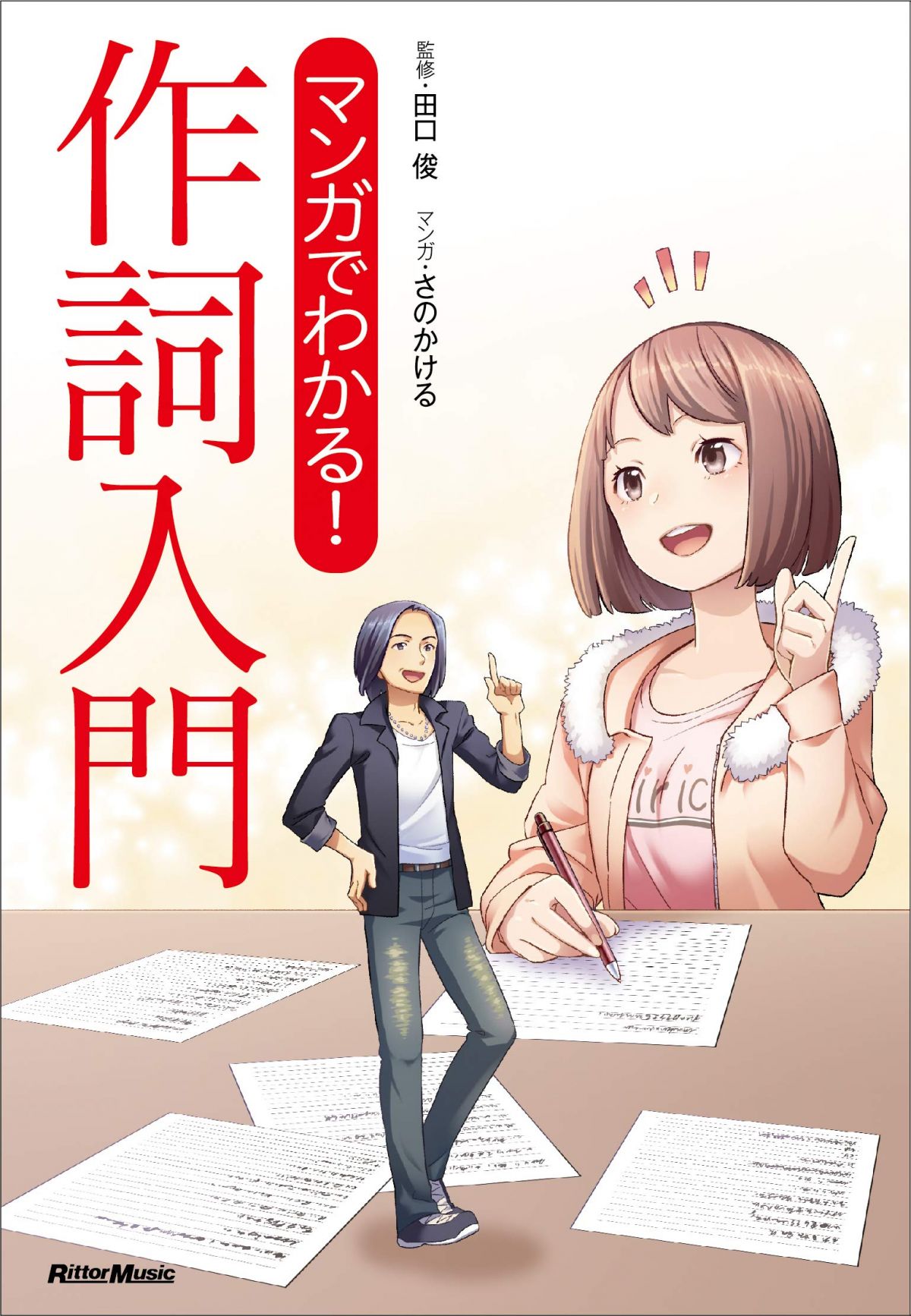
最近「うっせぇわ」という歌を頻繁に耳にするようになった。もちろんそれが流行っているからだが、その理由のひとつはやはりあの印象的な「歌詞」にあるのだろう。この歌に限らず、ヒット曲というものには大体、リスナーの印象に残るフレーズが存在することが多い。しかし口でいうのは簡単だが、例えば単に不平不満を並べたてるだけではヒットする歌詞にはならないだろう。そう、やはり作詞にもある種の「基礎知識」は必要なのである。『マンガでわかる! 作詞入門』(田口俊:監修、さのかける:イラスト/リットーミュージック)は、とあるガールズバンドの曲作りを通じて、作詞の基礎を漫画で分かりやすく学ぶことができる。
本書の主人公・松原琴美はバンドでギター兼ボーカルを担当しているが、今度の学園祭で新曲を作ることになった。しかし作詞経験のない琴美は、馴染みの喫茶店の常連である「先生」に作詞を教わることに。先生の指導にはいくつもの要点があるのだが、特に気になった部分を紹介していこう。
詞はサビから作り始める
歌詞に限らず、人は文章を書くとき最初から書こうとする人が多いだろう。もちろん間違いではない。しかし先生は友人の作曲家たちに「曲のどの部分から作っているか?」と尋ねたところ、ほとんどが「サビの部分から」だと答えたのだという。曲に乗せる言葉ということを意識するなら、やはり歌詞も「音楽的」な作りかたをしたほうがよいのである。
ちなみに本書では曲を「Aメロ」「Bメロ」「サビ」のブロックに分けて解説している。「サビ」とは曲が一番盛り上がる部分であり、エモーショナルかつシンプルな言葉を使うべきだという。そして「Aメロ」にはサビの感情に至った出来事を、「Bメロ」にはサビやAメロとは違う時間軸(過去や未来など)の話を入れるのだ。本書においてはサビ、Aメロ、Bメロの順に作ることがオススメだとしている。
詞は誰の視点で書く?
多分、どのようなジャンルにおいても「ターゲット層」を想定することは必要であろう。作詞の場合は「誰に聞いてもらいたいか」であり、それによって内容や言葉のチョイスも変わってくるはず。本書で琴美たちは「お世話になった先輩たち」のための曲作りを選択。このことによって、先輩たちの曲の好みなどを考えるといった方向性が見えてくるのだ。
そして詞を書く上では「作詞モードはやめよう」と指摘。作詞モードとは、キザっぽくなったりロマンチックな言葉を使いがちになったりすることだ。もちろん曲の方向性によってはアリなのだが、近年の傾向としてはそういう方向よりも話し言葉のようなリアルなフレーズが求められているという。確かに、最近の流行歌を聴くとその傾向はあるかもしれない。
作中で先生も語っているが、「作詞のやりかたは1つだけじゃない、人それぞれ」である。しかし右も左も分からない初心者にとっては、ある程度の指針があったほうが進みやすいのも事実だ。そういう意味では、本書で紹介されている手法は非常に理解しやすく、漫画・テキスト併用なのも読みやすいのでありがたい。もしもこの先、何かの機会で作詞に挑戦することがあったとき、本書は心強いアドバイザーとなってくれるに違いない。
文=木谷誠