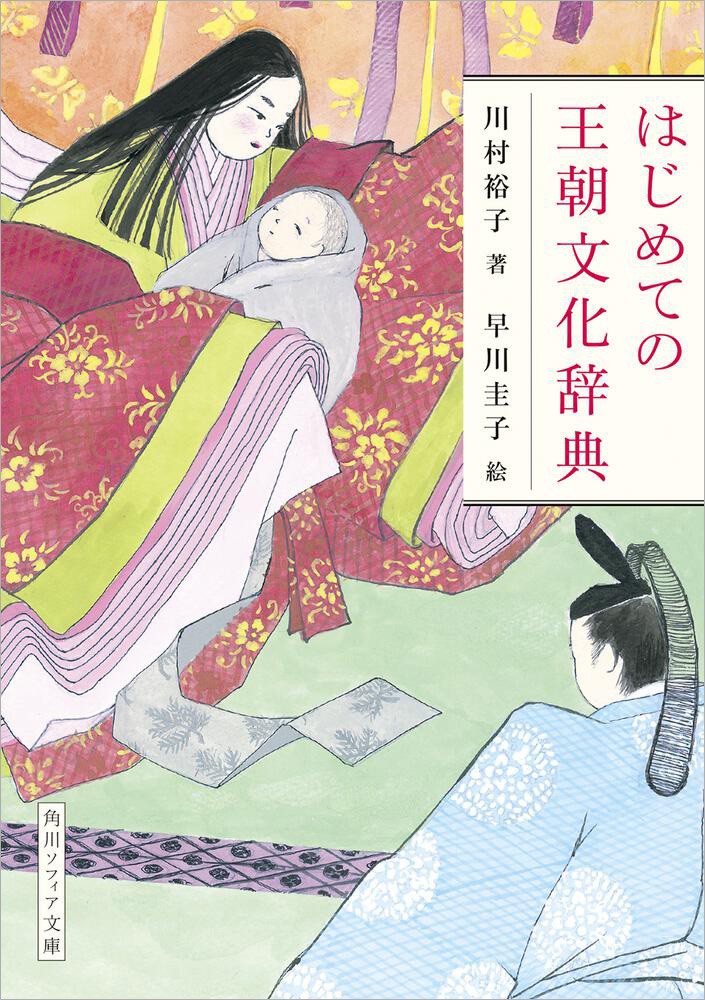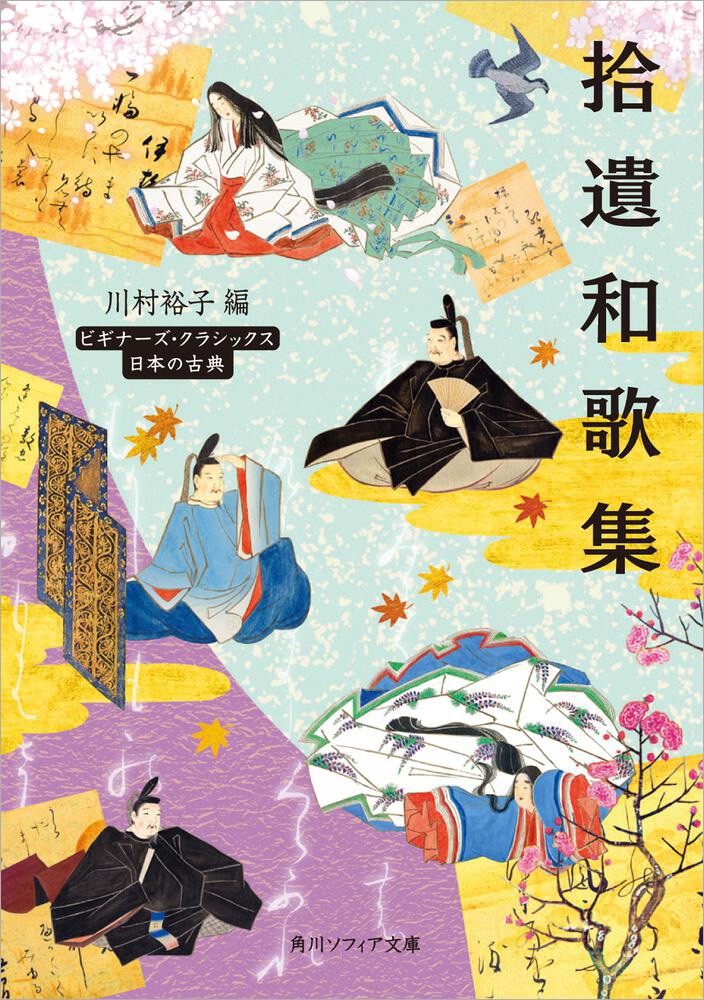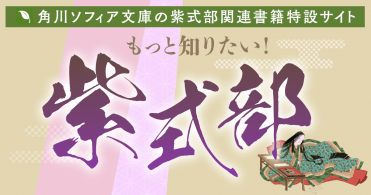第八回 藤原詮子(道長の姉)【大河ドラマを100倍楽しむ 王朝辞典 】
公開日:2024/5/12
第八回 藤原詮子 (道長の姉)【大河ドラマを100倍楽しむ 王朝辞典 】
藤原詮子は道長の姉。
詮子は、九九一年(
さて、この詮子についてあまり知られていないのですが、小さいころの話が『蜻蛉日記』に残ってます。女子の出産をあきらめた道綱母は養女を引き取ります。その養女と一緒に
養女も詮子も后がね。天皇の子どもを産めば国母ですね。ただし詮子は円融天皇の女御となったのですが、養女は詮子の女房(
兼家は詮子に期待していたのですが、
遵子の弟だった
実際、公任は詮子関係で歌を残しているんです。有名なのは、詮子の四十賀の時の次の歌。
君が世に今幾度かかくしつつうれしき事にあはんとすらん
(あなたの世に、これからいったい何度、こんなうれしい事に会うことでしょう。めでたいことです)(『拾遺和歌集』「雑賀」一一七四)
これは詮子の弟・道長が主催した詮子の四十歳の誕生日パーティーです。一〇〇一年十月九日のことでした。その祝宴で公任は歌を詠んだのですね。公任はこのような場や折を踏まえて歌を詠むのがすごく上手でした。この歌も祝意の歌としては最高ですよね。なお、この時には紫式部の父・為時の方は屏風歌を詠んでいます。
また同じ『拾遺和歌集』には詮子の四十九日以内に詠まれた公任の歌もあるのですすよ(「雑賀」一〇二二)。
確かに兼家の立場からすると、詮子には、いちはやく立后して貰いたかったのでしょう。ただし、円融天皇自身と詮子がそれほど仲が悪いかどうかは、わからない。ライバル
またあまり知られてはいませんが、詮子は
ある時、道綱が
かばかりもとひやはしつるほととぎす花橘のえにこそありけれ
(今まではこの程度のおたよりもいただけなかったのに、ほととぎすが花橘に縁があるように、これも昔の人の縁(時姫)だったのですね)(『蜻蛉日記巻末歌集』)
と詠みました。それに対して道綱は
橘のなりものぼらぬみを知れば下枝ならではとはぬとぞ聞く
(橘の実のように上にならない身を知ると、ほととぎすが下枝を飛び回るように、私も下々の者とつきあっておりました。そんなわけで、あなたのような高貴な方に手紙をさし上げられなくて……)
と返します。道綱の歌は自分の立場を卑下して、少し意味深。道綱から見ると詮子は天皇の妻ですから、高貴であることは間違いないのですが……。
さて、花橘を贈るところから始まる有名な作品。それは『和泉式部日記』です。
この詮子の歌は当然詮子没以前なので一〇〇一年以前となるでしょうか。そして『和泉式部日記』の成立はだいたい一〇〇八年。だから、この詮子・道綱による橘のお話は『和泉式部日記』に影響を与えたのかもしれませんね。
プロフィール
1956年東京都生まれ。新潟産業大学名誉教授。活水女子大学、新潟産業大学、武蔵野大学を経て現職。立教大学大学院文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程修了。博士(文学)。著書に『はじめての王朝文化辞典』(早川圭子絵、角川ソフィア文庫)、『装いの王朝文化』(角川選書)、『平安女子の楽しい!生活』『平安男子の元気な!生活』『平安のステキな!女性作家たち』(以上岩波ジュニア新書)、編著書に『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 更級日記』『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 拾遺和歌集』(ともに角川ソフィア文庫)など多数。
作品紹介
王朝の文化や作品をもっと知りたい方にはこちらがおすすめ!
『はじめての王朝文化辞典』
著者:川村裕子 絵:早川圭子
https://www.kadokawa.co.jp/product/321611000839/
『源氏物語』や『枕草子』に登場する平安時代の貴族たちは、どのような生活をしていたのか?物語に描かれる御簾や直衣、烏帽子などの「物」は、言葉をしゃべるわけではないけれど、ときに人よりも饒舌に人間関係や状況を表現することがある。家、調度品、服装、儀式、季節の行事、食事や音楽、娯楽、スポーツ、病気、信仰や風習ほか。美しい挿絵と、読者に語り掛ける丁寧な解説によって、古典文学の世界が鮮やかによみがえる読む辞典。
『ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 拾遺和歌集』
編:川村裕子
https://www.kadokawa.co.jp/product/322303001978/
『源氏物語』と同時期に成立した勅撰和歌集。和歌の基礎や王朝文化も解説! 「拾遺和歌集」は、きらびやかな貴族の文化が最盛期を迎えた平安時代、11世紀初頭。花山院の勅令によって編まれたとされる三番目の勅撰和歌集。和歌の技法や歴史背景を解説するコラムも充実の、もっともやさしい入門書。
角川ソフィア文庫の紫式部関連書籍特設サイト
https://kadobun.jp/special/gakugei/murasakishikibu.html