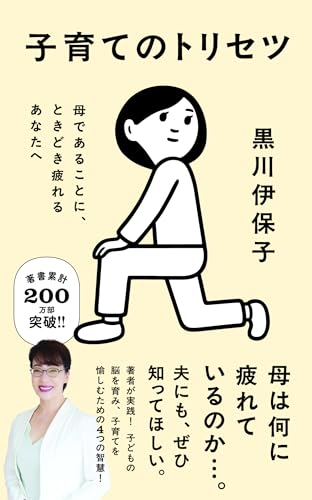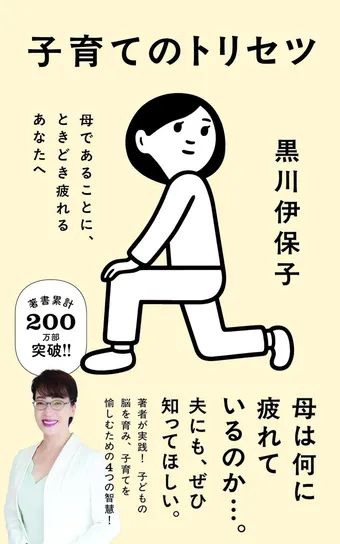人の悪意を知るのは13歳以降でいい。子どもに猜疑心を抱かせないために必要なこと/子育てのトリセツ
更新日:2025/3/14
悪意を知るのは13歳以降でいい
自分が陰口をきかないだけではなく、子どもが、他人の悪意のあることばにさらされたときも、愛のことばに言い換えて、子どもを守ろう。
私は、息子に対する学校の先生のことばに悪意を感じたことがあった。息子は先生運のいい子で、素敵な先生に次々に出会い、心に残ることばをいくつももらって大きくなってきた。とはいえ、稀に悪意のある言葉に出会うこともある。先生も人間だから、好き嫌いがあるのだろう。
そんなときでも、私は、彼が子ども脳のうち(12歳まで)は、先生の悪口を言わなかった。「先生は、あなたに期待してるのね。身体が大きいし、思考力があるから、ついおとな相手のような気持ちになっちゃうんだわ。できる男は、つらいわね」というふうに、ポジティブな解釈に変えたりして。
「この世に悪意がある」なんてことは、おとな脳になってから気づけばいい。とっさに使う感性の領域を養う子ども脳時代には、無邪気でいられたほうが絶対に得だ、と思ったからだった。
大人になった息子は、異国の人たちともおおらかに触れ合うし、年長のVIP相手に臆することがないし、大舞台にも緊張することがない。これはなかなかのアドバンテージである。行動範囲と人脈がとても広いので、親の私もびっくりしてしまうくらいだ。
おとな脳への移行期には、悪意の存在を認める
10代の前半は、分別や社会性を担保する脳の部位、前頭前野の発達期に当たる。この時期は、「そうはいっても」という思考展開を手に入れていく。この世の不条理を知り、それでも乗り越えていくタフさを身に付けて行くときだ。
この時期には、社会の悪意にも触れる必要がある。これから、親の手を離れて、過酷な現実の世の中を生きていくために。
中学の3か年は、戦争や殺人や理不尽な挫折など、この世の不条理に触れた小説(純文学だけでなくミステリーやファンタジーも含む)を読むべきだ。自分が日常触れるレベルを遥かに超えた悪意の存在を、まずは客観で知ってほしい。自分に起こることとして、主観で知る前に。実際の悪意に触れたときの、守りになるから。
13歳を過ぎたら、親も子の前で、人には悪意もあることを認めてもいいと私は思う。「たしかに、その発言には悪意があるね。あなたは、そんな言い分を真に受けなくていい。傷つく必要もない。その発言の目的は、あなたの気持ちを萎えさせることなんだから」と一刀両断にしてもいい。その相手の品性の低さをなじってもいい。
悪意を認めなければ、悪意にどう対処していくかを、子どもと共に考えることはできない。
この期に及んで、この世に悪意がないかのように振る舞ったり(「相手にも言い分があるのよ」)、小言にすり替えたり(「あんたも人にそんなことをしないように気をつけなさい」)する親は、本人は知的に振る舞ったように思っているのかもしれないが、これ以降、尊敬されることがない。
<第4回に続く>