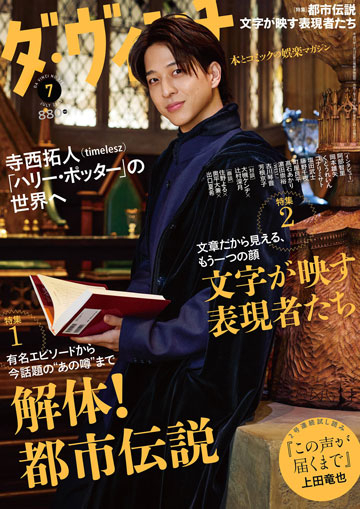幼少期の脳にはオノマトペ絵本がおすすめ! 読書が好きな子どもに育てる方法/子育てのトリセツ
公開日:2025/3/15
子育ては思い通りにいかないことの連続で、心身ともにいっぱいいっぱいになってしまうこともありますよね。
そんな時に手にとってほしい、人口知能や脳科学の専門家で、生き方の指南書が好評の黒川伊保子氏による子育て本『子育てのトリセツ 母であることに、ときどき疲れるあなたへ』をご紹介します。
失敗を怒らない、対等に付き合う…黒川氏自らが子育てで実践し、脳科学の裏づけをもとにした目からウロコの子育て法。妊娠中の人、思春期の子どもがいる人、子離れ中の人…子育てのあらゆる段階に役立ち、「一般的」とされている育児の常識を、最新の脳科学と自身の実体験で覆します。
※本記事は書籍『子育てのトリセツ 母であることに、ときどき疲れるあなたへ』(黒川伊保子/ポプラ社)から一部抜粋・編集しました
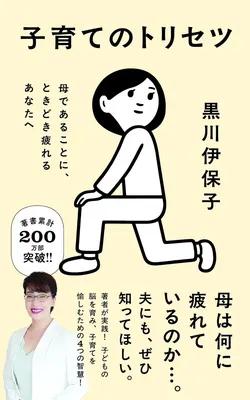
母であることに、ときどき疲れるあなたへ』
(黒川伊保子/ポプラ社)
読書好きへの道は、絵本の読み聞かせから
読書好きへの道は、絵本の読み聞かせから始まる。
本を読むのは、本来は、億劫な動作なのである。読書好きといえども、ときによっては、最初の何ページかは気分が乗らず、我慢して読み進めることもある。ページを繰りながら文字を追い、意味を解析する面倒くささ……あれが、読書という動作の正体だ。しかし、本が誘ってくれる想像世界の面白さを知っているから、読書家はページを進める。
子どもを読書家にするには、本が楽しい世界を開いてくれることを、脳に刷り込む必要がある。それが素直にできるのが、幼少期の絵本との出会いなのである。
絵本にうまく出会わせておけば、自然にファンタジーに移行して、やがて読書家の大人になってくれる。合理的だ。
幼児期の脳にいいオノマトペ絵本
絵本との出会いに、早すぎることはない。0歳から始めてほしい。ただし、2歳半までの脳が、とっさに視覚認知できるのはシンプルなかたち。文脈理解もまだできないので、シンプルなイラストと、添えられたことばの発音を単純に楽しめる絵本がいい。
たとえば、こっちに向かって歩いてくるとぼけた犬の画に、「ずんずん」なんていう擬態語がついていたら、1歳児は、いつまでも笑ってくれる。オノマトペ(擬音語・擬態語)は、子どもたちの脳を刺激する。発音体感と、そのことばが指し示すところのイメージが一致するからである。
たとえば、ずんずんは、舌を前歯からはみ出すくらいに硬く尖らせ振動させる「ず」と、弾ませる「ん」の組合せ。突き進み(ず)、跳ね(ん)、突き進み(ず)、跳ねる(ん)。何かが、容赦なく突き進んでくる感じが、口元に起こるのだ。その発音体感と、とぼけた犬の鼻先が迫ってくる感じが妙に合っているので、脳の身体制御の領域(発音を司る場所)と、視覚認知の領域が反応し合って、子どもたちは興奮するのである。
ちなみに、我が家の息子のこの時期のお気に入りの絵本は、丸だけが並んだ絵本だった。「まるまる、おおまる」という文字だけのページをめくると、大きな丸が現れる。「まるまる、こまる」という文字だけのページをめくると、カラフルな小さな丸がたくさんちりばめられたページ。
低い迫力のある声で「まるまる、おおまる〜」と唱えながら、大丸のページを見せてやり、軽やかな声で「まるまる、こまる〜」と唱えながら、小丸のページを見せてやると、彼は何度でも笑い転げた。そのときの笑い声を思い出すと、今でも、胸がきゅんとなる。大人になってしまった息子を、母親がそこまで笑わせてあげることなんて、もうできやしない。子に絵本を読んでやるなんて、長い人生から見たら、本当にわずかな時間だ。後になって思い返すと、宝物のような時間である。
「まる」も「おお」も「こ」も、オノマトペではないけれど、発音体感と見た目の印象が一致していることば。「ま」と発音したとき口が丸くなり、「る」と発音したとき舌が丸くなる。「お」は口が最も大きな閉空間を作り、「こ」は最も小さな閉空間を作る。
絵本の読み手の口で起こることと、絵本の画が妙に一致して、なんとも楽しい。その感覚は、大人の読書にもある。大人になると、誰かが読んでくれなくても、文字を見ただけで発音体感が想起される。「ずごごごごぅ」なんて文字が書いてあると、その摩擦力と振動とパワーが、ありありと脳に浮かぶのである。
逆に言えば、その想起力が、8歳以下の子どもには足りないので、読み聞かせ(発音を見せてやる)や音読(自分で発音体感を確認する)が不可欠なのだ。小学校低学年では、教科書音読の宿題が出るが、あれは、言語脳を完成させるために、とても有意義なことなのである。
母親の選択に間違いはない
絵本を選ぶときのコツは、発音して楽しいことばを選ぶこと。日本語の場合、オノマトペ以外にも、たくさんの発音体感と事象が一致することばが存在する。よかったら、絵本売り場で、実際に発音して、確かめてください。
母親が面白いと感じ、発音して楽しいことばは、幼子もそう感じる。なにせ、ことばの感性は、母親が胎内で与えたものなのだから。母親の選択に間違いはない。
絵本が、ものがたり本になり、やがてファンタジーへと移行する。その間に、脳は、言語脳の完成期を迎える。脳に言語機能が揃うのは8歳である。
8歳近くなると、脳は、実際の発音に触れなくても、文字を見ただけで「発音体感」を想起するようになり、子どもたちは、自然に読み聞かせから卒業する。
ファンタジーへは、絵本の流れから自然に移行すればいい。脳神経回路が著しくその数を増やす脳のゴールデンエイジ(9〜12歳)を「ファンタジーに夢中」で過ごすのは、脳科学的には、たいへん理想的なことだ。圧倒的で半端ない超人生体験を脳に与えられる。
この時期を、答えが決まっている受験勉強に費やすなんて、もったいなくてしょうがない、と私は思ったので、一点の迷いもなく中学受験はパスした(もちろん、読書をしながら受験勉強もこなす器用な脳もあるので、一概には言えない。我が家の息子は不器用だったので、この結論に達した)。
ナルニア国物語、指輪物語、ハリー・ポッター……挙げていくだけでも、わくわくする。この時期の我が家の息子の心を一番奪ったのは、バーティミアス・シリーズだ。英国の若い(執筆当時)男性作家が書いた本で、大人男子でも楽しめる。
こうして、絵本→ファンタジー→本格社会派小説(ミステリーやSFの類いでもいい)の道を歩めば、脳はかなりの体験とセンスを積んで大人になれる。理系の科目が高等レベルになってもすんなりステップを上がれる。そう考えると、赤ちゃん期の絵本、手が抜けないでしょう?
前にも書いたけど、息子は15歳のとき、「ハハの子育てで、何が一番気に入ってる?」と聞いたら、一瞬も迷わずに「絵本を読んでくれたこと」を挙げた。
私自身も、幼い日に、来る日も来る日も寄り添って本を読んでくれた母の、甘い匂いと柔らかい腕の感触を今でも思い出す。
絵本の読み聞かせは、母と子の最初のデートのようなもの。親にとっても子にとっても、何年経っても風化しない、密やかで甘やかな思い出である。
ちなみに、我が子が既に幼児期を過ぎてしまっていて、うまく読書家にしてあげられなかったという方。大丈夫、まだまだ取り返しがつく。
親が本をむさぼり読む姿を見せてやれば、ある程度効果がある。「時間の隙を見つけて夢中になるほど読書は面白いんだ」という無意識の刷り込みになるからだ。高校生くらいまではこの手が使える。大学生以上の脳の戦略力は、読書力以外のことでつければいい。『英雄の書』(ポプラ社)をぜひご参考に。
母親自身が本嫌いなら、なおいっそうのこと、ここで「親が本を読まない→子も本を読まない→孫も本を読まない」という負の連鎖を食い止めなければ。読むふりだけでもかまわない。息子の将来の戦略力のために女優になろう。
<続きは本書でお楽しみください>