子どもが学校でだけ暴力的になるのはなぜ?児童精神科医が、状況別に様々な対処法をご紹介【書評】
公開日:2025/4/29
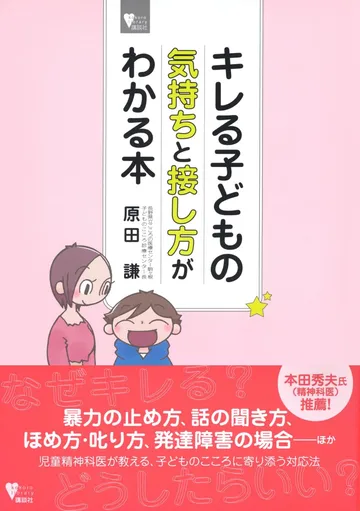
小さい頃から、端からみたら些細なことでキレて号泣。イヤイヤ期かな?と思いきやその後も収まる気配はなく……。そんな我が子に疲弊している時に出会ったのが『キレる子どもの気持ちと接し方がわかる本』(原田謙/講談社)。
本書の著者である原田氏は児童精神科医。その原田氏によると、子どもにとってキレることは最大の感情表現=こころのSOSとのこと。“キレる”という行動の裏にどんなメッセージがあるのか、子どもの気持ちに寄り添うことが必要だと述べる。しかしキレる子どもを前にして寄り添う気持ちを持ち続けるのは至難の業。筆者も実際子どもにキレ返し、事態を悪化させて反省したことは一度や二度ではない。
そこで本書ではキレる子どもへの対応や、気持ちの寄り添い方の土台となる「心構え」を解説。事例をわかりやすくマンガで紹介し、親や教師が子どもと接する際の方法論を伝授してくれる。
まず大切なのは心構え
キレる子どもに向き合う上で、一番大切なのは心構えであると最初に本書は説く。「どのような姿勢で向き合うのか」の指針となる心構えが確立していれば、ひとつの方法がうまくいかなくても焦らずに違うアプローチを検討することができるからだ。そこで本書はまず「基本的な対応」と「七つの心構え」を伝授。


上記を踏まえて一貫した対応をすることで大人の心が子どもに伝わり、子どもとの関係、子どもの言動に変化が生まれるというのだ。こちらのトピックスは各章や章末のコラムページで詳しく解説されているので、気になるところから読み進めることもできそうだ。
逆ギレして同級生に暴力……子どもを落ち着かせるためにまず取る行動は?
ここからはいくつかのケースをマンガとして取り上げながら、すぐ実践できる方法を紹介。例えば親の前ではいい子だけど、学校ではキレてしまう小学4年生Bくんの場合。

先生に自分だけ怒られたのが理不尽だと逆ギレし、同級生を蹴ってしまったBくん。
ここではまず「枠付け」という取り組みを紹介する。これは「次にキレた時の対応」を家庭や学校で決めておくことだ。私自身冒頭で述べた通り、子どもがキレた時に大人が冷静に対応する難しさは実感しているところ。“誰が・どこで・誰と”を具体的に決めておくことで、一貫した対応を取ることができるというのはとても興味深かった。
さらに本書は子どもができる対応も紹介。一度その場を離れたり別のことをしたりして気持ちを落ち着かせる「クールダウン」。

本人が自ら「クールダウン」ができない場合の「タイムアウト」など、子どもの状況に応じた方法を紹介していく。
「要求」を受け入れるのではなく、その裏の「気持ち」に寄り添うことが重要
子どもの気持ちを理解する際に重要なことを教えてくれるのが、学校を休みがちなDくんのケース。

Dくんは「転校したい」「引っ越したい」に対する親の「そんなの無理よ」にキレてしまった。ではどうしたらいいのか? そこで重要なのは「なぜキレたのか?」と子どもの気持ちを考えること。キレる子どもは「自分の気持ちをわかってくれない」と感じがちだとも本書は言う。
子どもの気持ちに寄り添う際、大切なのは“気持ち”と“要求”を分けて考えること。例えば今回のケースなら「学校が嫌だ」という気持ちには寄り添い「どうして嫌なのか、どんな気持ちなのか」と聞く。しかし「転校させてほしい」という要求自体は、現実的な範囲でできることのみ伝える。要求は受け入れられなくとも、子どもの気持ちを受け止めた上でできる限りの反応をすれば子どもも落ち着いてくると本書は述べている。
“キレるパターンは三種類ある”“「不当性」「故意性」に子どもは怒る”など子どもの気持ちを理解する手助けになる情報と具体的な対策の両方が掲載された、充実した一冊だ。
文=原智香




