本づくりの原点にあるのは「おもしろマグマ」?読むと本がさらに好きになる、「仕事としての出版」の入門書【書評】
PR 公開日:2025/7/16
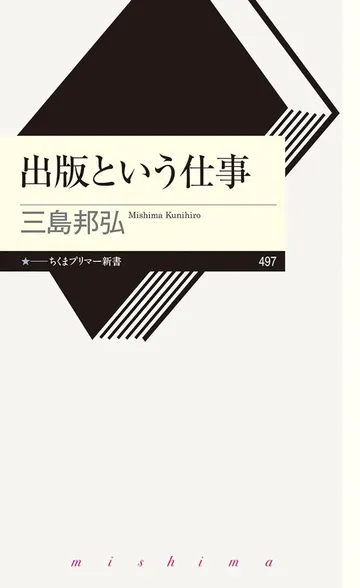
自分の住む街から本屋がなくなった……そんな悲しいことが、いま日本のあちこちで起きている。「スマホと時間の取り合いで本が読まれなくなった」「出版不況」「出版は終わった」とかいろいろ言われるけれど、本好きからすれば出版業界にはとにかく元気でいてもらいたいもの。
このほど登場したちくまプリマー新書の新刊『出版という仕事』(三島邦弘/筑摩書房)は、いかに面白い本を出すかという出版社の仕事をひもときながら、出版業界の現状&未来を見つめていく入門書。将来出版業界を目指している人はもちろん、「本は好きだけど、出版社の〈中の人〉はよくわからない」という出版初心者も、本が生まれる現場の「情熱」、そして未来の展望を知ることで、本がさらに好きになるに違いない。
著者の三島邦弘さんは来年創業20年を迎える小さな総合出版社・ミシマ社の代表だ。ビジネス本から文芸、エッセイ…独自の目線が光るユニークな本、ヒット作を送り出しているミシマ社は、著者や読者とのつながりも深く、信頼の厚い出版社として知られている。
実は出版業界においては「取次」という流通業者を介して本を卸すのが一般的だが、ミシマ社の場合は全国の書店と“直接取引”を中心に本を流通させているのも大きな特徴。かなり手間のかかることだが、その分自由度が高いため、新刊にこだわらずに既刊も積極的に販売できるし、絶版本も作らない。そうして「一冊入魂」で面白い本を作り続けるミシマ社の姿勢にひかれて、会社そのものに根強いファンもついている。
本書は、そんな三島さんが「仕事としての出版」の入門書として、編集・営業・書店、それぞれの具体的な業務についてだけでなく、それを支える「あり方」や「思い」といった根っこにあるものを伝え、そこから出版社の経営、さらには出版業界の「負」の側面とその改革についても視野を広げてくれるのだ。
本書において三島さんは、本づくりの原点にあるのは「おもしろマグマ」だと強調する。それは「書き手から見れば——どうしても書きたい。書かずにはいられない。なんとしても伝えたい。編集者にとっては——ぜひともかたちにしたい。なにより、自分が読みたい。プロの編集者として、後世に残す作品であるのを直感する」(本文より)といった強烈な衝動のようなもので、そうした書き手のマグマを編集者が受け取るところからスタートするのが本づくりなのだ。
「そんなの当たり前なんじゃないの?」と思うかもしれないが、実際には「おもしろマグマありきの本」ばかりが出版されているわけではない。詳しくは本書に譲るが、出版社として売り上げを立てるために刊行点数が優先され、マグマにこだわっている場合ではないこともしばしば…。
しかしそうではなく、あくまでおもしろマグマをキャッチして「本」に注入できるのがプロの編集者の役割だと断言する三島さん。そして、その本の最初の読者として面白さを受け止め、書店へとつなぐのが「営業」であり、そうして出来上がった本を読者へとつなぐのが「書店」――。そうした妥協なきプロたちの手で出版業界はまわり、私たちのもとに「面白い本」が届けられるのだ。
三島さんはあとがきで、自分に本書の執筆依頼がきた理由を「出版不況と言われる環境下で、一貫して楽しく仕事をしてきている。愚痴を言う前に、まずはやるべき課題を現場でしっかり実践」したからと分析する。そんな三島さんの姿勢が貫かれているからだろう、本書を読むと「出版業界、まだまだやれる!」となんだか前向きな未来が見えてくるようだ。
文=荒井理恵




