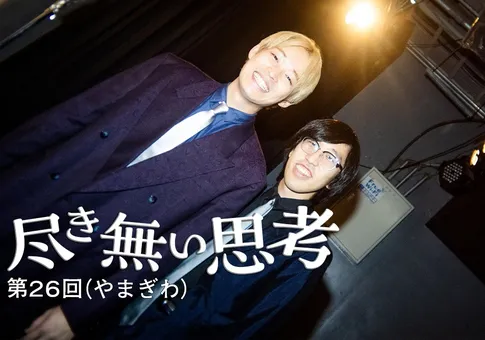東大卒コンビ・無尽蔵のコラム連載「尽き無い思考」/第16回(やまぎわ)「お笑いと内輪ノリの甘美な関係【前編】〜お笑いは所詮内輪ノリ〜」
公開日:2025/8/21
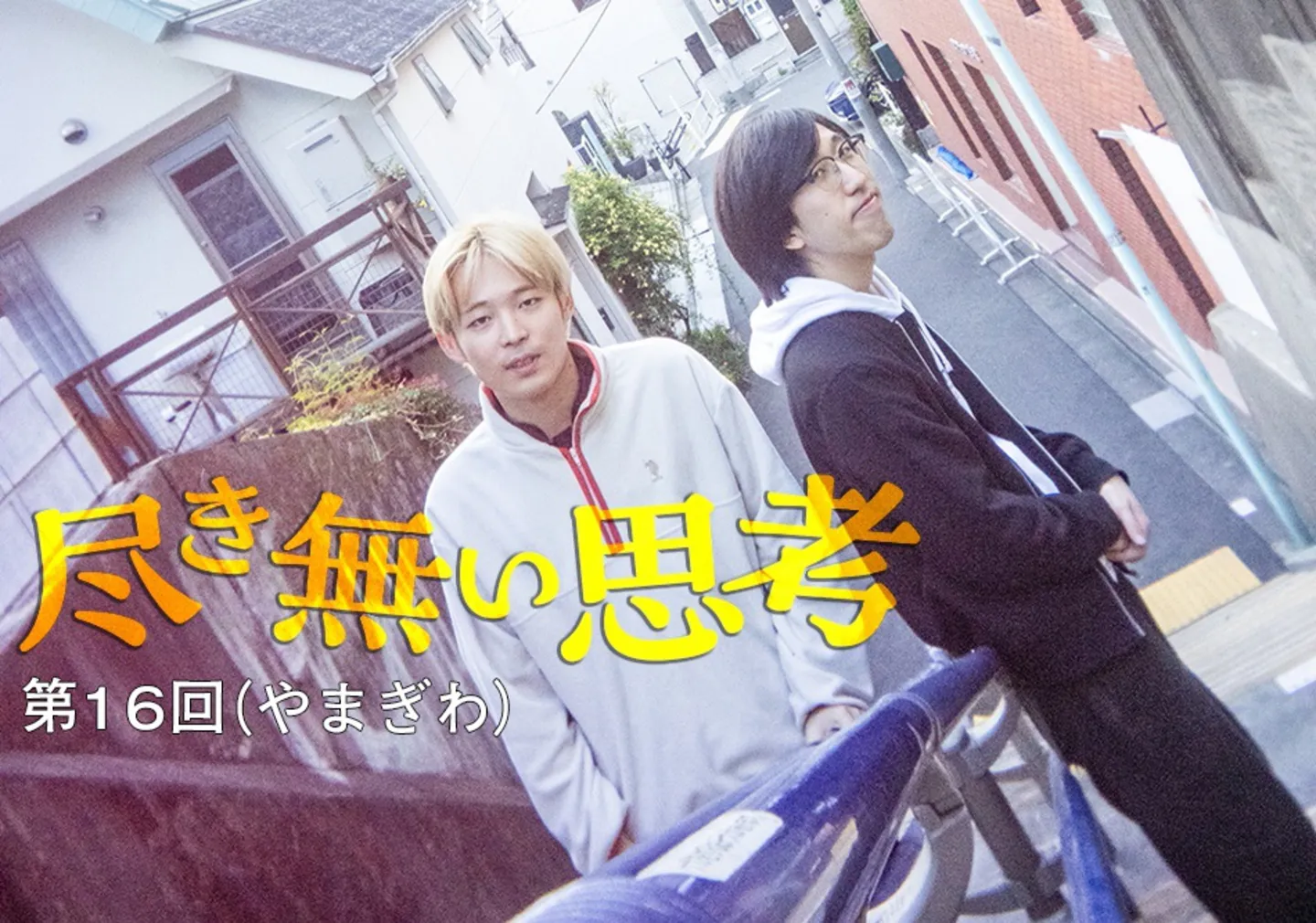
サンミュージックプロダクションに所属する若手の漫才コンビ・無尽蔵は、ボケの野尻とツッコミのやまぎわがどちらも東大卒という秀才芸人。さまざまな物事の起源や“もしも”の世界を、東大生らしいアカデミックな視点によって誰もが笑えるネタへと昇華させる漫才で、「M-1グランプリ2024」では準々決勝に進出・「UNDER5 AWARD 2025」では決勝に進出し、次世代ブレイク芸人の1組として注目されている。新宿や高円寺の小劇場を主戦場とする令和の若手芸人は、何を思うのか?“売れる”ことを夢見てがむしゃらに笑いを追求する日々を、この連載「尽き無い思考」で2人が週替わりに綴っていく。第16回はやまぎわ回。
第16回(やまぎわ)「お笑いと内輪ノリの甘美な関係【前編】〜お笑いは所詮内輪ノリ〜」
お疲れ様です。私事ではございますが、先ほどまでお笑いのお仕事と旅行を兼ねて北海道におりました。北海道まで無尽蔵のお笑いの輪が届いたかと思うと万感の思いですね。ウニいくら丼、あれも万感の思いでした。
さて、今回はお笑い界の「内輪ノリ」問題についてお話ししたいと思います。といっても僕が勝手に言っているだけなのですが。
「内輪ノリ」とは、僕なりに定義させていただくと「共通の知識・経験・価値観を前提としたくだりやコミュニケーション」のことです。
ここで重要になってくるのは、「内輪ノリが伝わらない人の存在」です。伝わらない人がいないのであれば、それは内輪ノリとはいえません。
特定の経験を共にしている人、趣向を同じくしている人でなければ分からない、という閉鎖的な性質を持っているのが内輪ノリです。伝わらない人が多ければ多いほど、より内輪ノリ的である、と言えるでしょう。
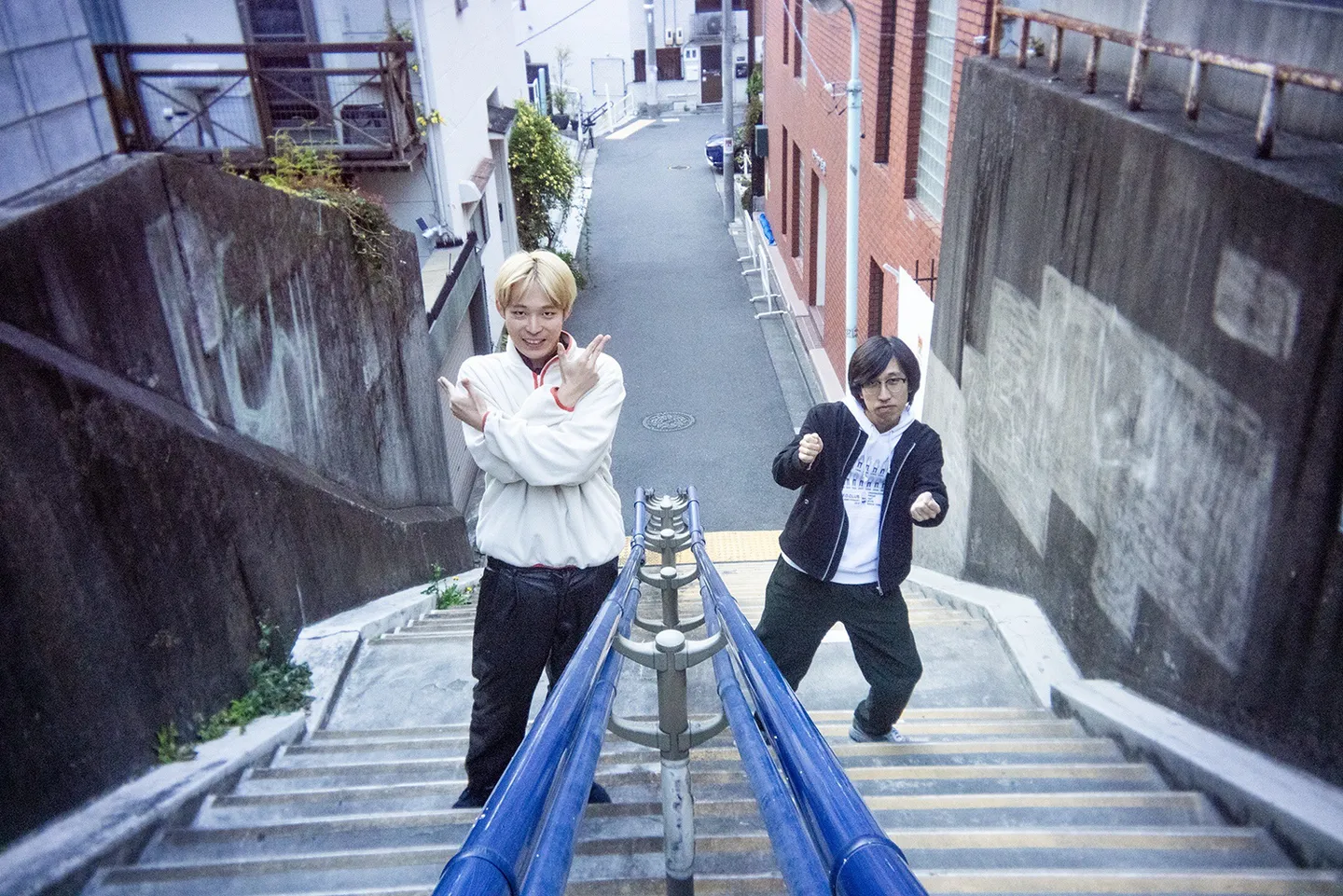
“お笑い界における内輪ノリ”を論じるのであれば、論点は2点挙げられると考えています。
1点目は、そもそもお笑いが内輪ノリとは切っても切れない関係であるという点。
2点目は、近年お笑いシーンの内輪ノリ化がより深まっているように感じられるという点です。
ここでは、まず1点目のお話をさせていただきます。
前提として、世間的にはお笑いは「内輪ノリ」と対置されている存在なのかなと思います。受け手に相応の経験や知識を求める内輪ノリに対して、お笑いは万人に開かれた大衆演劇であると。
しかし私はお笑いこそ「単なる大きな内輪ノリ」に過ぎないのではないかと考えています。その理由を説明するためには、「どのように笑いが生まれるのか」という仕組みから解説しなくてはなりません。
「お笑いの手法は神秘的なものである必要があり、受け手にそのメソッドを伝えることはお笑いに対して俯瞰的な態度を取らせてしまう悪手でしかない」という派閥も根強く、僕もその主張には強く賛同しますが、あくまで一般論のみを語ることとしてご容赦ください。

言われ尽くされていることですが、お笑いの根幹は「共感」であると考えます。「わかること」と言い換えても良いです。
例えばミルクボーイさんのコーンフレークの漫才では、共感を産む代表手法である「あるあるネタ」が大量に散りばめられています。「あれよう見たら牛乳の栄養素を含んだ五角形になってんのよ!」なども、日々意識していることではないものの「わかる!」と思う人は多いでしょう。
また、僕が好きな言葉がチュートリアルさんのWikipediaに掲載されてます。チュートリアルさんのネタの基本テーマは「わけわからんけど、わけわかる」だそうです。ほとんどのお笑いはこの言葉に集約されてしまうほど言い得ていると思います。
参照元からの引用とはなりますが、例えばチュートリアルさんの「チリンチリン」のネタも、「自転車のチリンチリンを盗まれたことを人生の大きな挫折のように語る」という「わけわからん」状況ではありつつも、「ご両親には言わん方がええ」「何かを求めてインドに行った」といった節々のあるあるは「わけわかる」ため、おかしみが成立しています。
このおかしみを「わかること」が共感を生み出し、それがお客さんの中で繋がり大きな笑いのうねりとなるのです。その時の皆さんは、アルキメデスが「エウレカ」と叫んだ時と同じ表情をたたえているでしょう。
ここで重要なのはただ「わかる」だけではダメだということです。当たり前の事を言っているだけでは、そこにおかしみはありません。「わかる」ためのある程度のハードルが必要です。そのハードルを乗り越え、「わかった!」とたくさんのシナプスに電流を走らせるような感覚が笑いに繋がります。

ハードルが低く万人ウケすぎるとそれはエンターテインメントとしてもはや陳腐であり、ハードルが高くニッチすぎると大衆的な賛同は得られない。その中で「ある程度大衆的でかつ消費されていない程度にニッチな」丁度良い塩梅のスイートスポットを見つける行為こそが、お笑いの真髄であると言えるでしょう。
それは集団の中に丁度良い大きさの円を描く行為にも似ています。集団の中に大きすぎず小さすぎない「わかる人」の集合を作り、その中で共感の渦を起こすのです。このように集団の中に「共感の輪」という円を描く行為こそがお笑いであり、その円の中に所属しているということの愉悦感と安心感が人を笑顔にします。
この時点で、“円の中”と同時に“円の外”の存在が確かめられます。もちろん、笑いを増幅させたり、効果的なタイミングで笑い声を起こさせることは、技術的な部分が支えていますが、基本的な笑いのメカニズムというのは共感であり、「目の前で起こっていることが理解できているコミュニティ」に所属しているという意識です。その点でお笑いは内輪ノリと同様の排他性を有していると言えるでしょう。
思えば、特に大衆が意識されているテレビのバラエティも「大きな内輪ノリ」と呼んで差し支えないのではないでしょうか。
「醤油うこと!」「やってるやってる!」などさんまさんの所謂「定食」も、それ自体が面白いというよりかは、同じくだりを繰り返すことで「これを面白がる」というコミュニティを作り出しているような印象を受けます。
とんねるずさんの業界人ノリ(ex.しきりにつるとんたんと言う)なども、視聴者にそれを理解させることで業界人コミュニティに所属しているような疑似体験を提供していると言えるでしょう。
僕含め、そんなテレビを見てむしろ疎外感を覚える人も少なくなかったのではないでしょうか。「なんとなくこのノリついていけないなー…」と思うのは、テレビ、ひいてはお笑いの排他的な性質の方に目が向いているのかもしれません。

多種多様なネタがある中で、どのネタを面白いとするか、強く共感を覚えるかは、その人が帰属するコミュニティを決めることになりますから、必然的に自身のアイデンティティを形成することともなります。
テレビのような「大きなコミュニティ」に所属する事を是とする人もいれば、それを非とし確固たる自身のアイデンティティを求める人もいるでしょう。
誰も笑っていないところで一人笑ったり、万人ウケしないであろうネタを絶賛したりする現象が時折見受けられますが、それは自身のアイデンティティを守る行為と捉えられます。自分は他人と違うんだというポーズを取り自分の存在を確かなものとしている行為、そんなハリネズミのような姿を以て人は「トガり」と呼びます。僕も大学時代はそんな人間の一人でした。
重要なのは、コミュニティの大小に関わらず、そこで得られる甘美な安心感は最大限許容しつつ、自身のコミュニティの外にあるお笑いを「つまらない」や「わからない」といった言葉で否定しないことでしょう。
イジメのようにコミュニティの外側の存在を否定することで連帯感を強めることはできるでしょうが、他者を傷つけてまで快楽を得て良いという理由にはなりません。人の価値観は千差万別なのですから、「自分はこれを面白いと思う」という絶対的なアイデンティティだけを持っていればそれで十分なはずです。
ここまで、お笑いもある種内輪ノリの一部であり、集団への帰属意識と強く関連しているのだという話をしてきました。ここから、近年のお笑い界ではその内輪ノリの傾向が益々強まってあるのではないかという話をしたかったのですが…WEB記事とはいえ紙幅も足りなくなってきましたので、今回はここまでとさせてください。二週間後、「あのお笑い界の地面師ノリなんやってん」という話をしたいと思いますよ。
■無尽蔵
サンミュージックプロダクション所属の若手お笑いコンビ。「東京大学落語研究会」で出会った野尻とやまぎわが学生時代に結成し、2020年に開催された学生お笑いの大会「ガチプロ」で優勝したことを契機としてプロの芸人となった。「M-1グランプリ2024」では準々決勝に進出、「UNDER5 AWARD 2025」では決勝に進出。
無尽蔵 野尻 Xアカウント:https://x.com/nojiri_sao
無尽蔵 野尻 note:https://note.com/chin_chin
無尽蔵 やまぎわ Xアカウント:https://x.com/tsukkomi_megane