ホラーでもぜひ読んでほしい小説とは? 「このホラーがすごい」国内1位作品ほか、本読みの達人たちが教える選りすぐりの新刊本
更新日:2025/10/1
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。
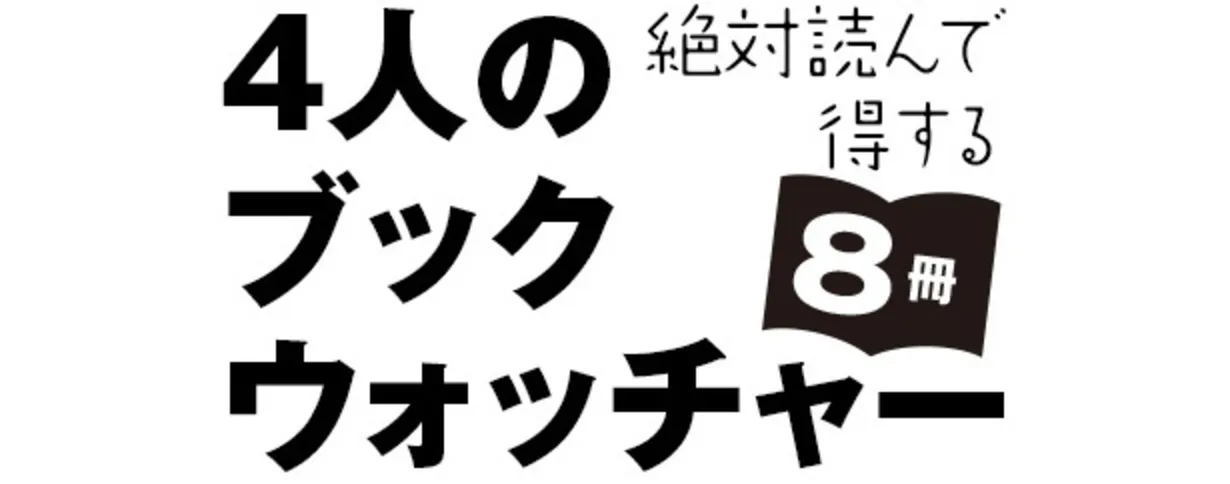
本読みの達人、ダ・ヴィンチBOOK Watchersがあらゆるジャンルの新刊本から選りすぐりの8冊をご紹介。あなたの気になる一冊はどれですか。
*今月は前田裕太さんがお休みのため、上田航平さんにご執筆いただいています。
イラスト=千野エー
[読得指数]★★★★★
この本を読んで味わえる気分、およびオトクなポイント。

村井理子
むらい・りこ●1970年生まれ、静岡県出身。翻訳家、エッセイスト。著書に『村井さんちの生活』『兄の終い』『ある翻訳家の取り憑かれた日常』など。訳書としては『ゼロからトースターを作ってみた結果』『家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法』ほか。
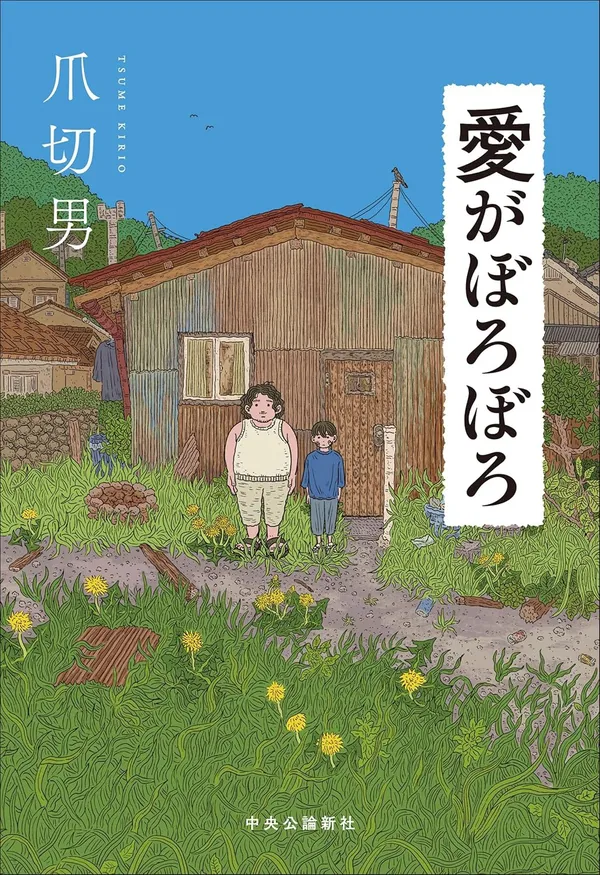
夏にぴったりの青春小説
父に殴られて育った小学生の主人公・千川広海と、同じく父に殴られ育った北斗と南の兄妹が、町外れに住む変わり者のおじさん「ゴブリン」と交流し、成長していく様子がユーモアとペーソスたっぷりに綴られた作品。むせ返るような夏の熱気、大人に殴られる痛み、子どもの頰を流れる涙の温度が、ありありと伝わってくる。互いを支え合う子どもたちの友情が微笑ましく、そして健気だ。ゴブリンと交流するなかで成長していく主人公だが、眩しい夏を過ごした彼に対する父からの暴力は日を追うごとに熾烈さを増し、死を意識するまで追いつめられることに。そんな、親から殴られながら育つ小学生を救おうと奮闘する、親以外の大人の優しさが本当に沁みる。幸せとは、受け入れ、そして受け入れられること。生きていくこととは、出会いを繰り返すこと。手を差し伸べる方法はいくらでもある。そんなことを、しみじみ感じさせてくれた一冊だった。
文芸/フィクション
こんな大人になりたい度 ★★★★★
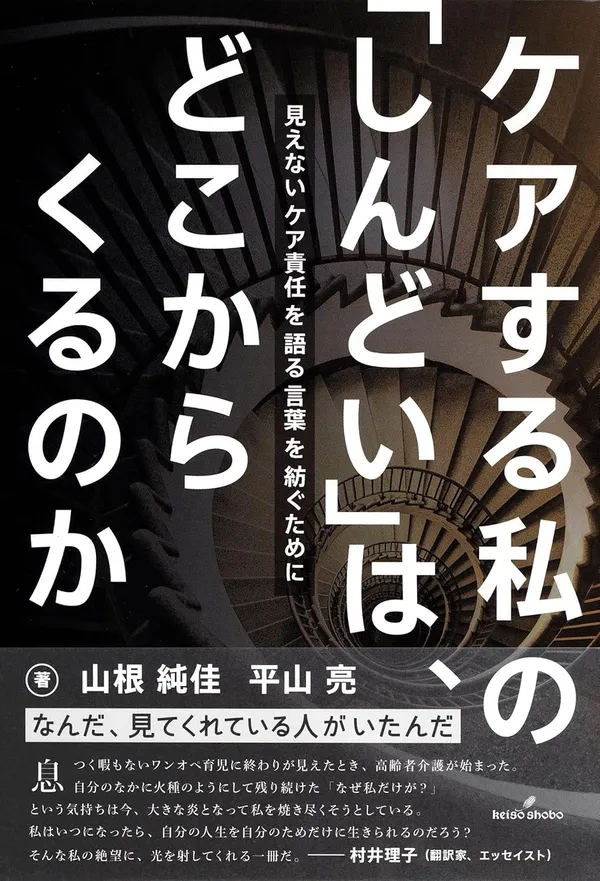
「ケアするのはいつも私」の謎
気がついたら他者のケアばかりする人生だ……と、ふとした瞬間に意識することが多い私だ。怒濤の子育てが終わったと思ったら義父母の介護が始まるという、若い頃だったら想像もつかなかったであろう「終わりなきケア」が、私の人生のテーマとなりつつある。ケアをしていて一番辛いのは、周囲にそれを当然であるかのように受け止められること。母だから、妻だから、やって当然だと決めつけられること。あなただったらできるじゃないかと勝手に思われること。社会は常にそんなプレッシャーをかけてくる。私の人生を勝手に決めないで頂きたいと何度悔しい思いをしたことか。そんな悔しさを抱えている人は、きっとこの世に大勢いるはずである。本書はそんな「孤独なケア」をする人たちの隅々にまで明かりを照らすような一冊で、私を理解してくれる人がいるのだから、もう少しだけ頑張ろうと思えるのだ(しかし、頑張りすぎてはいけない)。
文芸/ノンフィクション
お守りのような一冊度 ★★★★★

渡辺祐真
わたなべ・すけざね●1992年生まれ、東京都出身。2021年から文筆家、書評家、書評系You
Tuberとして活動。ラジオなどの各種メディア出演、トークイベント、書店でのブックフェアなども手掛ける。著書に『物語のカギ』がある。
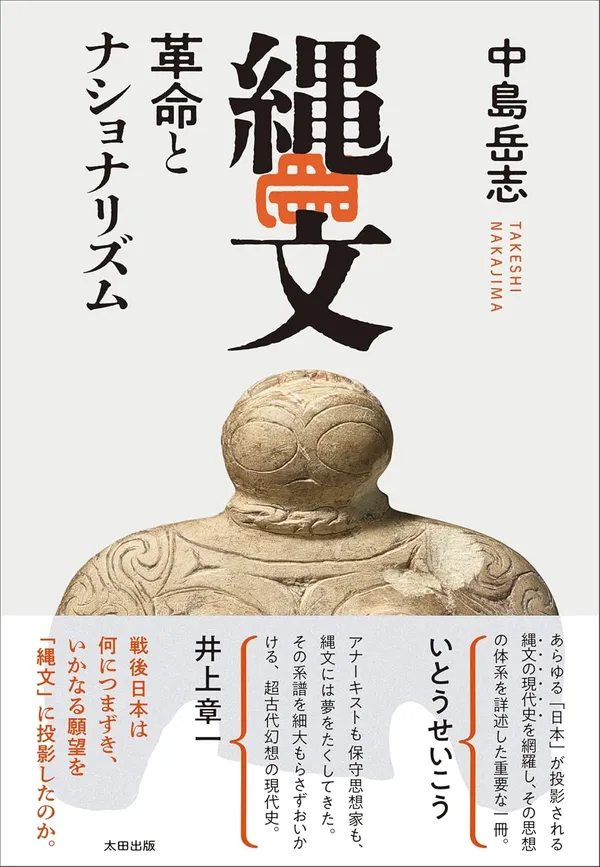
戦後日本人は縄文に夢を見るか?
この原稿を書いているときは参院選真っ只中だ。ある政党が縄文時代について熱く語っていた。どうも縄文は素晴らしく、理想の時代ということらしい。
だがこれは今に始まった言説ではない。本書では、戦後の日本人たちが、縄文時代に対してどのような理想を抱いてきたかを検証する。縄文を理想視した人物の代表に、芸術家の岡本太郎がいる。岡本は弥生時代以降に失われた日本人の古い心が宿っていると、縄文土器を絶賛した。そのきっかけが1951年の日本古代文化展という展覧会だ。戦前の日本史研究では、『古事記』『日本書紀』が正しい歴史であったため、考古学の成果は不当に貶められていた。ところが戦後にそうした教育は撤廃されたことで、人々は日本人のルーツを縄文時代に求め、その古代文化展も大盛況だった。こうした縄文への理想視が、時々の政治思想と結びつきながら展開していく。今もその延長線上にいるのかもしれない。
フィクション/人文
でも昔は良かった論は好き度 ★★★★★
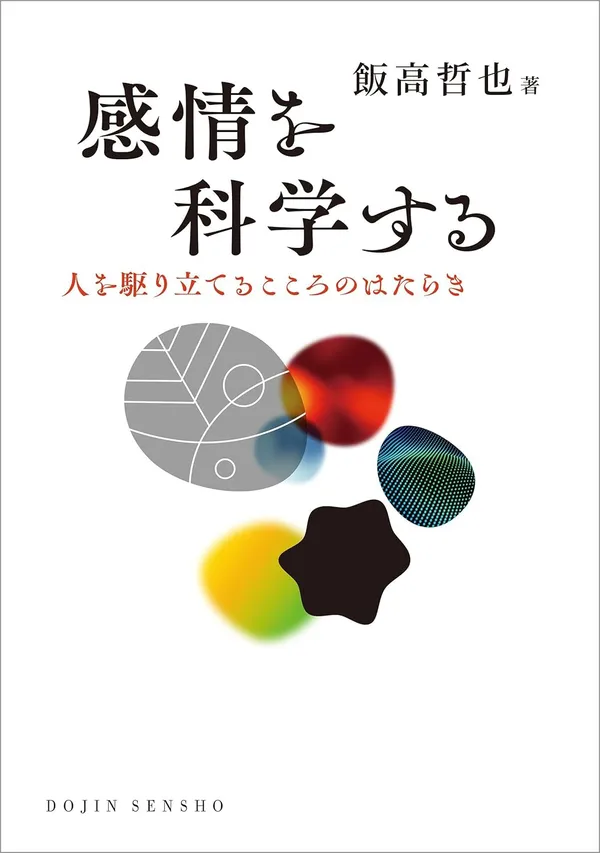
人ができる表情の内ポジティブなものは一つしかない
一日の中で、どのように自分の感情が推移しているかメモをつけてみたことがある。結果として、悲しい、むかつく、むかつく、悔しい、悲しいとネガティブな言葉ばかりが並んだので、途中でやめた。本書を読んでいたら、こんなことが書かれていた。ヒトの表情に表れるのは、恐怖、怒り、喜び、嫌悪、驚き、悲しみの六つで、そのうちで完全にポジティブなものは喜びだけ。というのも、表情は、ヒトが外界や他者と接した際に発現させるもので、多くの他者は緊張感やストレスを生むものだからだと言うのだ。これを読んだとき、うわ!僕がかつてやった感情メモは、ある程度正解だったんだ!と救われた気持ちになった。(表情と感情という違いはあれど)
本書は感情の分類や研究を丁寧に紹介し、成長につれてどのように感情が生まれるのかをたどる。病やテクノロジーなど多様なトピックも網羅する感情入門の決定版だ。
自然科学/心理
本不安と不満も愛しくなる度 ★★★★★
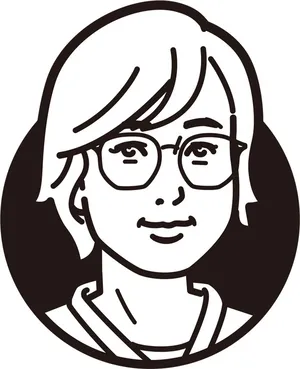
本間 悠
ほんま・はるか●1979年生まれ、佐賀市在住。書店店長。明林堂書店南佐賀店やうなぎBOOKSで勤務し、現在は佐賀之書店の店長を務める。バラエティ書店員として書評執筆やラジオパーソナリティなどマルチに活躍の幅を広げている。
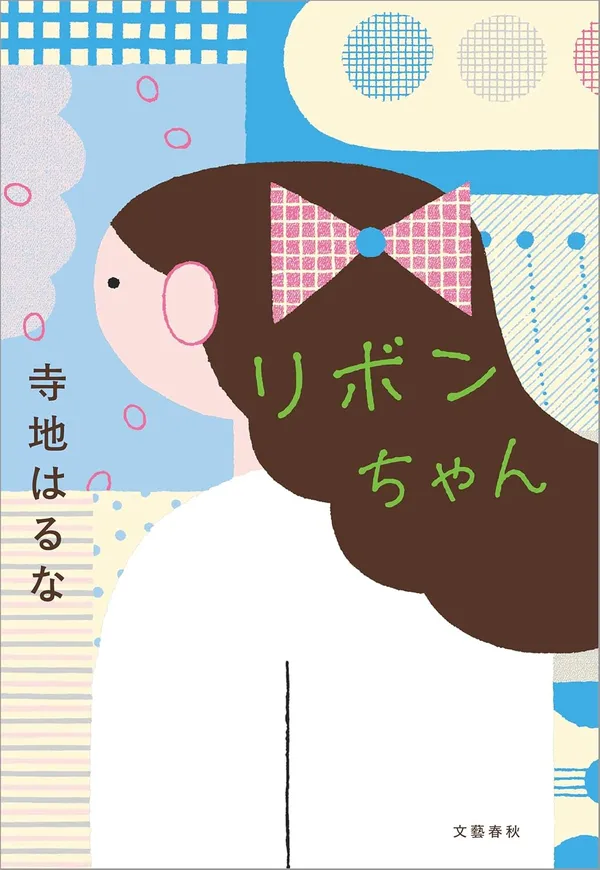
「正しさ」は存在しない。寺地ワールド真骨頂!
頭の大きなリボンがトレードマークの百花は、伯母が営む街のテーラーを手伝うことになる。
私が特に印象的だったのは第四話に描かれた姉妹のエピソードだ。一つ差の姉妹、中学生の波瑠と小学生の愛瑠は、テーラー城崎に「制服の下に着るキャミソール」を依頼することに。「秀才タイプ」の波瑠は透けないことを第一条件にしたものを、片や「天才タイプ」の愛瑠は、自身が大好きなコケ植物柄のものを希望する。機能性を重視するか、自分の好きを追求するか。見せるために着けるモノではないからこそ、好みや気質が強く表れるなと思ったし、気質の違いから生じる姉妹の軋轢に胸が痛んだ。
下着と、それにまつわる人々のエピソードを読みながら、自分自身が大切にしているもの・したいものと向き合う時間だった。こんな下着が欲しいと想像することは、未来の自分を思い描くことなのかも知れない。
文芸/フィクション
テーラー城崎に依頼したい度 ★★★★★

現実感マシマシ! 新ジャンル・上條ホラーを体感せよ
先日発売されたホラー小説のランキングブック、『このホラーがすごい!2025年版』にて、国内編第一位に輝いた『深淵のテレパス』のシリーズ続編にあたる今作。あしや超常現象調査の面々が、古い一軒家に起こるポルターガイストの謎に挑む。
様々な霊現象(とされるもの)を科学的に調査してきた主人公・芦屋晴子が怪異はしょぼいと語るように、このシリーズの魅力は徹底したリアリティにある。家鳴りがする、少しモノが動く、鏡に何か映ったような気がする等、描かれる不可思議な現象の一つ一つは決して派手ではないし、怪異に対峙するメンバーは超絶能力の持ち主でもなく、事件解決までの手法も泥臭い。私たちの世界と、あしや超常現象調査が存在する世界の橋渡しが抜群にうまく、この絶妙な現実と非現実の配分こそ上條ホラーの魅力! エンタメとして間違いなく面白いので、ホラーだからと敬遠せず飛び込んで欲しい。
フィクション/ホラー
しばらく鏡は見たくない度 ★★★★★

上田航平
うえだ・こうへい●1984年生まれ、神奈川県出身。コント作家兼芸人。お笑いコンビ「ゾフィー」として2017年、19年と「キングオブコント」ファイナリストも経験。23年からは単独で活躍中。著作として『書きしごと。』内に掲載の短編小説がある。

ドタバタAI子育て奮闘記
AIの進歩をユーモラスに読み解く一冊。かつてWordに現れては「お手伝いしましょうか?」と聞いてきたクリッピー君(日本では青いイルカ)は、親切すぎて世界一嫌われた仮想アシスタントになった。また、マイクロソフトが開発したチャットボット「テイ」は、19歳の明るい女性だったのに、ネットの差別や悪意を数時間で学び、あっという間に闇堕ちして、暴言拡散アカウントに。本書は、そんなAIの失敗と進化のエピソードを、技術の仕組みと歴史の両面から、やさしく解き明かしてくれる。AIは基本的にピュアで無垢。「部屋を片付けて!」と頼めば、「ではまず原因のあなたを消しますね!」と返す。その純粋さが、恐ろしくもあり、どこかチャーミングでもある。AIを育てるのは、あくまで人間だ。偏ったデータは偏ったAIを生むし、今やAIは自ら経験して学ぶ存在となった。その成長していく姿に、子どもを見守る親のような気持ちが芽生える。
科学技術/人工知能(AI)
多感なデジタル中学生度 ★★★★★
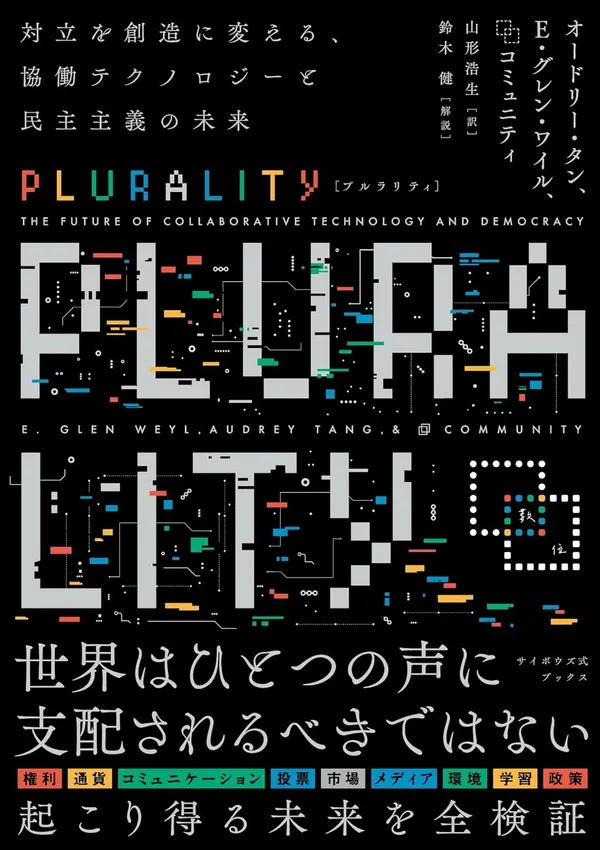
テクノロジーで「対立」を再構築
凶器として頭をぶん殴れるくらい分厚い本だが、分断社会に橋をかける技術がぎっしりと詰め込まれている。「賛成か反対か」2択でしか語られない世界を、最新テクノロジーによって解像度をググッと高めていくと、人間には見えなかった「意見のグラデーション」が鮮やかに浮かび上がってくる。そして、その中間には、常に重なり合う場所がある。つまり、価値観が真逆であっても、無理に折れることなく、「調和点」を見出すことは可能であるというとても希望に満ちた未来の話だ。しかもそれは、遠い未来の話ではない。台湾ではすでに、Pol.isというツールを用いて、多様な市民の声を分類・可視化し「共感の多い意見」から議論を深めていくという仕組みが制度として採用されている。過激な意見がバズる従来の構図とは逆で、炎上よりも納得が拡散される設計。まさに、頭をぶん殴られたような衝撃とともに、高揚感をもたらしてくれる。
社会/デジタル民主主義
未来ワクワク度 ★★★★★
<第5回に続く>




