社会に向いてなくても案外大丈夫。自分に合った仕事の見つけ方【カレー沢薫 インタビュー】
公開日:2025/10/17
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。
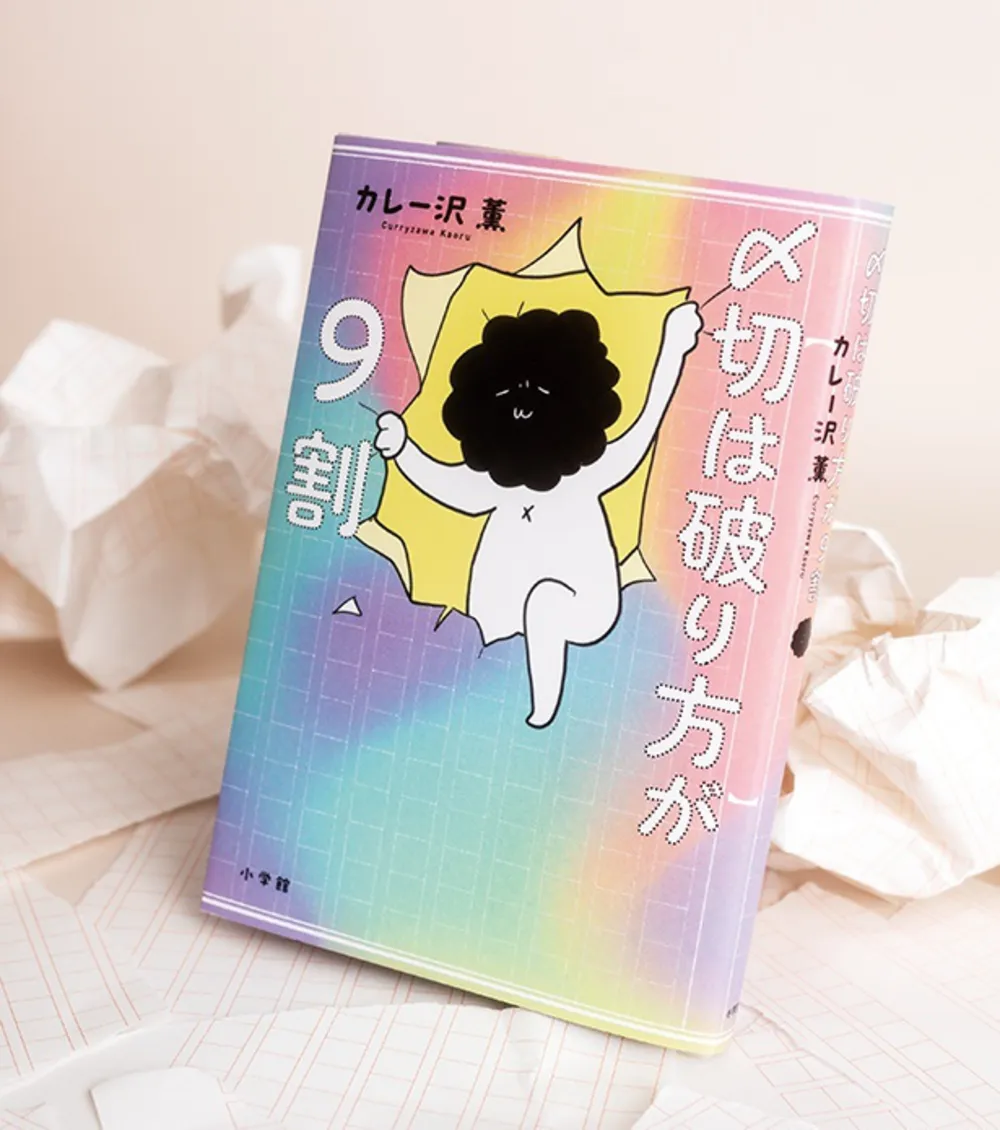
なければ仕事にならないが、あればあったで鬱陶しい。〆切とは、なんと厄介な存在だろうか……。
ドラマ化された『ひとりでしにたい』をはじめ、多くのマンガ連載を抱えながら、エッセイも精力的に書き続けるカレー沢薫さん。その新刊は、実に挑発的なタイトルの一冊だ。帯には「本書に載っている原稿の9割は催促を受けてから書き始めた」とあるが、これは本当だろうか。
「この連載に関しては、〆切がよくわからなくて。『この日まで』という日付指定がないので、担当編集者から催促が来たらその日か翌日に書いています。ただ、催促があるうちはまだいいんです。エッセイの場合、こっちは原稿を出さない、編集者も催促してこないという双方のやる気のなさから、連載が自然消滅することもありますから。そう考えると、やっぱり〆切は必要なんです。それに、編集者も本当にまずい〆切は伝えてこないんですよね。他の業種と違って、マンガやエッセイの世界は多少〆切を破っても許される。だから、私のように適当な人間でも、この仕事ができるんだと思います」
本書には、Web連載『ハクマン 部屋と締切(デッドエンド)と私』から抜粋した29編のエッセイに加え、〆切に関する書き下ろしコラムを収録。そもそもこの連載がスタートしたのは、2018年のことだった。
「最初は『小説を書いてみては』という依頼でしたが、書いたことがないので難しくて。そこで、書き慣れているエッセイを連載することにしました。当初は、マンガはどう作られているのか、マンガ家はどんな生活をしているのか、『バクマン。』のようなマンガに関するエッセイを書いてほしいという依頼だった気がします。ただ、編集部からは『今回はこのテーマで』という指示が一切ないので、その時に書けることを書くという感じ。あまり関係ないことを書いている回もあります」
『バクマン。』といえば、2人の少年がコンビを組んでマンガ家を目指す青春ストーリー。カレー沢さんも、キャラクターの作り方から確定申告の乗り越え方まで、マンガ家生活を赤裸々に明かしている。時には、打ち切りを言い渡す編集者、とんでもない失礼メールを誤爆した編集者などへの恨み節も……。
「ほとんど逆恨みですけどね。編集者は社会性や社交性が高くて、私とは対極に位置する人たちです。だから、敵対心や嫉妬心を抱いてしまうんですよね。数少ないミスを何度も書くので編集者がひどいように見えますが、回数で言ったら私のほうがよっぽどやらかしてる。恨みつらみは本音ですけど、本気で怒っているわけではないし、もちろんいなくなったら困ります」
連載は現在も続いているが、本書に収録されたのは23年までのエッセイ。一冊にまとまったものを読み直した感想は?
「世の中は変わりましたけど、私の生活はそんなに変わってないな、と。ただ、コロナ禍を挟んでマンガ業界の状況はかなり変わりましたね。紙と電子書籍のシェアが入れ替わる転換期の話もけっこう入っています」
意味のない自己否定はしなくていい
連載の打ち切りが決まった、自分より売れているマンガ家とは口をききたくないといったぼやきも多いため、カレー沢さんの書くものは“自虐系”と言われることが多い。だが、本人は“自己肯定系”だと思っているという。自己肯定感と自信について書いた回は、読者を勇気づける効果もありそうだ。
「家でひとり、誰とも接することなく文章やマンガを書いているので、自分と向き合う時間が非常に長いんですね。『私の自信のなさ、自己肯定感の低さは一体どこから来ているんだろう』と考えることも多くて。でも、考えたからといって、私の自己肯定感が上がるわけでもない。『不毛だから、みんなは考えちゃダメだよ』『意味のない自己否定はしなくていいよ』と伝えておこうと思って」
過度な卑屈と自虐は周囲に対する他害になってしまいかねない。そんな言葉にも、目からウロコが落ちる。
「面白ければいいですが、ただ相手を困らせるだけの自虐もあるじゃないですか。それに、時代的にも自虐はもう受けない。だから私も、自分が書いたものを『面白くない』とは言いません。私の本を面白いと思ってくれる人、お金を出して買ってくれる人がいるなら、書いた本人がそれを言うのは失礼だと思うので。もちろん売れない作品もありますけど、それを『失敗作』と言ったら読者も落ち込んでしまいますから」
「私の本は売れていない」ではなく、逆に言えば「希少本」「『ONE PIECE』の1億倍レア」と考える。この「逆に言えば」という発想の転換が、カレー沢さんのエッセイの根幹をなしている。
「そう、よく使う表現ですね。ネガティブとポジティブは裏表。『悪く言えばこうだけど、良く言えばこうだね』と、いろんな視点から考えればいいだけだと思ってます」
こうした考え方を、ネットミームやオタクワードを盛り込み、毒気のある笑いをまぶして伝えている。この独特のカレー沢文体は、どのようにして生まれたのだろうか。
「さくらももこ先生やナンシー関さんのエッセイが好きだったので、そこから影響を受けたのかなと思います。マンガ家を目指したきっかけも、さくらももこ先生。『ちびまる子ちゃん』を読んですごく笑ったんですよね。だから私も、根底に笑わせたいという気持ちがあるのかもしれない。真面目なことを書く時も、ちょっと冗談を入れたいんです」
仕事がつらいならつらくない場を探していい
このエッセイには、仕事論の側面もある。何度〆切を破っても怒られないマンガ家という職業、その実情を知ることで、「こういう世界もあるのか」と視界が開け、肩の力がふっと抜ける。
「私は10年近く、会社員として事務職をしていました。指示を受けて、みんなで役割分担しながらひとつの仕事をするのですが、それが本当につらかった。仕事ができないので、自分がしたことによって誰かの作業に影響が出たり、“ほうれんそう(報告連絡相談)”ができなくて周囲の仕事が滞ったりと迷惑をかけることがすごく多かったんです。でも、マンガ家は自分が何をしてもすべて自分に返ってきます。誰かに対して申し訳ないと感じることがないので、気持ちがすごく楽になりました。もちろん今の仕事にもストレスはありますけど、会社員時代とは質がまったく違いますね」
〈己の才能を見つけるのも大事だが、才能がないと理解することも大事である〉〈「絶望的に向いていない仕事」を回避し「辛うじてできる仕事」につくことは可能である〉──作中では仕事に対する向き合い方も語られているため、マンガ家志望者に限らず、すべての働く人にとってヒントになりそうだ。
「どんなに仕事がつらくても、みんな我慢しちゃってますよね。でも、一番大事なのは、自分がつらくないこと。どうせ働かなきゃいけないなら、自分に合わない場所で頑張るより、負荷が少ない職場を選んだほうがいい。長続きしますし、会社にとってもプラスですから。働く会社によって仕事も人も違うので、自分に向いている場所を探してみるのもいいのかなと思います。これから職業を選ぶ人、今の職業は向いてないと感じている人、フリーランスに興味がある人が、このエッセイが読んで『こんな働き方もあるのか』と参考にしてくれたらうれしいです」
取材・文:野本由起 写真:首藤幹夫
かれーざわ・かおる●山口県生まれ。マンガ『クレムリン』でデビュー。2021年『ひとりでしにたい』で第24回文化庁メディア芸術祭のマンガ部門優秀賞を受賞。同作は今年NHKでドラマ化された。他の著書にマンガ『なおりはしないが、ましになる』、エッセイ『寝そべり錬金術』『負ける技術』『ブスの本懐』など。
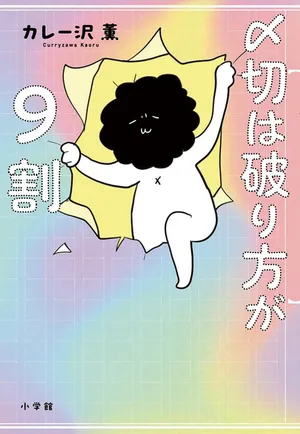
『〆切は破り方が9割』
(カレー沢 薫/小学館)1760円(税込)
「本書に載っている原稿の9割は催促を受けてから書き始めた」──〆切が迫ると、なぜか原稿ではなくSNSを始めてしまうカレー沢さん。でも、どれだけ納期を破っても、マンガ家なら怒られない! 会社員の才能もなければ社会にも向いていないけれど、それでも自分を嫌いにならずに生きるには? 仕事に悩むすべての人に贈るエッセイ集。





