入社3年目テレビ局員によるエッセイ連載「テレビぺろぺろ」/第7回「“東大卒”の価値に愚かにも無自覚でした」
公開日:2025/12/19
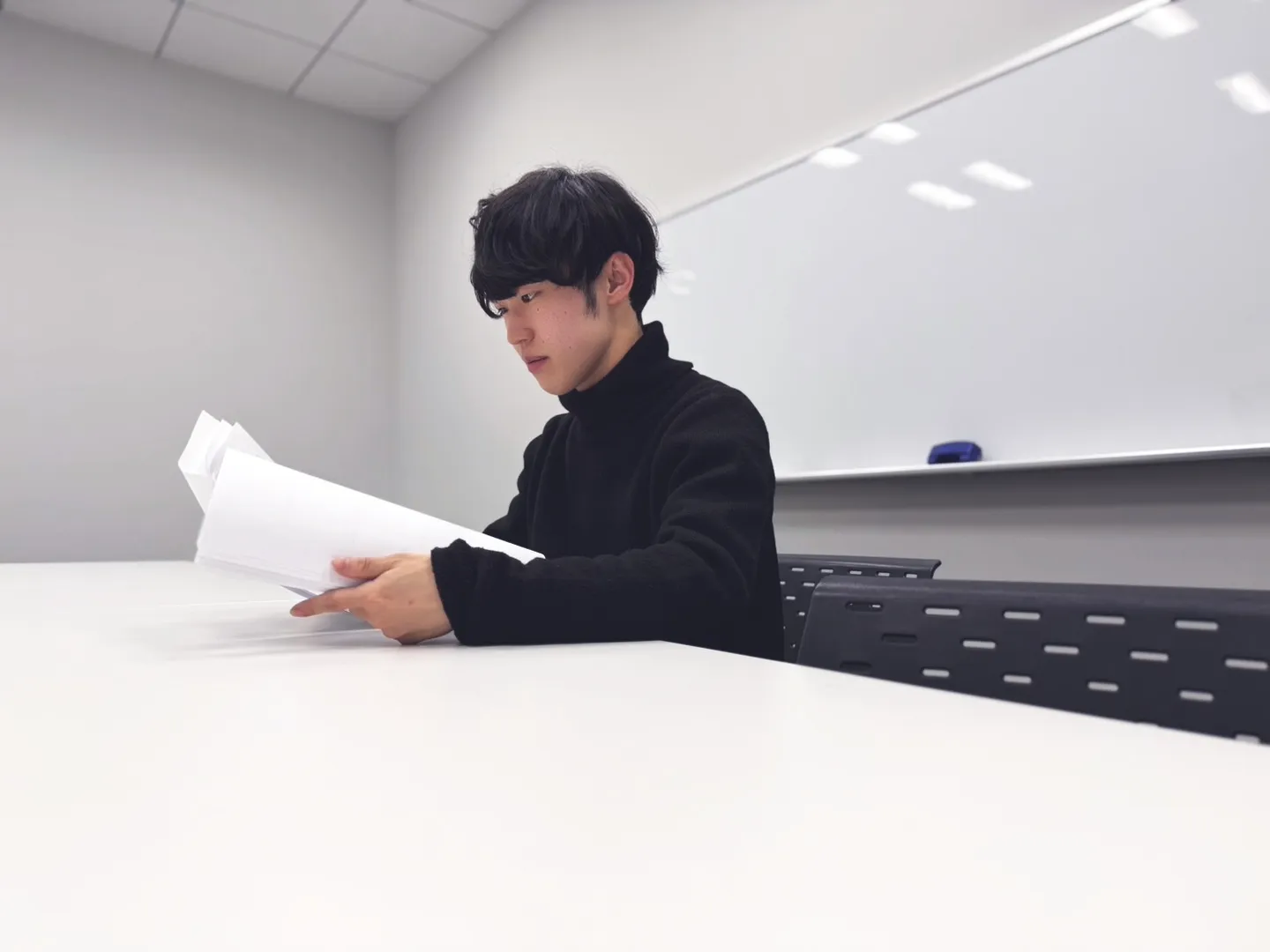
テレビ東京入社3年目局員・牧島による、連載エッセイ。「新しくて面白いコンテンツ」を生み出すため、大好きなお笑いライブに日参し、企画書作成に奮闘する。これはそんな日常の記録――。
こんにちは。
テレビ東京の牧島俊介です。さて...。
むかしむかし、私は天才だった。
企画力でも、編集能力でもない。勉強、あくまで勉強の話だ。
天才は、自分が天才であることを知らない。
私は勉強が嫌いで、勉強から逃げた。それでも勉強ができた。
ゆえに、自分の才能への興味が希薄だった。
自分は勉強が得意な方だと気づいていなかったという意味ではない。
苦労をしていないから、執着が生まれないのである。
そんな、あどけなくも無自覚の天才だった私に、突然の転機が訪れる。
「こいつ、東大卒なんですよ」
新米ADの私がロケで一般のご家庭を訪問したとき、先輩ディレクターが言った。
沸き立つお茶の間。揺れるダイニングテーブル。踊るサラダ。
物珍しい来客への好奇、不思議な生態と出会えた歓喜、どこか傑物めいた存在への敬意が交差する。
やがて、それは畏怖へと変わった。郊外の一軒家が小宇宙になる。
お母さんの口がかっぴらいたまま、固まった。お父さんの箸が宙で止まった。10歳の娘が、ヤンチャな兄貴に魂の抜けた視線を送る。
15秒の沈黙。
いや、10分だったかもしれない。やっと箸を置いたお父さんが切り出した。
「なんで東大生なのに、テレビ局に入ったの?」
東大生像の揺らぎへの困惑。そこには、世界の理が崩れ去る瞬間を目撃した者の混乱があった。
私はこの質問への答えに窮した。
東大卒だからこういう仕事に就こう、などと考えたことがなかったのだ。
就活でテレビ局以外は受けていなかった。
咄嗟に、ジョークで逃げることにした。弱毒で場を和ませる算段。
「法学部だったので、テレビ業界のコンプラを叩き直してやろうと思いまして」。
お茶の間の磁場がまた狂う。無自覚な天才たる私は、甘かった。
「えっ、東大法学部なの?」
ここで、〈初登場!柔らかな微笑がアトラクティブ!〉おばあちゃんが立ち上がった。
これはめでたいと、寿司の出前を頼み出す。
ビール、ビール、ビール。次々と缶が空いていく。
希少種の来訪を祝う宴だった。
楽しいロケの帰り道、夕暮れの住宅街を歩きながら、私は自覚した。
私がかつて天才だったと。
天才であるがゆえに、その価値を知らなかった。東大という肩書が持つ象徴性、人々が抱く憧憬、社会的な意味、すべてに対して私は無邪気だった。
そういえば、「どこの大学に通っていますか?」と聞かれたら、「一応、東大です」と謙遜して答えるのが東大生あるあるらしい。私には無縁の感性だった。
にわかにもどかしさが込み上げる。
何をしているんだ、私は。自覚がなかったばかりに。
天才であることをもっと楽しめばよかった。誇ればよかった。謳歌すればよかった。
高校生の頃、口数が少なく根暗だった私の成績に興味を持つ同級生はおらず、天才らしい称賛を浴びることはなかった。人知れず成績が良かった。東大に落ちても、別の大学がある。信念なく塾には通わず、漫然と受験生活を送り、だらしなく東大に入った。そして、軽率に在籍して卒業した。
ちゃんと毎日、通えばよかった。まるでブルジョワ気分の私は、赤門の前で足を止め、そこが俗世と神域の境界だと意識して深々と一礼し、中央を避けて端の方からくぐる。そんな気高き通学をしたらよかった。あるのかわからないけれど、素敵な立食パーティーに行って、「東大なんてすごいね」と持て囃され、困っているフリをしてみればよかった。『きっと、何気ない日常がキラキラと輝く宝物のような時間になっていただろうに』。
あの日、一軒の家庭で寿司をごちそうになり、私は遅すぎる覚醒を迎えた。
天才だった時代は、もう戻らない。
現在、テレビ局員になった私に、かつての面影はない。
入社してすぐ気づく。私は仕事ができる方ではないらしい。
テレビ局の仕事は番組単位のチームで動く。ADの役割は、ロケの段取り確認、機材手配、取材者への連絡、ロケ地の許可取り。1つの企画で10も20もの細かいタスクが同時に走り、それぞれに締切がある。
私はこの全体像を把握するのが壊滅的に苦手だった。どのタスクがどこまで進んでいるか、誰に何を伝えたか、他のスタッフを含めた番組全体の動きはどうなっているのか。頭の中で整理できない。同僚からスケジュール確認の連絡が来る。私だってわかんないよ、とそっと閉じる。答えないわけにはいかないよなとまた開く。それは半日後。メールを遡ってスケジュールを何とか把握し、返信する。かくして一通に返信するだけでもいたく疲弊する。そして把握できていないから、ミスをする。「お前以外みんな来ているよ」。ある日、スタッフ会議にいないのは私だけだった。
こんなにも仕事ができないとは思わなかった。勉強は無敵だったのに。
まず、サラリーマンとして挫折した。
では、クリエイターとしてはどうか。これまた天才ではない。
あの頃の、天才だった頃のような、無垢さがないのである。
自分の考えた新企画を同僚に披露する。「そんなの思いつかないよ」と言われれば、自分に天才性があるのではないかと浮き足立つ。私の制作した番組が、「SNSに激ヤバ感想が噴出」などと記事になれば、世間から偉才と認められたのではないかと顔を綻ばせる。その一方で、ディレクターとして編集したVTRに先輩社員から容赦ない指摘を受ければ、才能がないのではないかと落ち込む。企画がなかなか通らなければ、自分の才能が認められないと塞ぎ込む。
今の私は邪気まみれだ。
かつて天才だったからわかる。天才は、自分に才能があるかないか、ましてや自分の才能が評価されるかなど、一切気にならないのである。
悔しい!




