ビール瓶はなぜ茶色? 知らなかったお酒の知識に仰天! バーのマスターが“お酒の楽しみ方”を教えます!【書評】
PR 更新日:2025/1/8
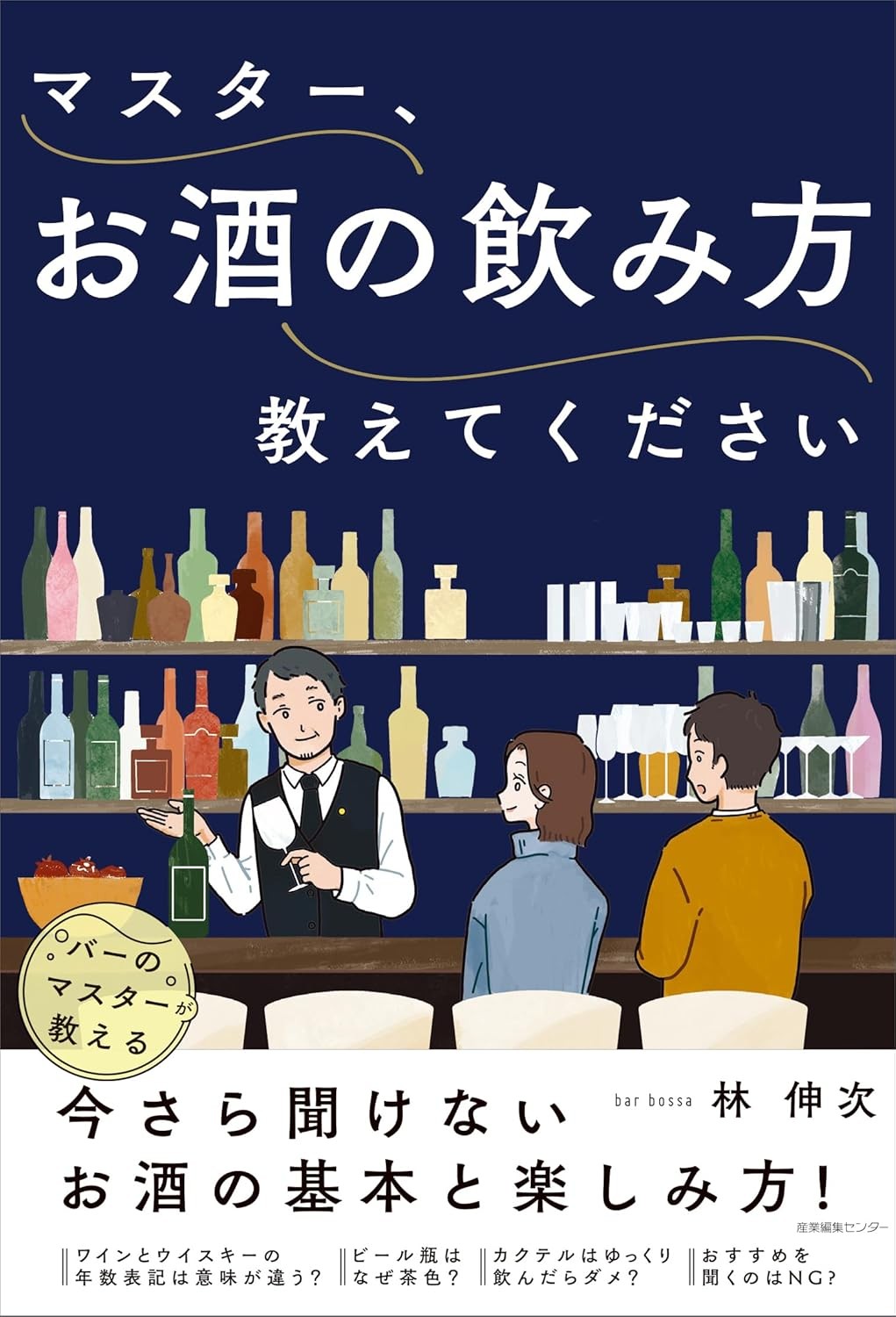
溜まったストレスや疲れを吹き飛ばすお酒は、大人だからこそ味わえる娯楽。だが、ふとした時に思うことがある。私は本当にお酒を楽しめているのだろうか…と。お酒の飲み方は誰かに教わる機会がなく、我流になってしまいやすいからだ。
『マスター、お酒の飲み方教えてください』(林伸次/産業編集センター)は、そんな気持ちになった時、役立つ一冊である。
著者は、渋谷のワインバー「bar bossa(バールボッサ)」の店主。本作は今さら聞けないお酒の基本知識や楽しみ方を“小説形式”で学べるというユニークな作りだ。
物語の舞台は、渋谷のバー。お酒の楽しみ方を知りたくてバーへやってきたのは、飲むのは好きだけどお酒には詳しくない20代の男性。マスターは彼と読者に分かりやすく、お酒の知識を教えてくれる。
例えば、日常の中で登場する機会が多いビールも奥深いお酒だ。ビールと一口に言っても種類はさまざま。ベルギーの修道院で造られている「トラピスト・ビール」や日本でメジャーな黄金色ビールよりも色が濃い「バス・ペールエール」などがあり、見た目や味の違いが楽しめる。
それぞれのビールに秘められたルーツに触れると、冷蔵庫の中で冷やしているビールがより尊く、愛しいものであるようにも思えてくるから不思議だ。
ところで、なぜビール瓶は茶色なのか、みなさんはご存じだろうか。マスターによれば、その理由はビールの風味を守るためだという。実はホップの苦み成分は、光を受けると化学変化しやすい。日光だけでなく、蛍光灯の光も風味を損なう原因になってしまうのだとか。
それを防ぐのが、茶色のビール瓶だ。茶色い瓶はホップを傷める光の波長をカットしやすいため、ビール瓶として使われているのだという。
ちなみに、透明の瓶に入っているメキシコの「コロナ」というビールは苦み成分が光で分解されにくく加工されているそう。一番おいしい状態でお酒を楽しむためには、こうした雑学も頭に入れておきたい。
本作ではビール以外にもワインや日本酒、ウイスキー、カクテルなどさまざまなお酒のルーツや嗜み方を紹介。ワインのテイスティングをする理由やウイスキーの産地と特徴など、意外と聞けない素朴な疑問も解決できる。知らなかった知識を得ると、いつもとは違うお酒を嗜みたいという気持ちもこみ上げてくることだろう。
また、舞台がバーであるからこそ、バーの楽しみ方を学べるのも本作の醍醐味である。マスターは、おすすめの服装や好みのお酒に出会いやすいオーダーの仕方、店内でのNGワードなど細かなルールを丁寧に教えてくれるので、バーに行ったことがない方は足を運びたくなるはず。
バー上級者の方も一目置かれる大人のふるまいや、お店側の気持ちを知ることで、より深いバーライフが楽しめそうだ。
著者は本作を通して、自分に合わない味のお酒を「不味い」という言葉で否定しないことの大切さを訴えかける。お酒は、提供してくれる人や製造に携わる人がいてこそ楽しめる飲み物。目の前にあるお酒には誰かの努力と想いが詰まっており、たとえ自分には合わなくても誰かにとっては「おいしいお酒」に成り得る。
そうした背景も理解してお酒を楽しむことこそ、大人である私たちに必要なマナーなのかもしれない。知らなかった扉が開くようなワクワク感を得られる本作を、ぜひお酒のお供にしてほしい。
文=古川諭香





