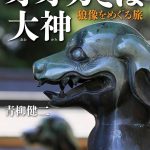狼像の謎を探るべく全国の神社へフィールドワーク! オオカミ(お犬さま)は火防・盗賊除けの守り神/新編オオカミは大神
公開日:2024/12/31
埼玉県寄居町にある川の博物館で平成29年7月15日から9月3日まで、特別展「神になったオオカミ 秩父山地のオオカミとお犬様信仰」が開催された。
この特別展は、動物としてのオオカミと、神として崇められたオオカミ(お犬さま)を紹介していた。展示物は、日本国内で三体のみ確認されているニホンオオカミの剝製(はくせい)(和歌山大学教育学部蔵)をはじめとして貴重なものが多く、狼好きの人間にとってはたまらないものだったと思う。
この関連イベントとして講演会「ニホンオオカミと三峯」が行われたので私も参加した。
三峯神社では、どのようにお犬さま(御眷属様)信仰が始まったのか、そして江戸時代には多くの人が参拝したこと、オオカミの民俗学的な視点からの話を主に、あとは秩父で発見された動物の毛皮がニホンオオカミのものだったとわかったときのエピソードなどが紹介された。
狼信仰は、一般的には、害獣の鹿や猪を食べてくれる益獣としての信仰から始まったが、とくに江戸で流行した理由は、火防・盗賊除けの守り神としてだったという。
犬は火事がボヤのうちに気がつき、また盗賊が店や蔵に侵入したときも騒いで知らせたり、賊を襲うという習性があることから、お犬さまが火防・盗賊除けの守り神となった。
江戸は「火災都市」と呼ばれるほど、大火が頻繁に発生した。ちなみに江戸時代の265年間に、江戸では49回もの大火が発生している。
浅草の浅草寺(せんそうじ)内に三峯神社があるが、ほかのお堂はみな南を向いているが、火防の守り神として三峯神社は東側の本堂を向いているそうだ。
火を消す水の水源地が三峯など秩父の山であったことも江戸の人たちが三峯を信仰した理由のひとつだったようだ。それは武蔵御嶽神社もそうで、江戸の水源地である奥多摩の山の森の大切さを感じていたのは神社関係者だけではなく、江戸の人たちもそうだったろう。

お犬さま信仰を追ったノンフィクション、小倉(おぐら)美惠子著『オオカミの護符』には、〈庶民がお山に参拝する行いの源には、遥かな古代から脈々と続いてきた「山への信仰」が息づいているように思われた。/私たちの暮らし、いや命は、今も変わらず山から生まれ出る水が支えてくれている〉とある。水への感謝は、山の信仰へとつながっているということなのだ。
現在、三峯神社は関東屈指のパワースポットとして知られているが、これは、現代版の自然崇拝・狼信仰といえなくもないだろう。動物・植物・岩・山・洞窟・川など、生物・無生物にかかわらず、すべてのものに霊が宿るという観念は、日本人のアニミズムの痕跡だそうだ。そういった霊的なものが宿るところは、現在「パワースポット」と呼ばれる。新しい自然崇拝の形だ。
<第2回に続く>