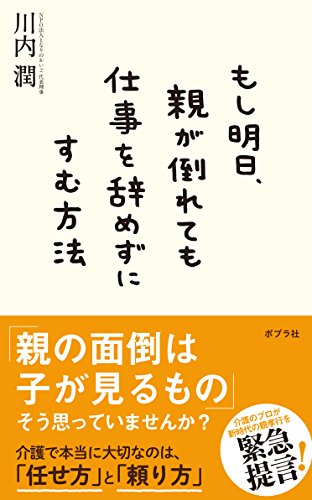もし明日、親が倒れたら…? 親の介護と仕事を両立させる方法
更新日:2018/3/19
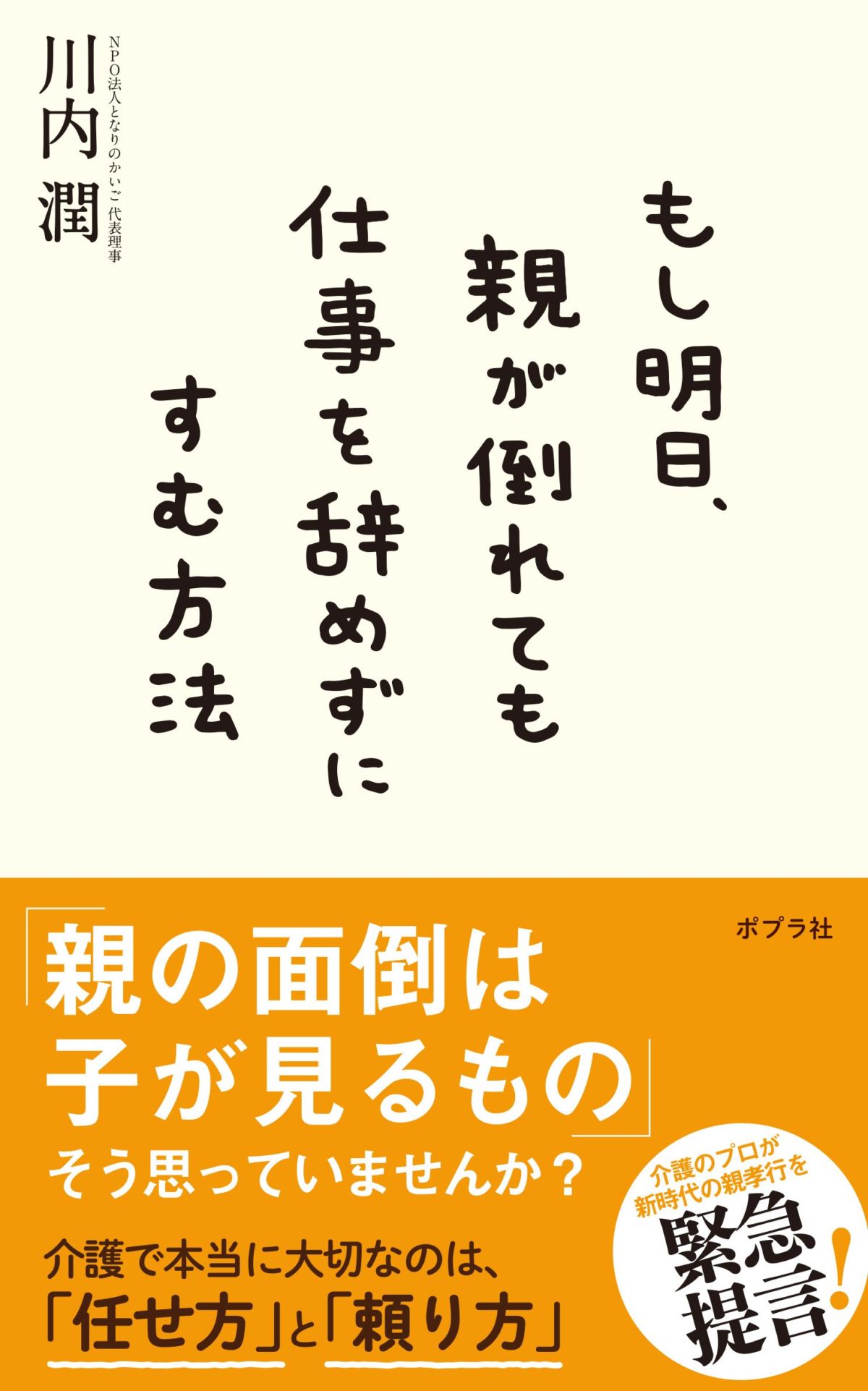
『もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法』(川内潤/ポプラ社)によると、介護のために仕事を辞めている人数は、毎年約10万人。そしてそのうちの約8割が女性だそう。驚くべき人数が介護のために離職しているのです。
そして介護のために転職した人の収入にも大きな変化があります。男性の転職前の平均年収が556.6万円。転職後には341.9万円。約4割も減っています。女性の場合、転職前の平均年収350.2万円から転職後は175.2万円と半減。
介護のために仕事の負担を減らそうとすると、収入はこんなにダウンしてしまいます。
親の介護が必要になったら、仕事を辞めなければいけないのでしょうか? 自分が直接介護をしないといけないのでしょうか? いえ、そんなことはありません。
■介護はチームで行うプロジェクト
「自分の仕事と、親孝行としての介護を、天秤にかけないでください」
「この2つは天秤にかける必要はまったくなくて、両方ともとるとができる」
このように「介護離職は誰のためにもならない」と断固として説くのは、著者の川内潤さん。外資系コンサル、在宅・施設介護職員を経て、NPO法人「となりのかいご」の代表理事をつとめる人物です。
介護離職をすれば、介護する側は経済的に行き詰まる、すると介護される親にもしわ寄せが来るといいます。介護はひとりで抱え込むのはあまりに過酷なプロジェクト。うまくアウトソーシングすることを川内さんは勧めています。
例えば「訪問入浴」という介護サービスがあります。1回あたりの負担は1500円。これを週3回利用していたとします。経済的に不安になってくると、その頻度を減らしたくなるのが人情です。週2回、週1回と回数を減らしていくと……、親の体が便まみれになってしまったときであっても、その体をきれいにするのは自分自身。
介護のプロである川内さんは、こんな状態を「自分の親だったらできない」と言います。
「面倒をみる人が自分しかいなければ風邪も引けない…自分が医者に行く暇さえなくなるでしょう。こうして親と一緒に自宅に引きこもり、社会と隔絶された状況でストレスをためてしまうと…最悪の場合、手をあげてしまうかもしれません」
介護に必要なのは、親孝行というふんわりとした意識ではなく、「チームで協力する」というプロジェクト管理の意識です。
■介護が必要になる2大パターン
働きながら、突然親の介護に直面する人は、だいたい次の2つのストーリーのどちらかに当てはまります。
(1)近距離別居の父親がある日倒れ、右半身麻痺に。一命をとりとめたものの病院担当者にこう告げられます。「うちは救急病院ですので、経過にもよりますが1か月ほどで退院していただきます」
(2)遠距離に住んでいるひとり暮らしの母。半年ほど前に帰省したときは変わりなかった。けれどある日の深夜、警察から「あなたのお母さんが道に迷っていたようなので保護しています」と。
こうなったとき、あなたらなどうしますか? 思いつくだけの対応を紙に記してみてください。回答の正誤は問題ではなく、自分の身に起きたこととして「介護」を具体的にイメージすることに意味があります。
介護は突然やってきます。そして介護に対する心がまえがなく、事前の情報収集をしていなかった人ほど、「介護離職もやむなし」といった誤った判断をしてしまいがちです。
■離職を防ぐための2つの「相談先」
こういった事態に直面したとき、「相談先」は大きく分けて2つあるようです。
ひとつは、「地域包括支援センター」。親が住んでいる市区町村名で検索するとすぐ出てきます。「地域包括支援センター」こそ介護の要。介護がはじまってからはもちろんのこと、必要になる前から、相談を受け、対策まで提案してくれる心強いサポーターである、「よろず相談所」です。親に認知症の兆候がなく、体がピンピンしていても、いざというときにどう備えておけばいいのか相談にのってくれる場所です。また遠方に住む親に「何かあったらいつでも電話してください」とお願いしておくと、初動がまったく違ってきます。
そして仕事をしている人のもうひとつの「相談先」は職場です。親の介護を会社に知られたくないと思う人は多いようです。けれども、親の介護で突然、仕事に穴を空けてしまうのは、あなただけではなく、職場も困ります。
職場に介護の可能性を伝えることは、出世にさしさわる、自分の評価が下がるなどと心配になる気持ちもわかります。ですが、職場としても早めの相談があれば、バックアップ体制をつくれるなど助かるのです。
■自社の介護サポート体制の情報収集を
職場でできることは、直属の上司に伝えるだけではありません。自社にどんな介護のサポート体制があるのか調べておくといいでしょう。あまり知られていませんが、介護のための休暇が取得できます。法律で定められた「介護休暇」という制度です。年に5日間、半日単位で利用できる休暇です。これはどんな企業でも取得できます。そして企業によっては、有給になるケースもあります。
加えて、「介護休業制度」という、休業期間中に給与の67%が雇用保険から支給される制度もあります。企業によって条件が多少変わるので、総務・人事の担当者に確認してみてください。
これらの制度やサポートを上手に利用すれば、たとえ遠方に住む親が認知症になったとしても、仕事を辞める必要はありません。
しかし、介護のことを職場に告げるのは、勇気がいります。誰にどのように伝えればいいのでしょうか。『もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法』に、そのあたりのことも詳しく記されています。
今、「介護」についての書籍は数多く出版されています。川内さん自身、外資系企業に勤めた経験のあるバリバリのビジネスパーソンでした。その経験をもとに同書では仕事と介護を両立するための手段と心がまえが記されています。 働くすべての人は今のうちに手に取っておきましょう。残念ながら親は年々、老いていきます。「ある日、突然」が来てからでは遅いのです。「元気なうちに」一読しておくことを強く勧めます。
どんな状況にあっても、「選択肢は常にある」と川内さんは言います。仕事や自分らしい生き方を手放さずに親を介護する方法を、親が元気なうちにぜひ学んでおきましょう。
文=武藤徉子