「お客様は神様」はもう古い!? 元CAが説く“よいサービスの条件”とは?
公開日:2018/3/26
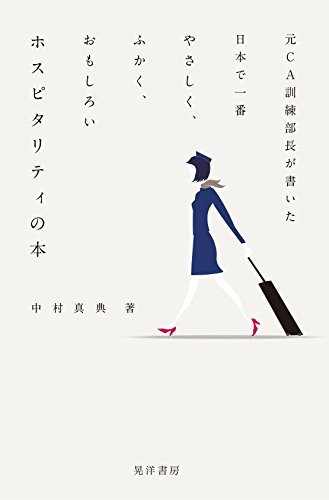
「お客様は神様」というキャッチフレーズは耳にする機会も多いサービス理念だが、モンスター○○と呼ばれるようなお客が増えてきている現代において、必ずしもお客様は神様だとは言いがたい。しかし、そんな風潮になってしまうのは、理想的なサービスの基準が人によって違うという理由もある。だからこそ、本書の冒頭に記載されている、「あなたにとってサービスとは何ですか」という問いはサービス業に携わっている方だけでなく、サービスを受ける側の心にも強く響く。
『元CA訓練部長が書いた日本で一番やさしく、ふかく、おもしろい ホスピタリティの本』(中村真典/晃洋書房)には航空会社でCAとしてサービスを提供してきた中村氏が自身の体験をもと、サービスの在り方が記されている。サービスを与える側になると誰だって「よいサービスをしたい」と考えるだろうが、よいサービスほど難しく不明確なものはない。なぜなら、よいサービスの中身は個人が抱いている理想像によって変わるからだ。
そのため中村氏は、サービスの定義を明確にさせることこそ、ホスピタリティの精神を育むために大切だと語っている。ホスピタリティという外来語を使われると、なんとなく身構えてしまったり、何をしたらいいのか分からなくなってしまったりする。ホスピタリティは直訳すると「心のこもったもてなし」という意味だ。人と人とが深く関わっていくためには、まず心が必要だ。きっとそれは、サービスを与えるときだけでなく受け取るときも同じ。ホスピタリティの精神は「目の前にいる相手を深く理解したい」という想いがあってこそ、生まれるものといえるだろう。
デジタル化社会である現代は、行うサービスの内容や組織の内情までが事細かに外部へ晒されてしまうことも多く、その場しのぎのサービスが通用しない時代が訪れてきている。だからこそ、自分の常識や経験だけで、目の前にいる相手が求めていることを理解した気になってはいけない。本当に心のこもったサービスは利益や人脈といった形ある報酬でなく、笑顔ややりがいといった実体のない宝も自身に与えてくれるのだ。
また、本書の中で筆者がもうひとつ興味を持ったのが「大きな石」の話だ。これは中村氏の先輩が語った、ある大学での話である。教壇の上に突然置かれた大きな甕(かめ)は、大きな石を10個入れると一杯になってしまった。しかし、石の大きさや入れる物自体を変えたりすれば、甕にまだ余裕があることに気づけるのだ。この話のおもしろいところは“人間には限りない底力がある”ということを示したいのではなく、“大きな石は先に入れないと甕に入らない”ということを教訓としているところにある。
ホスピタリティの精神を大切にしようとすると、自分よりも相手の気持ちを優先的に考えなければならないことが多く、自分自身が手一杯になってしまうこともある。だからこそ、心のこもったサービスを提供する前には、事前に“自分にとっての大きな石はなんなのか”を明らかにしておく必要もある。収入や目標、夢など大きな石は何でもいい。自分の原動力となってくれる大きな石を探すことは、自分の人生を自らの手で左右することにも繋がっていくのではないだろうか。
サービス業は心の対話によって成り立っている。目の前にいる相手ときちんと対話できれば、よいサービスよりワンランク上の“人を感動させられるサービス”も提供できるようになることだろう。
文=古川諭香





