かつて「小説」は有害メディアだった!? 俗悪とされた文学と道徳教育がむすびついた理由
公開日:2018/8/22
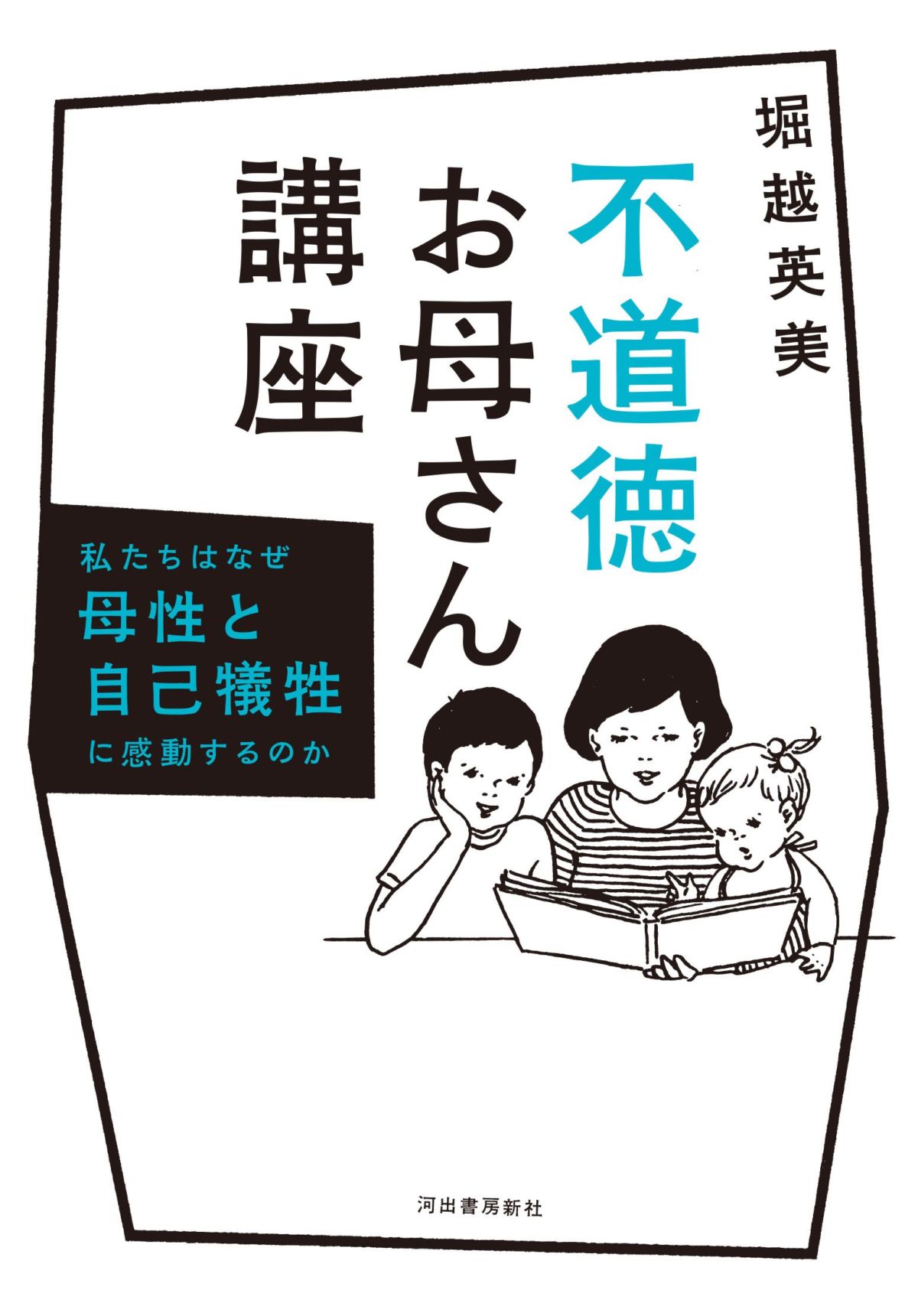
小学生の頃、親父に永井豪の漫画『ドロロンえん魔くん』を破り捨てられた。私が勉強よりも漫画に夢中になっていたのが原因ではあるけれど、ヒロインである雪子姫の艶めかしいヌードもいけなかったようだ。世間でもエロだの暴力シーンだのがある漫画やアニメは目の敵にされ、続くようにテレビゲームが子供の健全な育成を蝕むモノとして標的となり、現代ではインターネットでのSNSなどが非難の対象になっている。一方、もっぱら推奨されるのは読書で、その理由の一つは想像力を育むかららしい。ならば、蘭光生や綺羅光などの官能小説も推薦図書にすれば良いのにと皮肉交じりに思っていたところ、昔は小説が不健全なモノとして扱われていたと、『不道徳お母さん講座: 私たちはなぜ母性と自己犠牲に感動するのか』(堀越英美/河出書房新社)に記されていた。
小学校では今年2018年から道徳が正式な教科となり、中学校では来年から始まることになっているのだが、道徳教育のあり方に疑義を投げかけている本書では、近代教育の始まりでもある明治期からの道徳の変遷を膨大な資料をもとに提示していて、さながら道徳の「解体新書」だ。
福沢諭吉にならぶ啓蒙思想家の中村正直が明治期に発表したという、小説の有害性を論じる内容がなかなかに凄い。小説を好む人は「正人佳士(立派な人間)ではない」「労咳(肺結核)で死ぬ」「子供が盗み読んで破滅するか、早死にする」「悪い病気を持っている人が多い」といった具合で、科学的な検証を差し挟む余地も無いほどにコテンパンである。著者によれば、当時の小説観が現代と違うことも影響しているらしく、君子が天下国家を語ることを「大説」と呼び、その対義語として虚構である物語を卑下した呼び方が「小説」だという。つまりは、想像力を育むことに昔は価値を見出していなかったとも云える。
道徳教育には、しばしばお伽噺も取り入れられているが、『桃太郎』や『浦島太郎』などの扱われ方の移り変わりも面白い。昨今では、平和主義を唱える人が『桃太郎』の物語を、桃太郎たちと鬼とが仲良く暮らすように変えようなどと云っているらしいけれど、実は『桃太郎』の問題点を福沢諭吉も批判していた。曰く、宝物は鬼が大事にしている物で、宝物の主は鬼であるのに理由も無く奪うとは、桃太郎は盗人であり悪者であるなどと批判どころか、大変なお怒りよう。当時はまだ現代のように同一内容の本を全国販売しているわけではなかったため、地域や媒体によって内容がバラバラで、鬼を倒す大義名分など無くとも、人々の「鬼は悪者」という暗黙の了解によって物語が成立しており、それが近代教育には相応しくないと福沢諭吉は考えたのかもしれない。
では、いわば有害メディアであったはずの小説やお伽噺は、いかにして学校教育に入り込んでいったのかといえば、自由主義の観点から、子供たちを監視・拘束・禁止するような学校教育は「自信の無い一種のごまかし、偽り」を強いるばかりであるからと、文学の活用を求める声が挙がってきたそうで、さしずめ現代なら漫画作品が教科書に載るようなものだろう。歴史は繰り返すということか。
おそらく著者と私とでは、政治的な信条が異なると思われる。私は、道徳教育をカリキュラムに組み込むのは賛成だ。ただし、唯一無二のような答えを提示するのではなく、著者が提案しているように感想をディスカッションし、自分と違う考え方や感じ方があることを知る教材としてである。教育論においては、どうしても自身の思想信条や政治的なイデオロギーが対立軸になりやすい。しかし違いがあっても、子供の教育を論じるのなら、まずは虚心坦懐になって自ら学ぶ姿勢こそが大事だと思えた。
文=清水銀嶺





