「2人目だから流産してもいいじゃない」――上司に言われた衝撃的な言葉…“見えざる貧困”の実態とは
公開日:2018/12/31
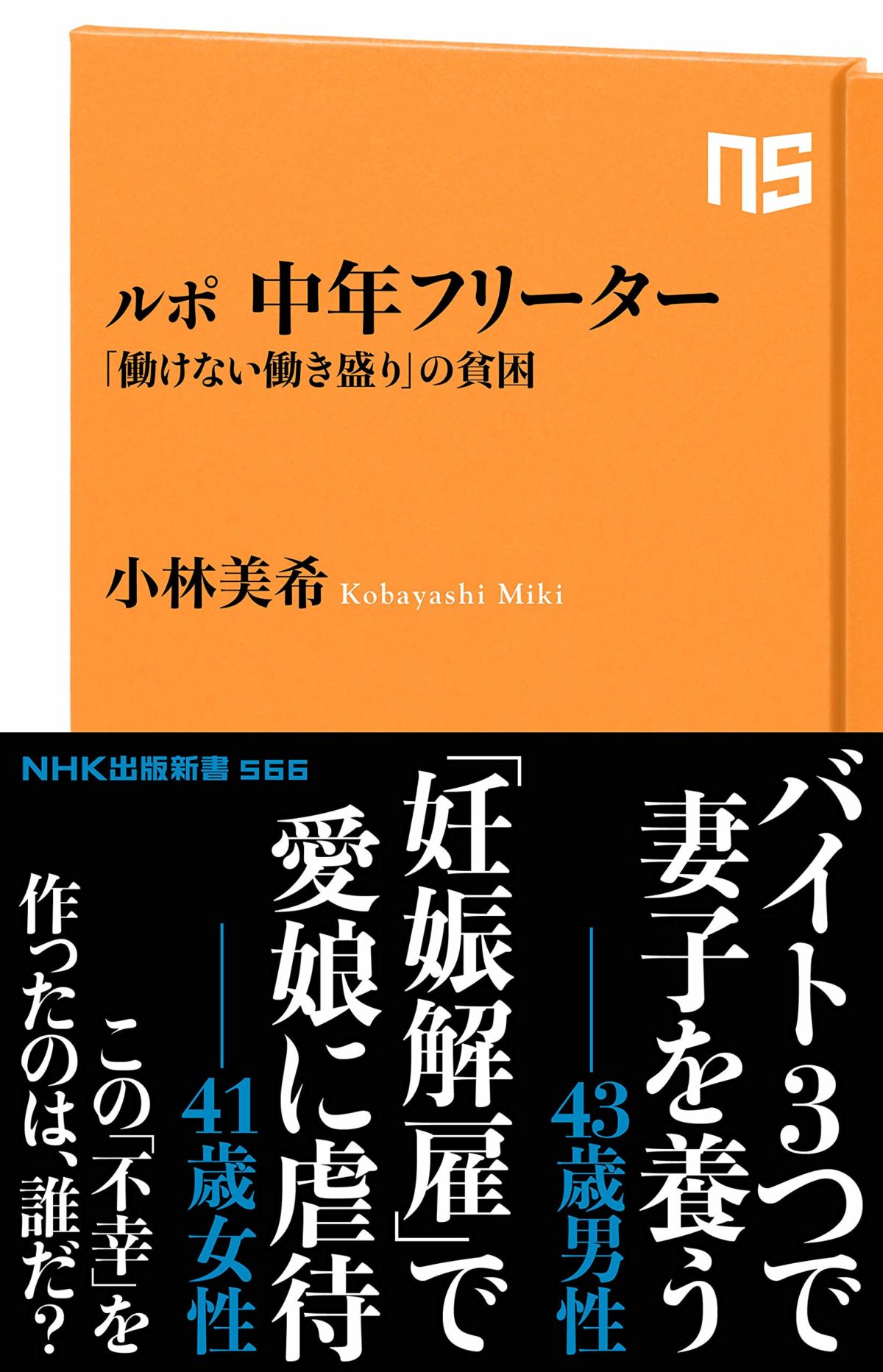
かつて厳しい就職活動を経験した「就職氷河期世代」や「ロスジェネ世代」と呼ばれる人々のうち、35~54歳になった今でも非正規雇用として働き続ける人のことをこう呼ぶ。
中年フリーター。
『ルポ 中年フリーター』(小林美希/NHK出版)は、「自己責任」という言葉では片付けられない、過酷で未来のない日常を懸命に生きる人々を切り取ったルポルタージュだ。景気が上向きとされる日本で、その恩恵を受けることなく今でも冷遇される彼らの現実を本書よりのぞいてみたい。
■休みがほとんどないのに手取りは少なくなった
野村武志さん(仮名:44歳)は、採用面接で決まって言われる言葉がある。
「44歳ですか。この年齢だと、チームリーダーになっていてもおかしくないですね」
この言葉を聞いた瞬間、落ちることを確信するそうだ。仕事探しにおいて年齢は大きな壁として立ちはだかる。
野村さんははじめからフリーターだったわけではない。専門学校を卒業後、まずは小さな旅行会社に正社員として就職した。しかしあまりに激務が続くせいで心身ともに疲弊。見切りをつけ、今後は中堅ドラッグストアに正社員として就職。仕事に精を出した野村さんは、やがて店長に昇進した。ところが、これが転落のはじまりだった。
「名ばかり店長」という言葉をニュースでよく聞く。日本の労働問題の1つであり、野村さんもこの過酷な試練を受けることになった。裁量や権限は任されておらず、急な欠員が出れば代わりに出勤し、残業代の支払いもない。休みがほとんどなくなったのに、手取り額は少なくなった。
そんな激務の中でも顧客のニーズを探って的確な商品を提案し、ドラッグストアの店長として薬剤の勉強を重ねた。野村さんの努力が功を奏し、店舗の売上に反映されたのだが…待遇が良くなることはなかった。店長手当を含む月給は24万円。搾取という言葉が頭を過る。
名ばかり店長になって4年が経つと、異変が起きた。まず顧客の来店が怖くなった。そのうち店への出勤も息ができなくなるほど辛くなった。理由もないのに激高したかと思えば、次の瞬間には落ち込んで涙があふれた。上司からのパワハラも重なり、うつ病を発症していた。ついに野村さんはドラッグストアを退職した。
ブラック企業に就職して心身を病んでしまい、退職するケースは珍しくない。日本は一度離職すると、その後は正社員としての就職が難しい傾向にある。結果、野村さんのように働く気があるものの離職し、心身が回復する頃には再就職が難しくなり、非正規雇用を転々とする未来が待っている。先の見えない状況に“無気力化”する中年フリーターが一定数存在する。これを、どう「自己責任」と説明できようか。
■2人目だから流産してもいいじゃない
女性の社会進出が目覚ましい昨今だが、一方で女性に望ましい職場環境が整備されていない現状がある。その1つが、妊娠による職場への影響を嫌悪する、マタハラだ。
「2人目だから流産してもいいじゃない」
介護職の加藤理恵さん(仮名:35歳)は、衝撃的な言葉を上司に言われた。
老人保健施設で働く加藤さんは、寝たきりの高齢者を介護する重労働をこなす。第1子を妊娠したとき、上司から「正社員なのだから、妊娠したせいで夜勤ができないとは言えない。みんな夜勤をこなしているから大丈夫」と告げられ、産前休業に入る直前まで夜勤を組み込まれた。切迫流産や切迫早産の傾向があったが、なんとか無事に出産。
ところが、第2子を妊娠しても同様のことが起こった。そればかりか上司に「夜勤が嫌なら辞めるかパートになるしかない」とまで言われた。生活のことを考え、無理をして働き続けた加藤さんは、妊娠9週目の夜勤明け、胎児が血の塊とともに押し出され、流産した。
職場にそのことを報告すると例の言葉を言われ、さらに「この仕事で流産は当たり前」と追い打ちをかけられた。
その後、休職した加藤さんだったが、夫の収入だけでは生活できず第1子の保育料を滞納する事態に陥り、やむを得ず復職。過酷な労働環境で身を削るように働いている。
多くの女性労働者は、妊娠によって休職する。それを嫌う職場がパワハラやマタハラを行い、ひどい場合では離職させ、女性たちを追い込む問題がある。女性にも満足な職にありつけない「中年フリーター」の側面があるのだが、結婚や妊娠などが“隠れみの”となり、問題が表面化しにくい。
さらに加藤さんのように、「子どもを諦めて生活のために働く」第2子以降を望めない「2人目不妊」は、日本の少子高齢化を加速させる絶望的な未来を呼び寄せる。女性へのパワハラやマタハラは労働問題だけでなく日本社会を崩壊させる大問題、ということを理解する職場はまだ少ない。
■中年フリーターは日本社会の被害者
中年フリーターは、日本社会の被害者といえる存在だ。文部科学省の「学校基本調査」によると、就職氷河期の真っ只中、2003年の大卒就職率は約55%。2人に1人が大学を卒業しても就職できなかった。さらに同年の20~24歳の完全失業率は約10%。10人に1人は無職だった。この超氷河期を経験した人々は、国や企業から見放され満足な雇用対策を受けられず、現在も正社員の枠に入れないまま年だけを取って、中年フリーターになってしまった。
そのツケが今、日本社会に大打撃を与えようとしている。総務省が統計を取った「就業構造基本調査」(2017年)をもとに、大卒男性の未婚率を雇用形態別にまとめると、35~39歳の派遣・契約社員の未婚率は約60%、パート・アルバイトになると約80%に及ぶ。2017年の出生数が過去最低の94万人を記録したことから、無関係といえるわけがない。日本の人口は減る一方。つまり生産人口が減ることでもあるので、今後の日本の経済成長が右肩下がりになる可能性を大いに示している。
さらに非正規雇用として人生を過ごすと、老後の先行きが立たなくなって生活保護の受給率が高まり、日本が破たんに追い込まれるかもしない。ある調査によると、フリーターの増加によって、潜在的な生活保護受給者が約77万人生まれると試算している。そうなると、追加の予算額が17兆円以上に及ぶという。国家予算が100兆円を超えそうな日本の財布にそんな余裕はない。
国税庁の「民間給与実態統計調査」を参考に、男性の平均年収を「1997年→2006年→2016年」で比べた場合、35~39歳は「589万円→555万円→512万円」、40~44歳では「645万円→629万円→563万円」と、それぞれ下がっている。
中年フリーターは「自己責任」ではない。誰が悪者か、はっきりしたはずだ。果たして日本の景気は上向きなのだろうか。今後、日本はどうなってしまうのだろうか。
本書には、就職氷河期世代を冷遇した日本社会に対する著者の怒りと、今後の日本の行く末を明らかにする嘆きが克明に記されている。本書を読んで、日本国民全員で考えたい。「中年フリーター」を生み出したのは、誰なのか。なぜ日本社会はこれほどまでに働きにくいのか。今後、日本はどう変わっていくべきなのか。
文=いのうえゆきひろ





