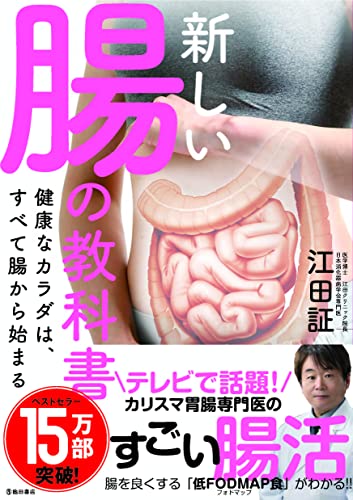腸と脳は連動している!? 旅行先で便秘、緊張で下痢する理由や解決レシピを紹介!
公開日:2019/7/21
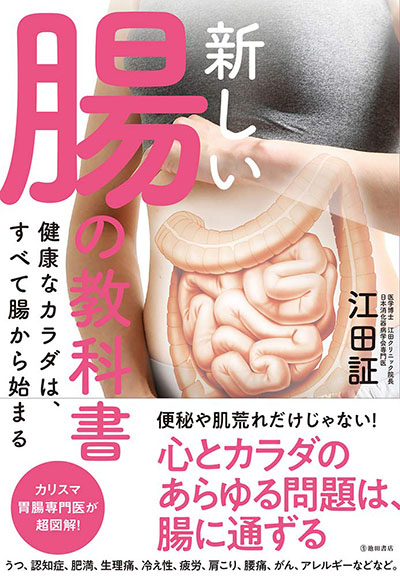
悩みを抱える人の多い便秘、下痢などの「お腹の不調」だけでなく、もっとさまざまな体や心の問題が、「腸」と関係があるといいます。近年医療機器や検査技術の進歩によりわかってきた最新の「腸」に関する知識がわかりやすくまとめられた1冊が『新しい腸の教科書 健康なカラダは、すべて腸から始まる』(江田証/池田書店)です。クリニックの院長として国内外の多数の患者さんを診察してきた著者の江田氏は、メディアでもカリスマ消化器専門医として知られています。
■腸はとても繊細な感覚器官
腸は、小腸と大腸から成り、身長の5倍ほどの長さと、テニスコートほどの広さを持つ器官。体全体の免疫細胞の約6割は腸に存在し、腸の神経細胞は約1億個もあるそうです。腸と聞いて誰もが思い浮かべるのは「食事で食べたものを消化・吸収するところ」でしょう。さらに近年の研究の結果、「腸管神経」のネットワークは「第二の脳」とも呼ばれ、腸が体のスイッチングハブとして脳や多くの臓器とも複雑に連携していることがわかってきました。
たとえば、「うつ」の患者には便秘や下痢が多いというデータも報告されており、腸内細菌が生み出した有害物質が認知症を招くともいわれているそう。腸の状態を整えることは、生理痛、肌荒れ、アレルギー、慢性疲労の改善ほか、脳や血管の健康、がんなどを未然に防ぐ“未病対策”にも役立ち、健康な体は腸から始まると著者は述べます。
その「腸内環境」を左右するのは、約100兆個も存在するといわれる腸内細菌です。善玉菌が悪玉菌より多いこと、さらに腸内細菌の種類が多いことも大事なので、一日にとる食品の種類を増やすことが大切なのだそうです。
■腸を整えるのに必要な食事と運動
整腸に効果的な4大食品(成分)は、ヨーグルトや納豆などの「発酵食品」、海藻などの「水溶性食物繊維」、青魚やアマニ油などに含まれる「EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)」、玉ねぎやバナナ、はちみつなどに含まれる「オリゴ糖」です。しかし、もともと腸が弱い人にとっては、お腹に良いとされるこれらの食品が、不調を招いてしまうことも。本書の解説を参考にしながら自分の体質や症状に合った食品を選び、不調を改善していきましょう。
また、食事と同様に大事なのは、腸をきちんと働かせて便を停滞させないようにすることです。「空腹時間」は腸にとってのおそうじタイムとなるので、意識的に空腹時間を作ることも必要です。具体的には、夕食は20時までに済ませるのがベスト。そうすると食事をしてから4時間後のちょっと空腹を感じるころから腸のおそうじタイムが始まります。
頼ってしまいがちな便秘薬は、長期間使用していると、腸に負担がかかりすぎ、元の健康な状態に戻すことが難しくなってしまうそう。薬にたよらず整腸したいですね。
他にも本書では、「腸と脳」「腸と心」の関連性についても、わかりやすい説明がされています。たとえば、旅行先で便秘になってしまうことが多いのは、不慣れな環境に脳がストレスを感じ、交感神経が働きすぎることで腸の動きが低下するため。また、緊張するとお腹がゴロゴロ…と下痢気味になってしまうのは、副交感神経が働きすぎるため。腸と脳、それぞれが感じたストレスは神経系のネットワークを通じて、互いに影響し合うのだそうです。
こうした腸のメカニズムを知り、自分の身体の不調と照らし合わせることで、腸をリセットする方法を見つけられる本書。腸がよみがえるレシピ、美腸マッサージ&ツボ押し、腸活体操などすぐチャレンジできそうなヒントも多数掲載されています。美容やアンチエイジングにはもちろんのこと、毎日気持ち良く過ごすために、腸内環境を良好に保ちたいものです。
文=泉ゆりこ