まず解決すべきはどれ? “問いグループ”の優先順位をつける/『哲学シンキング』⑦
公開日:2020/3/24
今後5年10年のビジネスは“問題解決型”の能力より、“課題発見型”の能力が重視される時代になる――。次の課題を見極める力を高め、世界のトップ人材に求められる新時代型の能力を身につけるための思考メソッド「哲学シンキング」を紹介します。
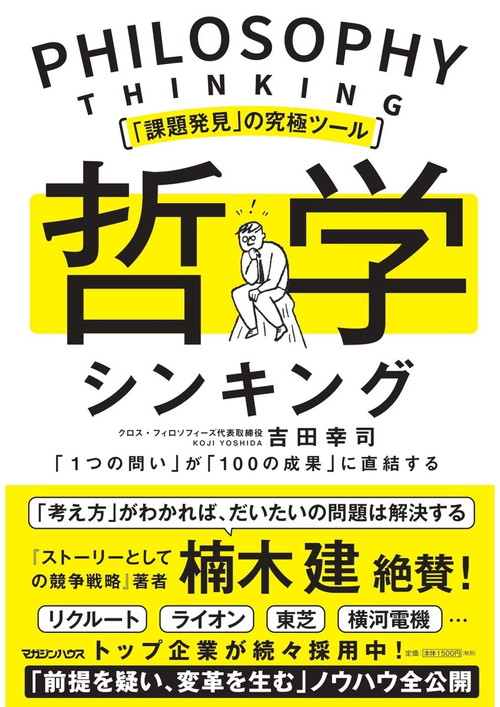
STEP2-B 問いを整理する:優先順位をつける
次に、問いのグループを、どこから考えていくか検討し、見通しを立てます。
なんらかの目的を達成するときに、やみくもに進んでは効率が悪いでしょう。それどころか進め方によっては、成功するはずのものも失敗してしまうかもしれません。
最初の課題を解決するのに、どこから考えたらいいか、戦略を立てたうえで考えはじめるのです。
前項でグループ分けしたAもBもCも、最初の課題に対して、それぞれ異なる視点を持った問いの集まりです。もう一度、見てみましょう。
A お店の売り上げアップ(伸ばし方)についての問い
B お客さん(潜在顧客を含む)の意識や来店理由についての問い
C おばあちゃんのお店を救うことの意味や理由についての問い
(「おばあちゃんが和菓子屋をやっている理由についての問い」)
では、みなさんなら、A、B、C、どれから考えはじめますか?
「おばあちゃんの和菓子屋を救うにはどうしたらいいのか」という問いについてなら、いちばん解決に近い視点は、売り上げアップを目指すAのグループや、お客さんを呼び込もうとするBのグループだと思う人が多いのではないでしょうか。
この意味で課題を解決するためには、AもしくはBから考えるのが最短ルートだ! ……と考えるひとは、「解決志向の考え方」にとらわれすぎています。
哲学シンキングでは、この方針の立て方は「よくない方針の立て方」です。
問いの答えを追求する習慣のあるひとは、最初に立てられたフレーム(=枠組み)のなかで考える傾向にあります。
しかし、どんな問いも、なんらかの隠れた前提や思い込みを宿しているものです。
「はじめに」でご紹介した「ほんとうのわたしは、何がしたいんだろう?」という問いの場合、「ほんとうのわたしがどこかに存在する」という前提や、「そのようなわたしがしたい、何かがどこかに、存在するはず!」という、強い思い込みともいえる前提が隠れていました。
問いの答えにばかり目を向けていると、「もしかしたら、ほんとうのわたしなんて存在しないのでは?」とか、「じつは、なにもしたくないわたしがいてもいいのでは?」という潜在的な問いに気づくことができません。
「おばあちゃんの和菓子屋を救うには、どうしたらいいのか」という問いも同様です。
もし、そもそも「売り上げアップ」をおばあちゃんが望んでいないとしたら、「売り上げアップ」の目標を達成するだけでは、真の課題を解決したことにはなりません。
売り上げは伸びたけれども、結果としておばあちゃんが不幸になったというのでは、本末転倒でしょう。
今回のケースの場合、たしかに最終的に知りたいのは、AもしくはBのグループに関する問いなのかもしれませんが、哲学シンキングで最初に考えるべき問いのグループは、Cになります。
なぜか?
売り上げアップやお客さんの増加の方法よりも、何をすれば真の課題解決となるのかが明確になるように、適切に課題を設定したいからです。一見、答えから遠そうに見える問いにヒントが隠れていることがあります。ですから、いくつか候補が上がったら「直接的には解決策にならなそうでも、モヤモヤ違和感がある問い」からスタートしてください。
では、Cの次に問うべきはどれでしょうか。
Aの売り上げアップの方法を考えるためには、Bの「どうしたらお客さんが来てくれるのか」を考える必要がありそうです。
その点で、Cの次にはBについて考え、最後にAについて考えるのがよさそうです。
C おばあちゃんのお店を救うことの意味や理由についての問い
(「おばあちゃんが和菓子屋をやっている理由についての問い」)
↓
B お客さん(潜在顧客を含む)の意識や来店理由についての問い
↓
A お店の売り上げアップ(伸ばし方)についての問い
「まず、おばあちゃんがお店のことをどう思っているか聞いてみないと!」
ただし、これはあくまでも、この段階における見通しにすぎません。
最初にCのグループの問いについて考えるうちに、Cの次にAを考えたほうがいいと気づくかもしれませんし、時間の都合で、AかB、いずれかしか考えられないかもしれません。
問いを整理する段階では、なんとなく青写真を描いておけば十分です。
哲学シンキングの大原則
解決策から遠そうに見えても、モヤモヤ違和感を感じる問いからスタートする





