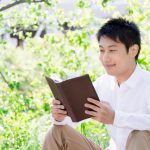忘れない読み方、知識を整理して定着させる読み方とは?/「記憶力」と「思考力」を高める読書の技術⑩
公開日:2020/7/25
忙しい人でも簡単にできる、法律家のすごい読み方を伝授! 木山 泰嗣氏が仕事にも学びにも効く読書法を紹介します。読解力はもちろん、記憶力、思考力のすべてを鍛えることができる著者独自の手法が満載です。
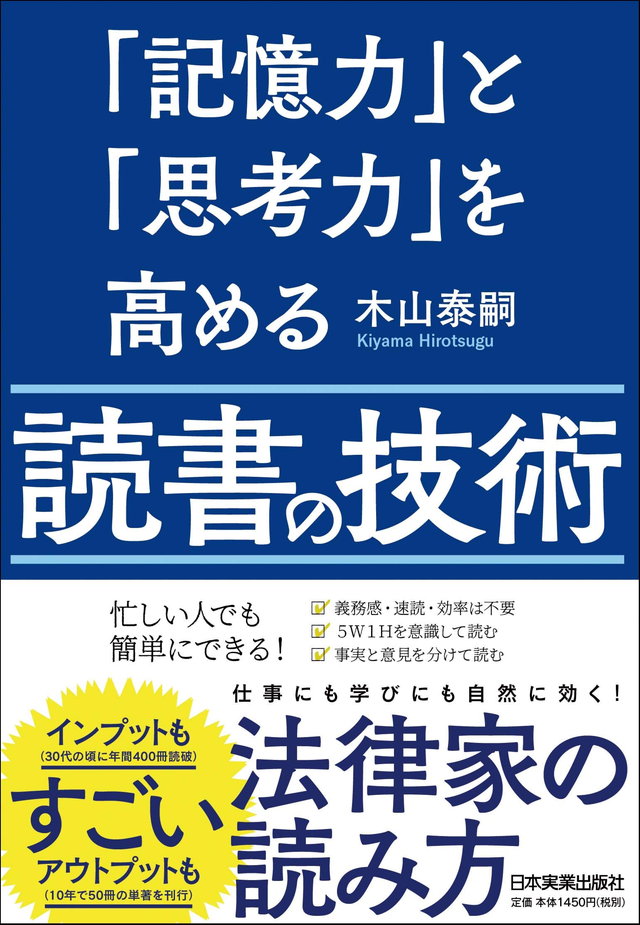
9 忘れない読み方、知識を整理して定着させる読み方
類書を数多く読めば暗記しなくてもいい
日常的に興味関心のある分野の本を読み続けている人は、その内容を自然に記憶し、知識を増やしていくはずです。
類書を大量に読めば、同じ言葉、専門用語、考え方、人物や会社の名前、エピソードなどが何度も繰り返し出てくるからです。そして、それらは、異なる著者の味付け(料理)により、手を変え品を変え、さまざまな切り口や角度で解説してくれるわけですから、それらの内容を深く理解することができます。なお、物語や漫画などでも、そのジャンルの本を読めば、ストーリーとして体験して記憶することができます。こうして得られた深い知識は長期間にわたって定着します。
もっとも、「ある専門分野について1から学びたい」あるいは「これを機会に徹底して勉強したい」という場合、例えば「会計学」「財政学」「税法」「アメリカ憲法」「所得税の歴史」などのような大学の授業を受けたことのない学問分野、あるいは「ベーシック・インカム」「消費税の軽減税率」などの最近よく耳にするようになったテーマを学ぼうとした場合に本を読むときは、それなりのコツがあります。
このような読書については、本を用いた勉強に近いといえます。学校の勉強や受験勉強との違いは、試験もなく、問題集もなく、先生の指導もなく、合格・不合格もない、という点です。そうした読書ならば、わたしの受験生時代とは異なり、時間を気にすることなく、純粋に興味のあるものを学べるということです。まずは、その恵まれた環境に感謝し、その環境を存分に活かすことだと思います。試験も、宿題も、レポートも、受験もなく、本を自由に読んで自ら学ぶだけでよい、と気楽に考えてください。
そして、自分で関心をもち、本を購入して学ぶということは、それだけ、ほかの普通の人よりも知的探求心が高いことを意味するとともに、有利な環境にあるといえるでしょう。なぜなら、時間的な余裕や精神的なゆとりがなければ、仕事をもちながら、いまの仕事に関係のない学問分野について読書をして学ぼうとする人はいないからです。
教養を深めたい人におススメの読書術
もっとも、10代や20代前半の若い人の場合には、「そもそも知らないことが多すぎて、会社や勤務先、取引先の人との会話についていけないことが多いので、何とかしなければいけない」というような事実上の強制力や向上心があって、学ぼうとされている人が多いかもしれません。
いずれにせよ、そのような教養を深めるための読書の場合は、まず新書を読むのがよいと思います。新書はサイズが少し小さめですが、文庫とは異なり細長いものです。この新書も、各出版社がさまざまなシリーズを出しています。そのため、新書だけでも、先ほど例示したような学問分野やテーマの出版物が、1冊ではなく何冊もあるはずです。それらを複数冊購入して立て続けに読むのがよいでしょう。
Amazonなどのネット書店のサイトであれば、テーマ検索ができますので、わたしはこの手の読書の場合は検索でできる限り多くの本を探して購入し、ある一定期間に立て続けにその分野の本を読み込みます。
また、最初は最も読みやすそうな本を選んで読みます。そして、本の中にもメモをして、次から次へと出てくる専門用語と体系をまずは整理していきます。その整理が1冊の本で終われば、次の本はかなり楽に読めます。なぜかといえば、すでに前の本で学んだ専門用語がまた同じように出てくるからです。
しかも、説明の仕方や切り口は異なるので、前に読んだ本ではわかりにくかったところが明確になったり、前に読んだ本には載っていなかったエピソードが出てきたりするため、すでに得ていた知識をベースにそれを広げていくことができるようになります。
「本当にわかっている」とは?
こうした読書も、基本は試験勉強のようにする必要はなく、楽しんで読めばよいと思いますが、読んで得た新しい知識を定着させる方法としては、本を読んだ後に歩くことをおススメします。
わたしが本を読む場所としては、カフェや電車の中など移動が必要な場所が多いので、読んだ後に外へ出て歩くことになります。そうすると、歩いているときに、自分の頭の中で、歩く前に読んだ本の内容を整理してまとめる時間が確保できます。歩いているときは本を取り出せませんので、何もみないで読んだ内容を整理できるか、声には出さず(声に出すと変な人だと思われますので注意してください)、自分の頭の中で講義(授業)をしてみるのです。
わたしはそうやって、知らない分野についても独学で学んできました。現在、わたしが大学で授業やゼミをもち、また以前はロースクールでも教えていた「税法(租税法)」も独学で学びました。大学時代にわたしは民事訴訟法のゼミに入っていましたし、司法試験もわたしが受験した時代では、試験科目に租税法はありませんでした。弁護士になってから税務訴訟という国税と戦う裁判を中心に仕事をしていたため、その仕事の必要に応じて、自分で本を読んで学んでいきました。しかし本格的に学んだのは、非常勤講師としてロースクールで授業を担当するようになってからで、学生に教えるために必死になって本を読んで学んだのです。「教える人が一番学ぶ」というのは、本当です。
わたしが大学教員になったのは、約5年前です。余談ですが、学生をみていつも思うのは、「学ぶことが本分の学生よりも、教える自分のほうがはるかに時間をかけて勉強しているなあ」ということです。
毎年教えている基礎的な授業でも、ゼミや大学院で学生が発表する判例研究であっても、授業の前に相当の時間をかけて予習をしますし、授業が終わった後も関連の論文などを読み込んでいます。教える側の緊張感が、学びを強制してくれているともいえますが、こうした仕事に関係する専門分野についても繰り返し学び続ければ、どんどん知識が増えて蓄積されていきます。
読書から少し話が離れましたが、いずれにせよ、試験勉強のような暗記をしようという発想はそこにはありません。社会人の学びは試験対策ではありませんから、人に説明できるかどうかを指標に本を読まれたらよいと思います。実際に説明しなくてもよいのですが、自分の頭の中で説明できるか試してみたらいかがでしょうか。
本当に理解しているということは、丸暗記していることではありません。いきなり「これって何ですか?」と他人から聞かれたときに、相手が誰であっても、その目の前にいる人に合わせた説明ができることだと思います。
それは、男性であっても女性であっても、小学生であっても、中学生・高校生・大学生であっても、社会人であっても、上司でも先輩でも部下でも後輩でも同僚でも、クライアントであっても、その人に合わせることができる、ということです。
それができるかどうかを考えながら、特定の分野の新書などを読み込んでいけば、暗記はしなくても、忘れることのない記憶として定着して、誰にでも説明できる知識が得られるはずです。